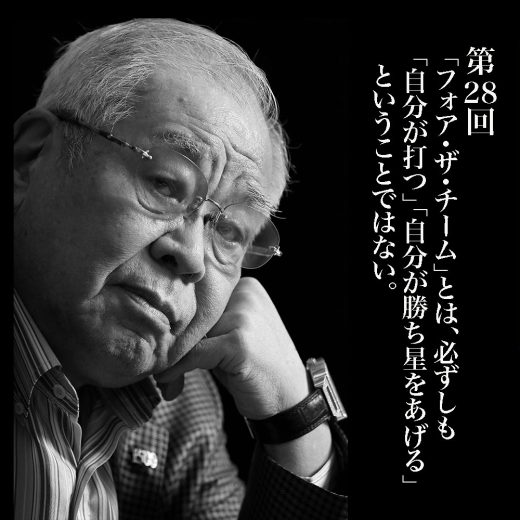戦後初の三冠王で、プロ野球4球団で指揮を執り、選手・監督として65年以上もプロ野球の世界で勝負してきた名将・野村克也監督。没後3年を経ても、野村語録に関する書籍は人気を誇る。それは彼の言葉に普遍性があるからだ。改めて野村監督の言葉を振り返り、一考のきっかけとしていただきたい。連載「ノムラの言霊」31回目。

優勝するために、まずは古田を育成
野村克也がヤクルト監督に就任した1990年、試合の進行をそっちのけで新人捕手・古田敦也にリードの指導を施していた。
「捕手は監督の分身である」
「捕手は試合におけるグラウンド上の監督である」
「チームを強くするには、捕手を育成するのが手っ取り早い」
たとえ監督1年目のペナントレースを捨ててでも、「急がば回れ」で捕手を育成していたようにも見て取れた。結果、リーグ順位は5位に終わるも、古田は新人捕手として史上初のゴールデングラブ賞に輝くことになる。
捕手が育てば投手も育つ。川崎憲次郎は1990年に12勝、1991年に14勝を挙げた。西村龍次は1990年に10勝、1991年に15勝だった。
また、野村の指導で打者も育った。「三冠王を狙う」と豪語した落合博満(中日)に対し、ヤクルトの選手は各部門からプレッシャーをかけた。
落合は1991年に打率.3395(2位)、37本塁打(1位)、91打点(2位)を記録したが、同年の古田は打率.3398(1位)をマークし、池山隆寛が32本塁打(2位)、広沢克実が99打点(1位)だった。
そこで野村の言葉が飛び出した。
「15勝級の投手がふたり。首位打者、本塁打王、打点王、盗塁王(飯田哲也)を狙う選手が育ってきた。監督就任1年目に種をまき、2年目に水をやり、3年目に花を咲かせてみせましょう」
まさに有言実行。監督就任3年目の1992年、途中9連敗など何度もしおれそうになりながらもリーグ優勝を果たす。野村は「ヤクルト」という名の大輪を、神宮の地に咲かせたのだ。
チームの成熟には3年の月日が必要
「3年目に花を咲かせる」は、「石の上にも3年」の野村流の言い換えだ。
監督を3年やれば野球観がチーム内に浸透していくし、その方向性に合わせた選手も育成できる。だが、実際にはそう順風満帆に事が進むことはなく、2年目終了時に契約を解かれ、志半ばにして無念の退陣というケースも少なくない。球団がチームの発展を待ってくれないのだ。
過去、「監督就任3年目」で優勝した例を挙げてみる。
パ・リーグではロッテオリオンズ(現・ロッテ)の濃人渉が3位(1968年)、3位(1969年)、優勝(1970年)。西武の東尾修が3位(1995年)、3位(1996年)、優勝(1997年)。楽天の星野仙一が5位(2011年)、4位(2012年)、優勝(2013年)。
セ・リーグでは、中日の与那嶺要が3位(1972年)、3位(1973年)、優勝(1974年)。広島の山本浩二が2位(1989年)、2位(1990年)、優勝(1991年)だ。
いずれも監督自身が指導者として円熟し、そのリーグの野球に慣れ、選手たちも成長して充実の様相を呈していた。
他にも、1976年シーズンの途中からの監督就任ではあるが、ヤクルトの広岡達朗が5位(1976年)、2位(1977年)、優勝(1978年)。メジャー野球を視察した広岡は、「先発ローテーションの確立」と「勝ち試合での抑え投手」の重要性をチームの戦略として持ち込む。
また、巨人コンプレックスを排除するために、1978年に初めてアメリカのユマで海外キャンプを敢行し、「われわれはメジャーリーガーとともに練習を行ってきた」という自信とプライドを選手たちに植え付けた。
現在、ともに2年連続最下位の日本ハム・新庄剛志、中日・立浪和義には、「石の上にも3年」「3度目の正直」を期待してやまない。
なかなか“新人”では受賞できない新人王
野村はプロ2年目に「戦力外」を通告されたが、球団に頼み込んで撤回してもらった。
冬の夜、合宿所でスイングを繰り返した。バットを握る手から血が出てきた。涙と鼻水で顔がクシャクシャになった。しかし、故郷の母親のために、少しでも仕送りを増やしたかった。
「いつになるかわからないけど、いつかきっと楽をさせてあげるから」
「努力には即効性はないけれど、努力は決して野球人を裏切らない」。野村はそう思い、胸に秘め、バットをひたすら振り続けた。その甲斐あって、3年目の1956年には捕手のレギュラーを奪取。しかし、その年のパ・リーグ新人王には、終生のライバルとなる西鉄・稲尾和久が選ばれた。
それでも野村は4年目に本塁打王となり、野球選手として大きな躍進を遂げた。南海、ヤクルト監督時代にも、地道な努力は必ず報われるという思いがあったに違いない。
さて、2023年の新人王はセ・リーグがプロ2年目の阪神・村上頌樹投手(MVPも受賞)、パ・リーグがプロ3年目のオリックス・山下舜平大投手が受賞した。
昔に比べ、入団1年目で新人王を受賞する選手が減ってきている。アマチュア野球とプロ野球の実力差が開いたのだろうか? 特にパ・リーグは2016年から8シーズン中、7シーズンがプロ2年目以降の選手である。
2016年の日本ハム・高梨裕稔投手(3年目)、2017年の西武・源田壮亮内野手(1年目)、2018年の楽天・田中和基外野手(2年目)、2019年のソフトバンク・高橋礼投手(2年目)、2020年の西武・平良海馬投手(3年目)、2021年のオリックス・宮城大弥投手(2年目)、2022年の西武・水上由伸投手(2年目)だ。
「1年目に種をまき、2年目に水をやり、3年目に花を咲かせてみせましょう」
勝負の世界で結果を出したければ、焦らず急がず、まずは下地をつくっていくことこそが大事なのだ。
まとめ
「努力には即効性はないけれど、努力は決して野球人を裏切らない」。地道な努力は、必ずや実を結ぶ。選手も指導者も、流した汗が肥やしになることを信じて邁進あるのみだ。
著者:中街秀正/Hidemasa Nakamachi
大学院にてスポーツクラブ・マネジメント(スポーツ組織の管理運営、選手のセカンドキャリアなど)を学ぶ。またプロ野球記者として現場取材歴30年。野村克也氏の書籍10冊以上の企画・取材に携わる。