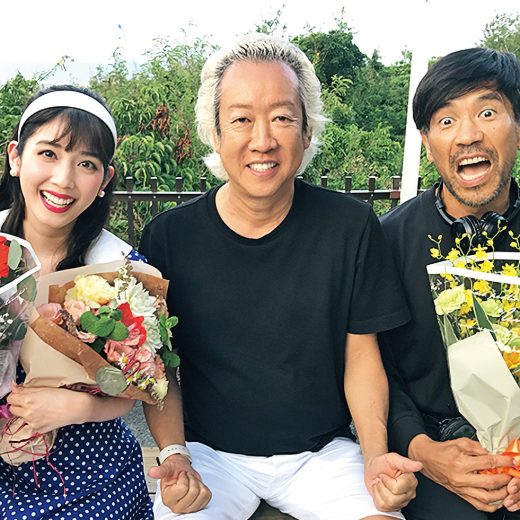まだまだ謎に包まれた男、福田淳(あつし)。なぜだかいつも周りの人間から頼られ、案件を持ち込まれ、奔走する。そして常に国内外を飛び回り、一日一日を本気で楽しむ。多岐にわたる企業の経営を担い、タブーをタブー視せず、変化を模索する男の人生哲学とは? 第10回目は生き方を左右する生活の拠点を複数持つ理由とその作法。

1965年大阪府生まれ。連続起業家。スピーディグループCEO、STARTO ENTERTAINMENT創業CEO、ソニー・デジタル・エンタテインメント創業CEO。世界19ヵ国での出版事業、日本でタレントエージェント、LAでアートギャラリー運営、リゾート施設展開・無農薬農場開発、スタートアップ投資など世界中でビジネスを展開する。『好きな人が好きなことは好きになる』など著書多数。
リノベも0からでも。家を造り続けることの愉しさ
ビジネスの拠点のひとつにしているドバイのオフィスに、現在ウォシュレットを取りつける工事の真っ最中です。工事スタッフの方は「TOTOを取りつけるのは初めてだから、ちょっと難航している」とおっしゃっていました(アラブで人気の日本ブランドはTOTOとトヨタと虎屋なんです)。
ビジネスで訪れることが多い場所には、できるだけ自分のベースをつくるようにしています。その土地のことをもっと知りたいから、そこに拠点をつくって、土地のコミュニティに入っていく。訪れるたびに土地の人に「おかえり」と言ってもらえる場所が、現在、世界で7つほど僕にはあります。
古地図をじっくり眺めて家造りがスタート
0から家を建てることも、できあがっている家をリノベーションすることもあります。どちらの場合も、その土地の風土を意識して家を造ることを心がけています。自分勝手な建物を建てるのではなく、地形や気候に合わせて素材やデザインを組み立てます。地域と一体化しないとコミュニティの一員になれないと思うからです。
アメリカのパームデザートに家を造った際は、ミッドセンチュリーの建築(1950〜60年代)をリノベーションしました。室内には当時の家具を置き、現地のアーティストが描いたカラフルなアートを組み合わせて配置したんです。パームデザートはマリリン・モンローやフランク・シナトラが別荘を建てたことでも知られる避暑地です。彼らは毎夜パーティを開き街の社交文化を牽引したそう。ハリウッドから2時間以内で来ることができる「ハリウッドの庭」(軽井沢みたいな感じ?)として栄えました。
21世紀になってからゲイカルチャーが持ちこまれ、カラフルなインテリアやブティックホテルが大人気です。その後、“パームスタイル”と言って、ロスの人達の憧れの場所となりました。そんな歴史を踏まえて、パームデザートの我が家は地元のアンティーク屋「Stewart Galleries」で買った家具に、カラフルな地元の人気アーティストDavid Travisのアートを設置しているというわけです。彼らとも友達となり、そこから地元コミュニティとさらに親交が持てるようになりました。
特にアートは、このパームデザートの燦々と降り注ぐ太陽光と、高くそびえるパームツリーや山々の緑にとても映える。東京では絶対似合わないのではないかと思うほどカラフル。色彩感覚というのはそこにいる人間の目の色、光、空気が大きく影響してくるのだと思います(やっぱりアートは地産地消!)。
私はたいていの場合、「この土地に家を造ろう」と思ったら、まず古地図をじっくり眺めます。「ここはかつて川だったのか」とわかると、なるほど、ならばちょっと小高くなっているこの土地は洪水の危険もなく安全で、かつて身分の高い人が住んでいたに違いないと思いを馳せる時間もまた楽しい。川があれば森も潤っていたでしょう。そして川の危険から逃れつつもその美しい川と森の恩恵を受けられる高台はやっぱり家の立地としては最高。そして思うのです、「セレブがやたら高台に住みたがるのは、人間の本能なのかも」と(世界中のリッチが住む家を集めたインスタを見たら、地域は違えど、家のポジションや造りは、ほぼ一緒!?)。
お金をどれくらい面白いことに変えられるか
「あちこちに家を持つのは資産形成のため?」とよく聞かれます。とんでもないです。資産を増やすだけなら、家を造るお金で暗号資産を数年持っておいたほうがいいですよね。でもそれじゃ面白くないんです。人の生き方って、お金の使い方で決まる。僕はクリエイティヴに使いたい。お金を1円でも多く増やして子孫に残そうとするのも、ひとつの生き方でしょう。でも僕はそんなの興味ない。自分の子供にもお金を残さないと宣言しています。自分もサラリーマンの家に育ち、初任給で額面16万円からビジネスマンを始めましたから、子供も頑張ればいいと思います(人間健康ならいつでもゼロから始められます!)。
生きるということは与えられた人生の全時間をいかに有効に使うかどうか、それしかないと考えています。世界を股にかけ、すべてを知り尽くすために働き、本を読み、移動し、人に会い続けるのです。だから僕にとって家造りは、人生を豊かでクリエイティヴにしてくれるツールなのだと思います。
色々なコミュニティの一員として人に認めてもらうために、意識していることがあります。それは「ひとりでその土地に乗りこむ」ことです。仲間をゾロゾロ引き連れていたら、その輪から抜けられません。だから独りで乗りこみ、そして現地で仲間を増やしていく。これが僕の人生の冒険なんです(なんだかロールプレイングゲームみたいで面白いでしょ?)。
世界中のストリートを歩いていると、文化は低層階の住宅や商店が集まっていることに気づきます。お肉屋さんがあり、カフェがあり、ギャラリーがある。ふらっと入ってみようかなと思う。これがビルの38階のお肉屋さんだとそうはいきませんよね。お肉屋さんの2階にはお店の家族が住んでいてお客さんは、みんなそこの家の息子の顔を知っている、そんなところからコミュニティも文化も生まれます。タワマンだと、そうはいかない。
ちなみに日本のある高級な旅館に泊まった際に、あまりに敷地が広すぎて「一度入ったらもう今日は出られません」と言われたことがあります。旅館のお料理もいいけれど、そのあとは町のスナックにも行きたかった、その土地の文化とコミュニティと交わりたかった。僕はそういうことに関心があるんです(オールインクルーシブって言葉に束縛を感じます!)。
ドバイのような熱い地域は構造上タワーが林立しレジデンスや商業施設も無数にありますが、そんな夏に40度になる地域でも、ウォーカブル(歩ける)な場所は存在します。モールです。世界で一番巨大なドバイモールは一日では歩ききれません。なかにはスキー場やダイビングできる水族館まであります! ヴェガスのような砂漠が都市になったように、人が住むところにはストリートができ、人は触れ合いを求めるものなのです。
Editor’s Note|能登に行くからには地元が潤う挑戦を
友人の付き添いで能登に行くことになり、福田さんはその際もまたその土地の風土、地理、歴史を調べていたそう。震災で廃業を余儀なくされたジン蒸留所を、ウィスキーの蒸留所として再建できないかと、現在取り組んでいるところです。「しかもAIをつかってウイスキーを造れないかと試行錯誤してるんですよ。さらに定置網漁漁業権を獲得し、活用、その収益を継続して能登に寄付できないかとも考えています」。能登発の新しいウイスキーブランドと復興支援の新たな仕組みが誕生するのも、もうすぐかも!?