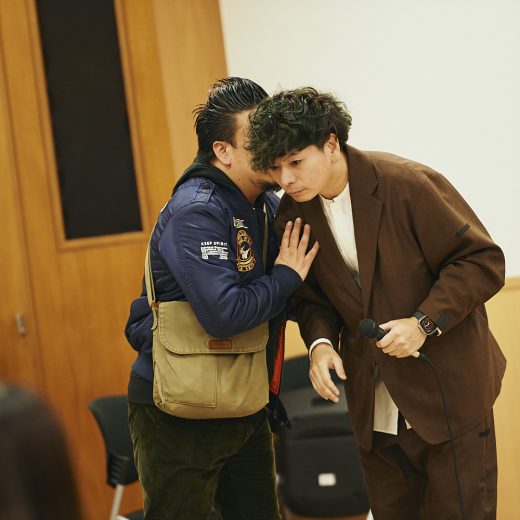放送作家、NSC(吉本総合芸能学院)10年連続人気1位であり、王者「令和ロマン」をはじめ、多くの教え子を2024年M-1決勝に輩出した桝本壮志のコラム。

「リーダー職の会社員です。桝本さんの新刊を読んで、分かりづらいことを言語化するスキル、例え話がとても上手な方だと思いました。どのように言語化のスキルを高めたのか、コツがあれば教えてください」という相談をいただきました。
まずは、拙著 『時間と自信を奪う人とは距離を置く』を読んでくださってありがとうございます。
そして、本の中でもふれましたが、かつての僕も「伝える言葉を持っていなかったリーダー」なので、安心してください。
「リーダー」という役職を言い換えると、業務上の曖昧なこと・抽象的なことを「整理された言葉で伝える人」のこと。
しかし、ただ整理された言葉では人は動きません。
最大の目的は"受け手の頭が整理されること"なので、私たちリーダーは、受け手の解像度を上げる"具体化力"が必要なのです。
そこで今回は、具体化力がアップする「吉本NSC流の言語化のコツ」を2つのステップで押さえていきたいと思います。
ステップ①:具体化力アップのコツは「あるある大喜利」
まず、リーダーは、高尚な「具体化」をする必要はありません。「具体化」という言葉自体がカタいので、例え話くらいの感覚でいいと思います。
そして、この例え話は、お笑いのジャンルで言うところの「あるある」。
共通体験があり、同じイメージが浮かびやすい、学校あるある、恋愛あるあるくらいのレベルでいいのです。
例えば、僕は吉本NSCで「学校あるある大喜利」をしながら授業を運営しています。
- 「最初から漫才を上手にやろうとして個性がない生徒」
➡「最初から上手にやらなくていいよ。『ノートの1ページ目はキレイな字で書こう』と思っても長続きしないでしょ? ムダに力まないで気楽にやろうよ」 - 「同期の中で、なぜか一人だけ叱られた生徒」
➡「たまたまだよ。『日付と出席番号が合っただけで先生に指名される』くらい深い意味がないことも多いよ」 - 「大人しいタイプで、なかなか集団トークに入れない生徒」
➡「声がデカい芸人だけが正解じゃないからね。『足が速い男子はモテる』くらいの感覚でやり過ごして、自分のスタンスを大切にしていこう」
などなど、人材育成で伝えるべきことのコアは、経験上、すべて「あるある」で例えることが可能です。
このとき気をつけたいのは、けして「子ども扱い」はしないこと。あくまで質の高いレクチャーや指示をデフォルトにしつつ、解像度を上げるスパイスとして「あるある」をふりかけることです。
では、より高度な言語化のコツを次のステップでシェアしていきましょう。
ステップ②:言語化を高める「普遍のシステム」
言語化を磨くために、僕は街を歩きながら、多くの人が認知している「普遍のシステムや文化」に目を向けています。例えば……
- 「日本」の読みかたは、「にほん」でも「にっぽん」でもいい
- 東海道新幹線には「こだま・ひかり・のぞみ」の3種類がある
- コンビニの割り箸から「つまようじ」が消えた
- 信号機のメロディが「とうりゃんせ」から「鳥の声」になった
などなど、様々な普遍的な事象をインプットしておくと、あらゆる場面で「例え」や「具体化」を補ってくれるのです。例えば……
- チームがAかBかの二択で激論をしている場合
➡「両方を試してみる選択肢Cはないだろうか。日本の読みかたが、『にほん』でも『にっぽん』でもいいように」 - チームが成果ばかりに気を取られ、あくせくしたり、慎重さが失われたりしている場合
➡「急ぐばかりが正解じゃない。『のぞみ』でも『こだま』でも、同じ目的地には必ずつく」 - いつまでも伝統やルールに縛られている組織の場合
➡「手放す勇気も必要ではないか。つまようじが消えても、信号機のメロディが変わっても、平穏に生活できている」
など、多くの人が知っている「普遍」は、私たちの伝える力の強力なサポーターにもなってくれるのです。
語彙力を高めるために読書や文章を書くことも有用ですが、僕は「街の歩きかた」を変えてみることも大切だと考えているんですね。
ではまた来週、別のテーマでお逢いしましょう。

1975年広島県生まれ。放送作家として多数の番組を担当。タレント養成所・吉本総合芸能学院(NSC)講師。王者「令和ロマン」をはじめ、多くの教え子を2024年M-1決勝に輩出。
新著『時間と自信を奪う人とは距離を置く』が絶賛発売中!
桝本壮志へのお悩み相談はコチラまで。