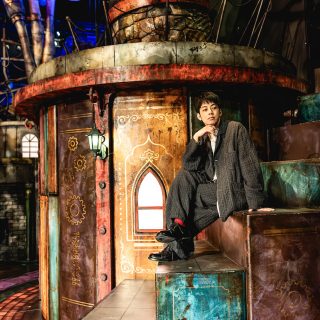子供のレベルにばらつきがあるチームで、指導者を悩ませるのが、出場時間とポジションの問題。育成歴30年のFC町田ゼルビアのアカデミーダイレクター・菅澤大我流、“子供がサッカーを嫌いにならない”ための策を伝授。#第3回 連載記事はコチラ

子供がイヤだというポジションにはつかせない
――少年団や街クラブでよく聞く悩みの一つが、試合の出場時間です。勝つことを重視してレギュラーを固定するチームや、監督やコーチが、お気に入りを中心に起用するというチームも珍しくありません。一方で、公平を期すために、出場時間を均等にした結果、なかなか勝てないというチームも見受けられます。
菅澤 どちらの場合も、メリットとデメリットがありますね。スタメンを固定してしまうと、勝ちやすいかもしれないけれど、試合に出られない子たちの経験値が上がりません。もっと怖いのは、「どうせ試合に出られないんだから」と、モチベーションも下がり、サッカーが嫌いになってしまうかもしれないこと。それに、スタメン、とくに背番号10番を与えられているような中心選手は、チーム内の立場も強く、つい周りの子供たちも特別扱いしてしまう傾向がある。それを放っておくのは、育成年代において、とても危険だと思います。
かたや、出場時間を均等にすれば、どの子も試合に出られ、嬉しいだろうとは思います。でも、調子が悪い子や一生懸命やらない子も同じように出すのは、頑張っている子にしたら納得がいかないんじゃないでしょうか。そのあたりは、指導者が細やかに察知し、たとえば手を抜いたプレーをしたら、頭を冷やさせるために、予定の出場時間より早くベンチに下げるなどの対応をした方がいい。本人も周りも、「あのプレーしちゃったんだから、仕方がない」と、納得しますよ。
チーム事情にもよるので難しい問題ですし、誰もが100%納得するメンバー選びは、正直ほぼ不可能。ただ、「これは絶対に勝たなくてはいけない」という試合は、その時の実力重視でメンバーを選び、重要度が比較的低い試合は、それ以外の子を積極的に起用するなど、工夫の余地はあると思います。
――誰がどのポジションをやるかも、指導者として悩ましいところだと思います。とくにジュニア年代は、攻撃に関わるポジションが人気で、ディフェンスをやりたがる子供は稀有です。
菅澤 ポジションもいろいろな考え方がありますが、僕は、子供がイヤだというポジションを無理にやらせるのは極力避けた方がいいと考えています。なぜなら、イヤイヤやっても楽しくないから。
適正に関しても、ジュニアユース以上になれば、ある程度はっきりしてきますが、ジュニア年代は、身体がどの程度大きくなるかも含め、未知数の部分が大きいので、判断は難しいですね。ただ、“性格”はひとつの判断材料になると思います。
たとえば、まじめで緻密な子は、後ろ(ディフェンス)のポジションにいてくれると安心できる。どこが危ないかを察知して、いるべき場所にきちんといてくれますから。逆に、周りを気にせず、自分がやりたいことにまっしぐらなタイプは、攻撃的なポジションの方が向いている。失敗しても気にしないメンタルの強さがあり、ガンガン攻めてくれるので。今振り返ると、重要なゲームで配置したポジションを攻守で分けると、攻撃側の選手はB型が多く、守備側の選手はA型が多かった気がします。
FC町田ゼルビアのアカデミーは、子供たちをプロにするのが最終目的なので、その子の特性を考え、将来どのポジションが一番力を発揮できるかを想定しながら、複数のポジションを経験させています。3つ以上のポジションをこなせるよう時間を与えています。

1974年東京都生まれ。1996年、選手として所属した読売クラブ(現・東京V)育成部門コーチとなり、元日本代表の森本貴幸氏や小林祐希氏ら、数々の逸材を発掘。その後、名古屋グランパスや京都サンガF.C.へ。ジェフユナイテッド市原・千葉ではTOPチームとアカデミーを指導。ロアッソ熊本などで育成年代のコーチや監督を歴任し、2021年からFC町田ゼルビアのアカデミーダイレクターを務めている。
――ジュニア年代だと、キーパーをやりたがる子がいないため、子供たちが順番に担当するケースも少なくありません。キーパーとしての練習をしていないので、キャッチミスが多かったり、ゴールキックが遠くに飛ばなかったりで、すぐに失点してしまうという話も耳にします。
菅澤 確かに、うちのアカデミーも、数年前まではキーパー志望の子ってほとんどいませんでした。必然的に、全員が交代でキーパーをやっていたわけですが、その時、子供に伝えたのは、「キーパーだと思わないでくれ」という言葉。子供たちが抱いているキーパー像は、ゴールの近くにベタ付きで、フィールドプレーヤーから独立した存在でしょう。それでは、つまらないと思うのも当然です。
うちのジュニアユースやユースチームは、キーパーはビルドアップの要。なので、ジュニアチームでも、キーパーは高い位置をとってプレーします。だから、キーパーになった子たちは、フィールドプレーヤーの一員という感覚で、孤立せずプレーできていると思いますよ。
キャッチミスやゴールキックについても、子供を責めるより、指導者が考え方を変える方が合理的だと思います。子供たちは、ボールを蹴るのが好きでサッカーをやっているのだから、手でボールを扱うことに一生懸命になれなくても、しかたがない。足で止めて、足で蹴るというスタイルでやらせてあげればいいし、ゴールキックが遠くに飛ばないなら、ドリブルで持ち上がってもいい。
それでミスしたとしても、子供にとって、きっとプラスの経験になるはず。なかには、うまくこなす子もいるでしょうから、その子が絶対に負けられない試合でキーパーになるよう、交代の順番をうまく調整するのも手だと思います。
出場時間にしても、ポジションにしても、指導者は、「子供がサッカーを嫌いにならないように」ということを念頭に、対応してほしいですね。
※第4回に続く
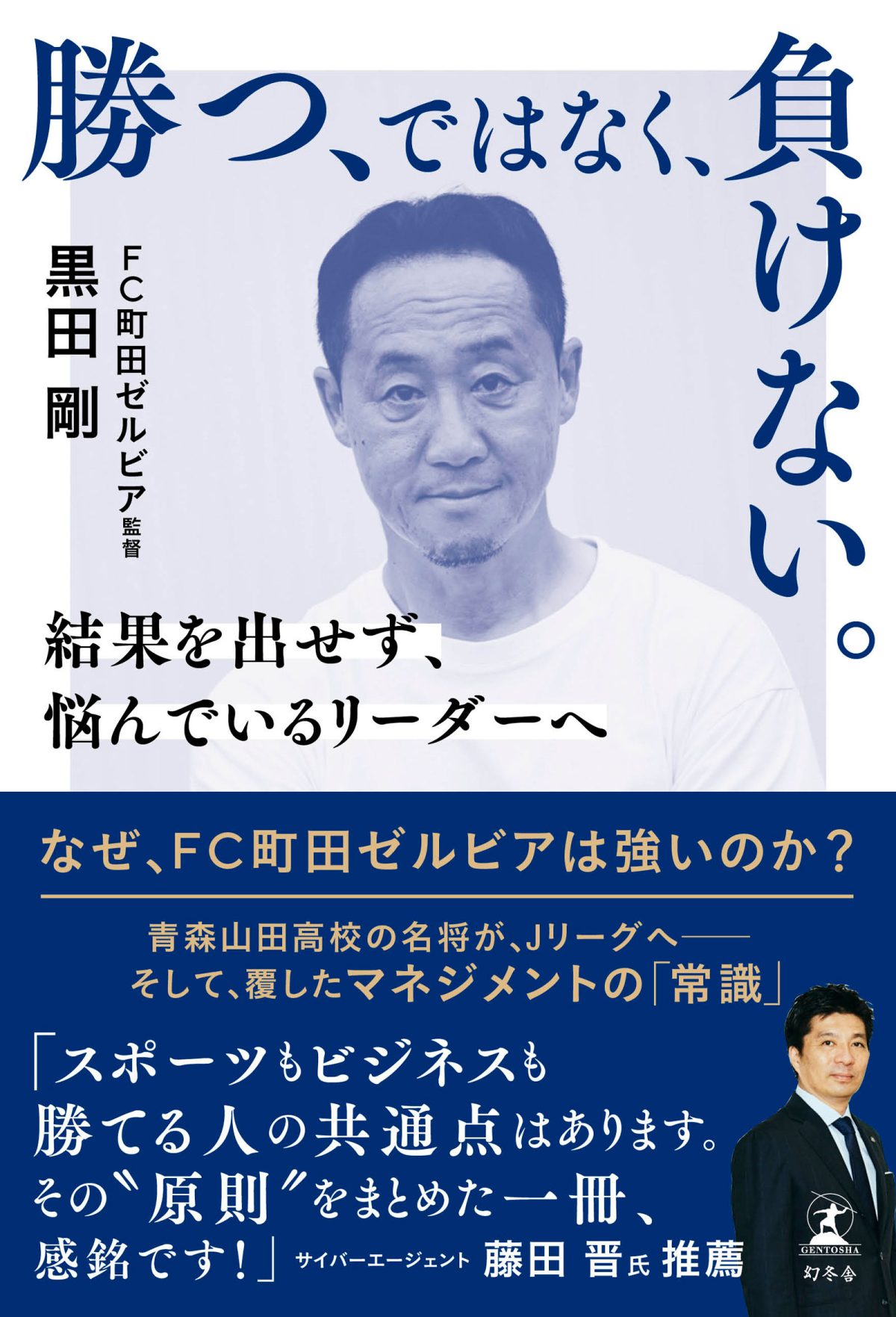
FC町田ゼルビア大躍進の裏には、アマでもプロでも通用する、黒田流マネジメントの原理原則があった。組織・リーダー・言語化など、4つの講義を収録。結果を出せず悩んでいるリーダー必読。黒田剛著 ¥1,540/幻冬舎
▶︎▶︎▶︎購入はこちら