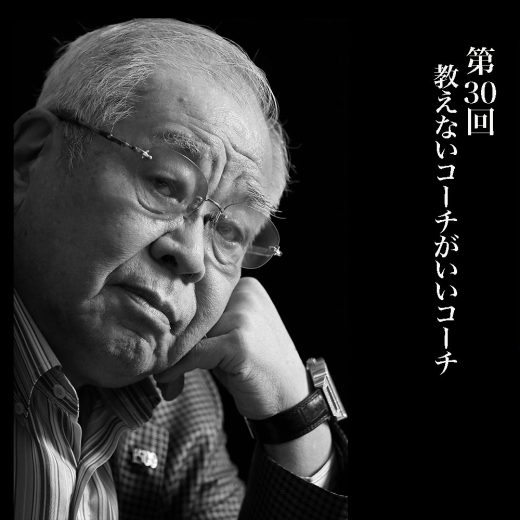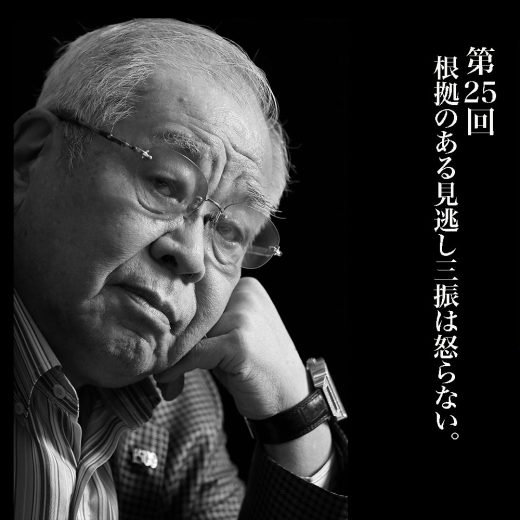39歳で東北楽天ゴールデンイーグルスの監督に就任。その後も、福岡ソフトバンクホークス、埼玉西武ライオンズのコーチとして請われてきた平石洋介の著書『人に学び、人に生かす。』より一部抜粋してお届けする。

1980年4月23日大分県出身。野球指導者・解説者。高校時代を名門PL学園で過ごし、3年時には主将として甲子園に出場。2004年ドラフト7位で楽天に入団。2019年に監督に就任。クライマックスシリーズ進出を果たすも退任。2020年から2年間はソフトバンクのコーチ、2022年は西武の打撃コーチとなり、2023年に西武のヘッドコーチに就任。2024年限りで退団した。
「指導者の言うことをやってたらあかん」
プロで結果を残すために求められる要素のひとつに「スルースキル」がある。
僕もそう思う。
スルースキルとは、その文字のとおり、「スルー」する技術のことだ。
わかりやすく言えば、指導者から「こうしろ」と指示されたとき、自分には合わないと思えば、その場では「わかりました」と言い、実際は他のやり方に取り組む。もし、それがばれてしまい怒られたとしても「すみません」とやり過ごす。図太く、“鈍感力”を意図的に振る舞えることも、プロとしては重要な技術だと思う。
もちろんいつも「そうしろ」という意味ではない。「時には必要になる」、ということである。
高校までの僕は、指導者から教えられたことはたいてい体現できた。大学では指導という指導をされることはほとんどなかったし、社会人では自分のやり方を尊重してくれた。
その矜持が、プロに入ってから崩れた。
当時のイーグルスは、ベテランが多く、必然的に指導者は若手にほぼつきっきりで教えてくれた。憧れの世界、最高峰のレベルで教えてもらったことは「やるべき」だと思っていた。
今、思えば、教えてもらったことを「自分なりに噛み砕いて」から実践できれば理想だったのだけど、7キロも痩せるくらいだから、そんなことを考える余裕もなかった。スルースキルなんて、持ち合わせてもいなかった。
プロ1年目の2005年5月、二軍に落ちてからのことだった。
それまでの僕は、監督の田尾安志さんからほぼマンツーマンでバッティングを教わっていたのだが、当時の自分には理解ができず悩みまくっていた。
「なんでもかんでも、指導者の言うことをやってたらあかんぞ」
僕にそう助言してくれたのは二軍コーチの駒田徳広さんだった。
完全にピンとは来ていなかったけど、そういうものなのか? と目からウロコが落ちる思いで聞いていた。その駒田さんが説いていたのが「スルースキル」だ。
一軍打撃コーチとしてイーグルスに入団したものの、シーズン途中に配置転換で二軍で指導をされていた駒田さんと僕は、話す機会が増えた。
巨人(現:読売ジャイアンツ)時代に「満塁男」と呼ばれるほどチャンスに強く、横浜 ベイスターズ(現:横浜DeNAベイスターズ)に移籍してからも、1998年の日本一に貢献。通算2000本安打も記録した一流バッターである。
プロで確固たる実績を築いた駒田さんは、とにかく喋りが上手だった。プロ野球の歴史などを交えながら技術論を展開してくれ、選手目線で指導してくれる方だった。
話があまりにも面白かったため、少しだけあの、背筋を伸ばしてバットを垂直に構える現役時代の駒田さんのバッティングフォームを真似したこともあったくらいだ。
駒田さんが伝えてくれていたスルースキル。
結果的に僕は実践できなかったが、一流の成績を残した選手は芯の強さがあるのだと教えられた。
「お前なんか二度と使わん」
プロ2年目の僕のバッティングフォームは、現在の選手で言うなら阪神の近本光司のようなバットのヘッドを極端に前に出した形だった。
それは、1年目から試行錯誤を続けた末にたどり着いた、僕にとってこのときのベストだった。
インターネットなどを通じてさまざまな情報が入手できるようになった今でこそ、多様なアプローチが肯定されるようになったが、当時の野球界では「バットを上から叩くように振る」という技術が半ば「絶対的」なものとしてまかり通っていた。実際、コーチからもよく言われた。
「映像で見たって、みんな上から叩いてないやろ」
そう疑問に思ってはいたが、指導される以上は従うほかない。
同じように「ヘッドは最短距離で出せ」もよく言われていた。
僕は調子が悪くなると、スイング時にバットが体から外れるクセがある。
そんな状態で当時、“バッティングの鉄則”とされるこのふたつを体現する方法を考えた。重要になるのが(左打ちの僕の場合)左手首で、ここさえ意識すればスイングをしてもバットが体から外れることなく、上からかつ最短距離で出せるだろう、そう考えたのである。
そうして、左手首の角度を意識しアップデートを重ねていると、ヘッドがどんどん前となり、この形となったわけである。
2年目の春季キャンプは二軍スタートだったが、新フォームには手応えがあった(今は「いい」とは思わないが)。実戦では納得のいくパフォーマンスが体現でき、シーズン開幕こそ一軍で迎えることができなかったが二軍では結果を残せていた。
忘れもしない。4月に一軍昇格を果たした初日の練習でのことだった。
「何や、お前の打ち方は。頭の前にヘッドがあったら、バットから体が離れるやろ」
ケージの後ろで僕のバッティングを見ていた、「監督」が言った。
球団創設1年目のイーグルスはダントツの最下位に終わった。田尾さんは一年で解任され、新監督となったのが名将・野村克也さんだった。
「そうなりたくないからこの打ち方にしてるんです」
名将の前でそうとは言えず、打ち続けた。すると、監督は呆れたようにこう言い放った。
「そんなんで打てるかい。お前なんか二度と使わん」
野村監督の僕に対する第一印象は、きっと最悪だった。だからといってそのまま二軍に落とされたわけではなく、4月28日のロッテ戦で僕は「8番・レフト」でスタメン起用され4打数1安打、「9番・レフト」で出場した翌日の試合では3打数ノーヒット、2三振と精彩を欠く。
僕はこの試合の直後に二軍行きを命じられた。
二軍では変わらず結果を出せている。しかし、一軍からお呼びがかかる気配はない。
「こんだけ打ってんのに、なんで上がれへんねん!」
もどかしさはあった。正直、腐りそうにもなった。だけど、二軍には僕のことを理解してくれる指導者がいた。松井(優典)二軍監督と二軍打撃コーチの廣橋(公寿)さんだ。
特に廣橋さんは、「平石、お前の気持ちはわかる。だから、結果で見返そうぜ。俺たちで一軍の首脳陣を黙らせようじゃないか」と励ましてくれ、僕が一軍に上がれずもやもやしていると感じると、「プロの世界はずっと同じ指導者が続くわけじゃないんだから、今は我慢だ」などと言っては、僕のモチベーションを繋ぎ留めてくれていた。
イースタン・リーグで打率2位の成績を残せたのは、ヘッドを極端に前に出すフォームを「そのままでいい」と認めてくれていた廣橋さんと、使い続けてくれた松井二軍監督のおかげでもあった。
2年目の秋季キャンプ。僕は一軍の打撃コーチから再三言われるようになる。
「今のままだとノムさんに使ってもらえないから、打ち方を変えろ」ーー。
僕自身、「変えないと使ってもらえない」という現実を受け入れていた。
一軍のコーチたちが言うのだ。変えるしかなかったのだ。
全てはチャンスをもらうため。一軍で結果を出すためーー。
結果的に僕は、迷走していくこととなる。
「自分を持たないとダメだからな」
「一軍ではチャンスがもらえてないけど、頑張ってるらしいな。色々と話は聞くぞ」
2年目のシーズンオフ。選手納会で武司さんが声を掛けてくれた。この年、僕は一軍こそ2試合しか出場できなかったが、二軍では 試合に出場してイースタン・リーグ2位の打率3割2分8厘、出塁率は1位の4割2分9厘を記録した。
武司さんは中日時代にホームラン王を獲得するなどチームの主砲だったが、2003年 にトレードでオリックスへと移籍。そこでも首脳陣とそりが合わずに2年で戦力外通告を受けている。その年に誕生したイーグルスが獲得したことで、移籍1年目の2005年に37歳ながら25本のホームランを打つなど見事な再起を印象付けていた。
実はこの1年前のシーズンオフ、選手納会で同じく武司さんから説教を受けていた。
「お前、気持ち入ってんのか? しっかり練習しねぇと後悔するぞ」
結果こそ出せていなかったが、練習に手を抜いているつもりはなかった。武司さんは豪快なイメージがあり、現にそういった一面もあるのだが、実はよく人を観察している。説教をされたときこそ気づけなかったが、1年目の僕は先輩選手に誘われ、食事に行く日が多かった。「自分によくしてくれる先輩だから」と、深く考えずに付き合ってしまっていた。
苦労人である武司さんは、それがプロとしてマイナスに働く可能性があることを知っていた。いくら先輩からの誘いとはいえ、断る勇気も必要だ。プロ野球の世界は甘くないんだから、自分を持て、と。
事実、僕は2年目に痛烈な厳しさに直面した。
書いたように、一軍の出場は2試合のみで、二軍に落ちてからは一軍に昇格する気配すらなかった。だからバットを振りまくった。
そうして2年目の選手納会には、褒めてもらった。
「お前、チャンスがもらえない中でも腐らずに、えらい変わったって話を聞くぞ。俺も経験したから言えることだけど、二軍で打てねぇやつは一軍でも打てねぇから。でも、二軍で打てるやつはチャンスさえ掴めれば一軍で打てる可能性は十分にあるからよ。だから、腐らずにこれからも頑張れ」
そして武司さんは、1年前の想いを口にして僕を激励してくれた。
「自分を持たないとダメだからな」
腐らずに、自分を持つ。こういう出会いがあったから、僕はやってこれた。