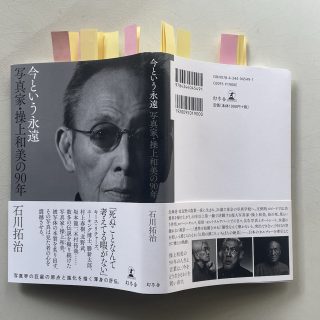いよいよプロ野球2025年シーズンが開幕した。昨季、4年ぶりにパ・リーグ優勝を果たした福岡ソフトバンクホークスを支える三笠杉彦GMに独占インタビューを敢行。第1回。

1974年岩手県釜石市生まれ。釜石南高でラグビーを始め東京大学でもプレー。卒業後、日本テレコム(現ソフトバンク)入社。東大ラグビー部のコーチ・監督も務める。2008年から球団事業に携わり、2019年より現職。
「世界一の球団」を目指すために
「能ある鷹は爪を隠す」
という諺がある。だが、この球団の場合は「能ある鷹は爪を磨く」がふさわしいのかもしれない。日本の球団初の4軍創設、コーディネーター制の導入、データサイエンスの徹底…リーグ優勝チームにも関わらず、布石を次々と打っているからだ。球団の名は、福岡ソフトバンクホークス。
その舞台裏を最も知る男が三笠杉彦取締役GM兼球団統括本部長(50)だ。東京大学ラグビー部で選手や指導者の経験を持つという異色のキャリアの持ち主。卒業後に日本テレコム(現ソフトバンク)に就職、2008年からソフトバンクホークスで様々な役職を経て、2019年にGM就任。オーナーである孫正義氏、球団の王貞治会長、後藤芳光社長からも信頼が厚い。
2025年はソフトバンクがオーナーとなって20周年となる記念の年。三笠GMの目標は「世界一のチーム」にすることだが、これは孫オーナーが掲げる理想でもある。壮大な理想実現のため、三笠GMは鷹の爪を磨き続ける。
GMの仕事は、開幕前に終わる
――あらためて昨シーズンのリーグ優勝おめでとうございます。また、映画「FUKUOKA SoftBank HAWKS REVIVAL ―2024優勝の軌跡―」を鑑賞しました。数年ぶりの優勝、強さの理由はなんでしょうか。
三笠 端的に言うと、監督コーチ陣のマネジメントの勝利です。2023年に比べて戦力の上積みはありましたが、小久保裕紀監督が就任した時に、改めて「1軍で勝つために、どうマネジメントしなければいけないか」を4軍まで含めて突き詰めて話し合いました。シーズンを通して監督がしっかりとマネジメントして下さったことが優勝の要因です。
――具体的に教えていただけますか。
三笠 まずは投手陣の整備です。もとから打線はリーグトップでしたが、ピッチャーのパフォーマンスはうまく機能していなかった。そこで、倉野信次さんに戻ってきてもらい、1軍投手コーチと1〜4軍を見る「ヘッドコーディネーター」を兼務してもらいました。モイネロ選手と大津(亮介)選手の先発へのスイッチも、うまくハマりましたね。小久保監督は多くを語らず、コーチやスタッフに役割を与えて人に任せる。その人たちをマネジメントしていく能力に長けた方だと思います。
チームは生き物、昨年と今年では全く違うチーム
――2024年、小久保監督の言葉に組織マネジメントとして「部分最適ではなく、全体最適を考えなければならない」という発言がありました。
三笠 組織がどんどん大きくなっているなか、球団の一体感というよりは1軍は1軍、2軍は2軍など部分的になっている。コーチはコーチ、データサイエンスのスタッフはデータサイエンス、トレーナーはトレーナーのスタッフで、各々が役割を最適化するのに一生懸命です。
1軍は勝つために、2軍以下は選手が成長するためにと、目標を統一してやるのがかつての球団の「常識」でした。ところが本来の目的を失って、自分のところでやるのが精一杯で、あとは知りませんとなってしまっている部分を、小久保監督は課題として捉えたのでしょう。
――多くの球団やスポーツチームにも同じことが起きていると思います。
三笠 コロナの影響でリモート会議が多くなり、コミュニケーション不足が起きていたのも要因のひとつだと思います。部分最適より全体最適を考えるというのは誰もが賛同しますが、なかなか実現出来ないという現状が2023年シーズンまではあったと、僕も認識していました。ところが2024年シーズンはそういった課題を克服し、リーグ優勝を果たしました。
ただ、工藤公康元監督や秋山幸二元監督もですが、1年目と2年目は全然違う。チームは生き物。優勝はもちろん、連覇はより難しい。理由は他球団が、王者に照準を合わして、先発ローテーションを組み、戦術もより意識してくるからです。優勝チームはそれに打ち勝たないといけない。ここに連覇の難しさがあります。
――2024年シーズンの開幕前、優勝への手応えのようなものはあったのでしょうか。
三笠 まったくないですね(笑)。シーズン前は選手のFAや移籍の業務で大変でした。チーム編成などのGMの仕事は、開幕前までに終わります。シーズン後、結果を踏まえてその答え合わせが始まります。
2025年も開幕を迎える頃までに仕事は終わり、開幕後は来年2026年のドラフトなどに向けた準備をしています。シーズン中は監督やコーチ陣の分野。だから、日々の勝ち負けに一喜一憂しないというのが、フロント・オフィスの人間としての意識です。

1週間で1つ勝ち越せば優勝する!?
――三笠さんは、東京大学ラグビー部で選手と指導者を経験された異色のGMです。一方で現在のプロ球団の仕事に就いてから十数年が経っています。日本のプロ野球をどう見ていますか。
三笠 日本のプロ野球は凄いコンペティティブですが、1週間で平均してひとつでも勝ち越せば、ほぼ優勝できると考えています。
週で5試合あれば、3勝2敗という結果を出し続ければ優勝できる。ラグビーやサッカーのように1週間に1試合しかないプロスポーツと根本的に違うのは、ほぼ毎日試合があり、毎試合の勝ち負けというより、1週間などのタームでの結果を意識することが重要になってくることです。
「今日勝った、明日負けた」ではなく、火水木、金土日の試合のなかで1つずつ貯金を積んでいく。すると勝率はほぼ6割。1つ勝利して手応えのあるなしは選手にはあるかもしれません。でも、マネジメントサイドは、ターム単位で考える。そしてシーズン後、僕らフロント側の結果が出る。選手の評価も同時に行い、思った通りに活躍してくれた選手もいれば、残念ですが、放出を考える選手も出てきます。
――「週単位で考えること」は、大変興味深いです。サッカー・FC町田ゼルビアの黒田剛監督も同じ、ターム単位で勝ち点を考えていると発言されていました。GMとして他にどのような動きをしていますか。
三笠 そうですね。2025年は2月1日からキャンプが始まりました。ホークスは選手が約120人在籍、一方でスカウトやフロントスタッフは約50人と、球団としては大きな組織です。
キャンプ中には来季のドラフト候補についての打ち合わせをします。小久保監督たちは今季どういったチーム作りをしていくかを話し合っていますが、フロント側は来季のチーム作りを話し合っていて、選手の契約年数などを頭に入れながら試合を見る。誰がどのポジションに何歳でいるか、またアマチュアのマーケットを見て「3年後のホークス」のデプスチャート(*注)を作成。そして、ドラフトの有望株やFAの選手を徹底的に分析し、スカウティング計画を立てています。
また、ホークスで特徴的なのは、4軍まであり、育成選手が現在50人以上在籍していること。2〜4軍に在籍している若手選手の育成計画をどうするかも議論しています。例えば、劇団だと1軍はトップスターが演じる檜舞台、ここは小久保監督たちに任せて、コーディネーターを中心にした2〜4軍の育成計画を立て、どの選手をどう配置していくかの基本方針を決めていく。このような仕事がGMとしての主です。
*デプスチャート:取引市場における買い注文と売り注文の量を視覚化したグラフ。市場の流動性や深さを把握するために使われる。
※2回目に続く