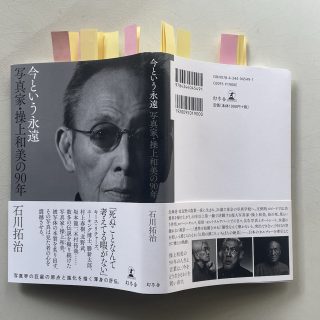2024年リーグ優勝を果たした福岡ソフトバンクホークス。「育成のホークス」といわれて久しく、昨シーズンは育成から支配下登録が8人実現したが、これは他の球団を抜きん出ている。現在1軍から4軍まで存在するのは12球団ではホークスのみ。その4軍創設に尽力したのが三笠GMである。選手獲得も重要だが、現代のプロ野球では、いや、現代のプロスポーツチームではそれ以上に育成が勝利の要因となっている。いち早くその点に気付きチーム改革を進めてきたGMから見た「育成のホークス」の未来はどのようなものだろうか。GM三笠杉彦GM独占インタビュー、第2回。

1974年岩手県釜石市出身。釜石南でラグビーを始め東京大学でもプレー。卒業後、日本テレコム(現ソフトバンク)入社。東大ラグビー部のコーチ・監督も務める。2008年から球団事業に携わり、2019年より現職。
ラグビーの指導者とプロ野球のGMの意外な親和性
――前回、GMの仕事は想像以上に幅が広いのと複眼的な視点が必要なのがよく分かりました。ちなみに三笠GMは東京大学ラグビー部出身で指導者の経験がありますが、現職にどのように活きていますか。
三笠 実はラグビーの指導者は試合中に目の前の試合のことばかり考えているわけではないのです。現在とは違い、昔は怪我ではないと選手交代はできませんでした。そのため、ラグビーの試合中は「ハーフタイムに何を言おう」「試合後はどう行動しよう」「来週はどういう練習をしようか」などを考えていました。その頃の経験によって、常に客観的に試合やチームを見る眼が自然と養われてきたのかもしれません。
最も注意しているのは、人と人との「距離感」
――ホークスは日本でトップクラスの予算を持つ球団。関わっている人もステークホルダーも多いですが、それらの調整事をまとめる秘訣はありますか。
三笠 まず、私の仕事は目の前の試合にどう勝つかではなく、良い環境をつくり、優秀な選手を連れてきて、優れた指導体制をつくる。この3つなのです。それ以外は組織の中の人に任せないといけません。選手やスタッフ、監督コーチの全ての契約を結ぶのが私の仕事です。ホークスに関わる全ての契約に携わっている、契約のおじさんなんです(笑)。契約することとはお願いをする業務、それをお金に変換して委託するということ。どの案件にどのくらいお金がかかるかを把握しておくのを常に注意しています。
そのためにも大事にしていることは、距離感です。特定の選手やスタッフと距離が近いことがないように気をつけています。小久保監督に対しても同じで食事などには行きますが、コーチのマネジメントは監督やコーディネーターにお任せしているので、特定のコーチや選手と個別に仲良くすることはありません。
何故かといえば、先ほども言いましたが僕は契約のおじさんなのでチームのパフォーマンスを出すのにもっと他に良い人材がいれば、その人との契約を切らなければいけない場合があります。私の仕事のミッションなので感情的に特定の人と長く付き合っていたら、「あなたはクビです」とは言いづらくなります。
ホークスというチームが短期的にも中長期的にも強くなるためにどうるすかを考えるのがGMの仕事です。なかでも一番嫌なのが、「戦力外通告」です。仕事ですから、やらなければいけない。悲しいですが新しい選手を入れるためには必要なことです。
――「戦力外」を含め、全体を見て、進めていかなければいけないんですね。
三笠 昔、ホークスの礎をつくった根本陸夫さんが、ある書籍でおっしゃっていた言葉が忘れられません。すごく厳しい見方なのですが端的にいうと、
「やっぱり駄目な人は早く辞めてもらった方がいい」
それもフロントの仕事だと。フロントは獲得した人が相応しくないと分かったら出来るだけ早く出すことを求められる。そのためにも距離感が必要です。プロスポーツの組織運営はそういうものだと思っています。
ちなみに、私がラグビー出身者で野球をやっていなかったから距離がとれるのではと考えています。逆にラグビーチームでは、どうしても自分の感情が出てしまう。自分の好みが出すぎてしまってチームを管理できないんじゃないかと思います。でも、野球は客観的に見られます。距離も保ち、自分の感覚だけで「この選手は良い選手だ」などと思わないようにしています。データを重視し、複数のスカウトからも情報を得て、選手を評価するようにしています。

スポーツビジネス関係者に見られる「甘え」
――徹底的に合理的ということでしょうか
三笠 はい。逆に合理的にやり切れないで苦労している人をスポーツビジネスの世界では多く見受けます。ただそれは、一種の「甘え」ではないでしょうか。
これは仕事なのです。仕事ですが、スポーツが好きで始めてスポーツチームに入ってきて、好きだという気持ちを差し置いて合理的になるみたいなことに本能的に抵抗がある人が多いように感じます。
再度言いますが、仕事でありビジネスであることを忘れてはいけません。組織的にやることは“熱い”ことが必要条件ではなく、合理的であることが必要条件です。多くの人を巻き込んでお金を払っていただき、チームが結果を出して、たくさんのお客様に入場していただいてやっと利益が出ます。この構図ができないと経営が成り立ちません。
育成のホークスといわれて久しいが…
――「育成のホークス」と言われて久しいです。個人的に筑後が好きで通っていますが、8人の育成選手の支配下登録がありました。改めてお聞きしますが、4軍創設の理由を教えて下さい。
三笠 2011年から始めた3軍制というのがとても成功をして拡大をするべきだ、と孫オーナーと話し合い、新しく4軍をつくることになったのが一つです。2010年代にホークスの育成が成功し、1軍が結果を出したことが大きいです。
現在ほとんどの球団が育成を進めていますが、以前は全く育成の選手を取っていなかったチームもありました。10月にドラフト会議を行いますが支配下選手のドラフトが終わったら育成選手のドラフトが開催されます。以前はジャイアンツとホークスがメインで、他の球団は育成に1名か2名くらいを指名して終わりでした。数年前からは12球団全てが育成指名をするようになりました。そのため、競争優位が少なくなり、我々に何ができるかと考えて「4軍制」というものが生まれました。
――育成で最も大事な部分は何だとお考えですか。
三笠 一般論として選手を育成するのは仕組みも大事ですが、より重要なのは「指導者育成」です。
サッカーとの対比で考えると、良くも悪くも指導者育成制度の点で野球はまだまだ確立できていません。プロアマの壁もありますが競技団体として指導者育成が系統立てて出来ていない現状があり、プロ野球全体としても取り組んでいかなければいけない課題です。ホークスではジュニアアカデミーから4軍へ釜元豪コーチを登用しています。アカデミーとファームのコーチが行き来する仕組みは指導者養成を発展させるという観点で大事です。
※3回目に続く