歌手・五木ひろしが通算175枚目のシングル「時は流れて…」を2023年9月にリリース。2024年で歌手生活60周年を迎えるレジェンド五木ひろしの半生に迫る。連載7回目。過去記事はコチラ。
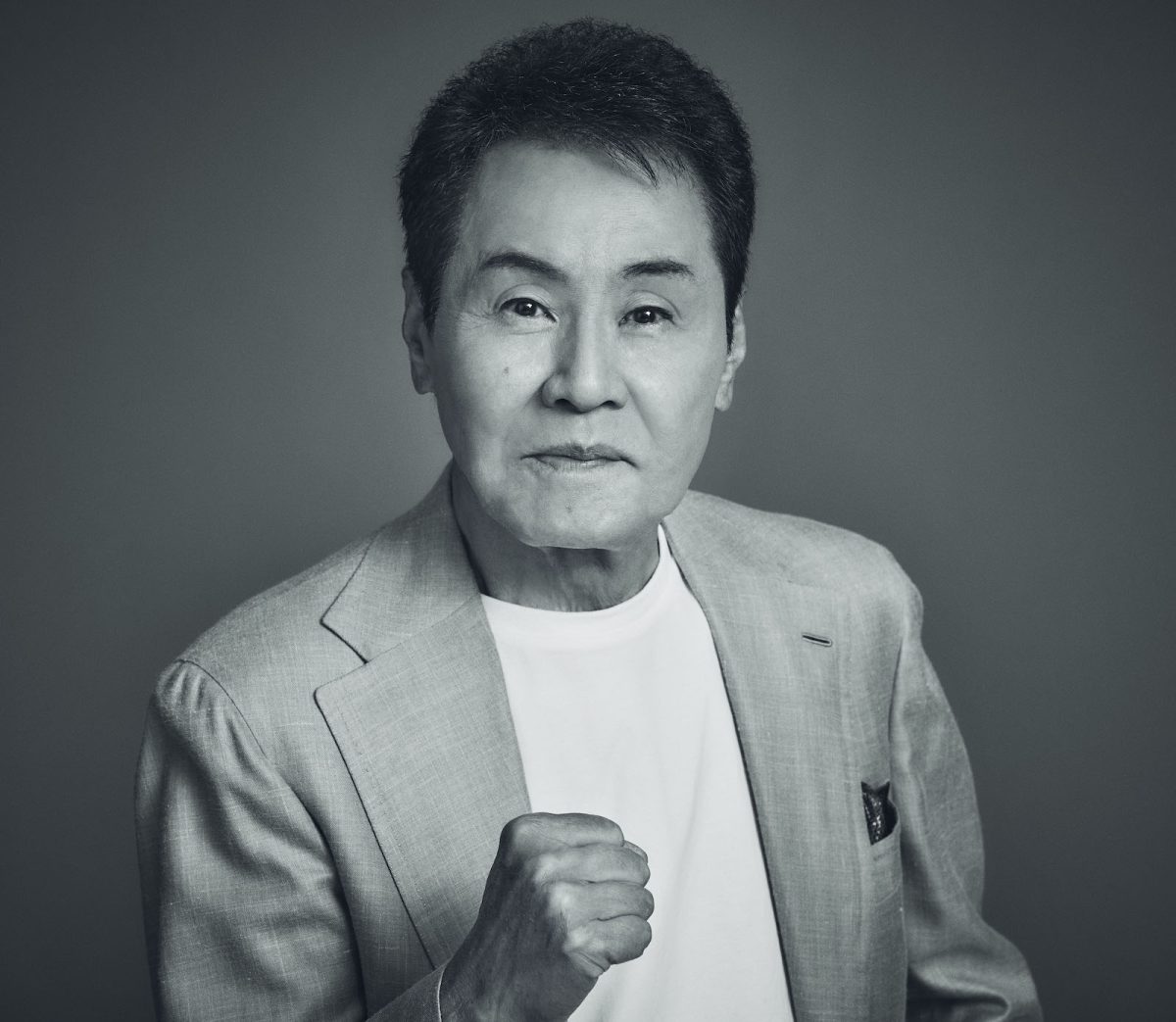
自分のライバル=全盛期の自分
「僕のライバルは、僕」
五木ひろしはきっぱりと言う。
「僕は1948年生まれ。団塊の世代です。人口が多いので、同世代でいつも競争してきました。歌手になりヒットが出るようになっても、同世代の歌手たちと比較されてきました。でも、特定の誰かをライバル視したことはありません。僕のライバルは、いつも僕でした。5年前の自分と比べて、今のほうがいい歌手になっているのか? 昨年の同じ時期よりもレベルアップしているか? 常に意識してきました」
今もコンサートやテレビ収録のときの歌を録音。自分の声のチェックを怠らない。五木のiPodには延べ8000曲分以上の自分の歌が収められている。
「正直なところを打ち明けると、歌手としての僕のピークは30~40代です。あのころ、一番声が出ていました。『おまえとふたり』をはじめ、作曲家でもあるギタリスト木村好夫さんと、どこまで音が出るか音域を競ったことがあります。僕の音域は3オクターブ半で、木村さんのギターに勝ってしまったくらいでした」
30~40代の自分にどれだけ近づけるか――。それを自分のテーマのひとつにして、今も五木は歌い続ける。
「限りなく近づける日もあれば、なかなか思うようにいかない日もあります。それでも、常に最大限の努力を自分に課しています」
自分の歌唱に満足できなかった「よこはま・たそがれ」
五木には1971年に「よこはま・たそがれ」のヒットまで約6年、ヒットが出ない厳しい時期があったことが知られている。
「松山まさるとしてデビューしてから売れない時期はありましたけれど、自分の歌唱力に疑問を持ったことは一度もありませんでした」
ほかの歌手たちもそれを認めていた。
「なんで、五木さんのほうが上手いのに、なかなか売れないんだろう?」
そんなことをよく言われた。
「売れるには、歌唱力のほかにさまざまな理由があります。タイミング、楽曲の出来、楽曲との相性……。必ずしも歌が上手い人が売れるわけではありません。わかってはいました。わかってはいたけれど、苦しかったですね」
だから「よこはま・たそがれ」が大ヒットしたときも、歌が上手いからヒットしたとは思わなかった。
「そもそも『よこはま・たそがれ』も満足できるレコーディングではありませんでしたから」
録音したスタジオでのことを五木は今もはっきりと憶えている。
「3テイク録ったら、OKと言われてしまいました。リハーサルの気分で歌って、さあ、これから本気で自分の味をだそう、と気持ちを入れた途端に……。えっ、これでいいの? 拍子抜けしたことを覚えています。あの頃の歌謡曲のスタジオでは、作曲家、作詞家、編曲家をはじめ、そこにいるスタッフがOKを出したら終了でした。だから、レコード化されている『よこはま・たそがれ』には今も満足していません。歌手として未熟に感じるからです」
通り過ぎてきた2つの声
五木ひろしは、約60年のキャリアで、3つの声で歌ってきた。
「最初は、1965年に松山まさるとしてデビューしたときの声です。ありのままきれいな発声で歌っていました。次はなかなか売れずにレコード会社を移籍して2つ目の歌手名、一条英一になったとき。声をつぶせ、と指示されました。言われるまま声を変えて歌いましたが、まったく納得できませんでした。自分本来の声とは思えなかったからです。まるで誰かを真似しているみたいな感覚でした。そのままヒットにも恵まれずにレコード会社をまた移籍して、今度は三谷謙になりました」
歌手名・三谷謙になったころにようやく自分らしい声になってきたと感じた。
「当時食べるために僕は銀座と新宿でクラブ歌手の仕事をやっていました。お店ではありとあらゆる楽曲をギターの弾き語りで歌います。クラブ歌手の歌はBGMです。お客さんたちの会話をじゃましてはいけません。有線放送のように薄く流れるようでなくてはいけません。声を張らずに、ささやくように、でも言葉は明瞭でなくてはならない。それを工夫しているうちに、僕だからこその歌唱が育まれていきました」
自分らしい声になってきた1970年、五木は讀賣テレビ系列の『全日本歌謡選手権』出場にチャレンジする。プロとアマチュアの垣根を取り払い、純粋に歌で対決する音楽番組。10週間勝ち抜くとグランドチャンピオンとなり、レコーディングのチャンスをつかめる。審査員は、淡谷のり子、船村徹、竹中労、平尾昌晃、山口洋子など。
そこで10週間勝ち続け、グランドチャンピオンの栄冠に輝き、歌手名・五木ひろしとして「よこはま・たそがれ」をレコーディング、大ヒットした。そこからは破竹の勢い。「長崎から船に乗って」「かもめ町みなと町」「待っている女」「夜汽車の女」……。リリースする曲が次々と大ヒットする。その過程で、さらに自分の声を探していった。
都はるみのひと言で自分のファルセットの魅力を知る
「1975年の『千曲川』のときに、今度は自分の明確な意思で声を変えました。まず、地声を生かしリズムを強く意識する歌唱に切り替えています」
毎年ラスベガスで公演を行った体験がそうさせた。
「演歌をはじめ日本の歌は抑揚が大切です。一方、アメリカではリズムの明確な楽曲をたくさん歌いました。その流れで、日本でもリズムがはっきりした曲を歌う機会が増えていった。それが、自分の声を見つけるきっかけの1つになりました」
日本の歌謡界の環境がセンターマイクからハンドマイク主流になっていったことも五木の意識を変えた。
「マイクを多様にコントロールして、発声を明瞭にしつつもビブラートのあんばいに工夫を重ねていきました。そして、自分流のファルセット(裏声)を手に入れたのです」
都はるみのひと言もきっかけになった。
「あなたほどのファルセットで歌える男性歌手はほかにはいないわよ」
ある番組で彼女に賞賛されたのだ。
「はるみちゃんは芸能界で1つ先輩。彼女とはとても仲よくしていて。言われてみると、確かに僕はファルセットで歌っていました。実は、歌っている自覚はなかったんです。自然のまま歌っていたらファルセットになっていました」
自分の持ち味であると知ったファルセットをコントロールして個性の1つになるようにと心がけた。
「地声でいけるところまでいって、最後にファルセットで抜いていく歌唱を身につけたのです」
地声を磨き、ファルセットを意識的にコントロールし、五木ならではの歌い方を手に入れた。
「開眼した」
自分で思えた。この3つ目の声をさらに磨き、今の五木ひろしの歌唱法になっている。「自分は誰よりも歌がうまい」と、胸の内で自分に言い聞かせ、さらに自信を持つようになった。このように人並み外れた努力、試行錯誤、創意工夫があった。
(※第8回に続く)












































