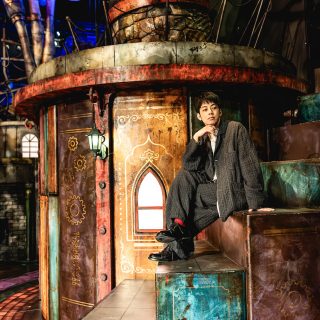他者のメッセージが持つ強い影響力は“呪い”だ。私たちはみな、無意識のうちに他者の意見や価値観を取り込み、それによって人生に絶望を覚えたり、言葉にできない生きづらさを感じてしまうことがある。サイエンスジャーナリスト・鈴木祐の新著『社会は、静かにあなたを「呪う」』を一部抜粋。4回目。【その他の記事はこちら】

快楽と充実
前半はコチラ。
が、いかに苦痛が重要だとは言っても、ただたんに“苦しみ”さえあれば人生が充実するわけではない。意味のない努力や報われない我慢をいくら積み重ねても、ただ心をすり減らすだけに終わってしまう。そこに「なんのために苦しむのか」という視点がなければ、それはただの痛み"でしかないだろう。「苦痛のパラドックス」を成立させるには、もうひとつ大事な要素を加えねばならない。
この点を考えるうえで参考になるのが、19世紀の哲学者ニーチェが残した「生きる意味を持つ者は、ほとんどどんなことにも耐えられる」という言葉だ。生涯にわたり人生の孤独に悩んだニーチェは、人間の喜びを“意味”に求めた。
この指摘の正しさは、近年いくつもの研究により裏づけられつつある。その代表例はオタワ大学などが行った調査で、研究チームは、人間が感じる喜びを「快楽」と「充実」の二つに分類した。
• 快楽:「楽しさ」や「心地よさ」を求める欲求が満たされた状態。
• 充実:「意味」や「成長」を追い求める活動を行い、他者貢献や自己表現などの欲求が満たされた状態。
日常の例を挙げるなら、「おいしい食事を楽しむ」や「リラックスして温泉につかる」などの活動は“快楽”が満たされた状態、「困難なプロジェクトに取り組む」や「ボランティア活動をする」は “充実”が満たされた状態だ。両者とも私たちにポジティブな影響を与えてくれるが、どちらのほうが人生の満足感への影響は大きいのだろう。答えを探るべく、研究チームは、約340人の参加者に、普段の生活のなかで「快楽」と「充実」を感じた瞬間を数週間ほど記録するように指示し、二つのデータをもとに回帰分析を行った。その要点はこうだ。
• “快楽”は一時的にストレスを減らしたが、その効果は数日で消える。
• “充実”は一時的にストレスを増やしたが、その後の3カ月間にわたって、人生の満足度が高くなった。
この結論は、納得しやすいだろう。趣味の時間、ショッピング、友人との交流などが楽しいのは間違いないものの、そればかりで深い満足感を得られないだろうことは、容易に想像がつく。楽しさを追うだけでは長い充実感を得られず、本当に満足した人生にはつながりにくい。
また、この研究では、「充実しているが快楽のない人生」のほうが、「快楽がある充実しない人生」より高く評価される傾向も見られた。たしかに、いくら楽しいイベントや贅沢な時間を積み重ねたとしても、後から振り返って「本当に価値ある人生を送れた」とは思いにくいだろう。私たちが人生から深い満足感を得るには、「苦痛」と「意味」をセットで考えねばならない。
それでは、人生に「苦痛」と「意味」を与えてくれる活動とは、どのようなものなのだろう。データによれば、“本当に充実した”と感じられる体験には、三つの特徴がある。
1 達成するまでに長い時間と努力を要する
2 他人に影響を与えることができる
3 物語として語ることができる
要するに、社会の役に立ち、時間をかけて努力し、それを人生のストーリーの一部として語れるような経験こそが、私たちに深い満足感をもたらす触媒になる。
最もよい例は「子育て」だろう。育児の大変さは言うまでもなく、睡眠や自由時間が奪われるのは当たり前だし、習い事や進学にかかる費用もばかにならず、仕事に支障が出ることも珍しくないだろう。それでも子供を作ったことを後悔する人が少ないのは、「子育て」が人生の充実に必要な三つの特徴を備えているからだ。事実、育児を終えたばかりの夫婦を調べた研究によると、子育ては短期的には幸福度を下げる傾向があるものの、長期的には「人生の意味」や「満足感」を大きく高めることが示されている。
育児は思いどおりにいかないことだらけだし、努力がすぐに報われるわけでもない。しかし、それと同時に、これほどひとりの人生に影響を与えられる活動はないし、子供が一人前に育った後は、そこまでのプロセスが独自の物語に変わる。自分の払った犠牲や苦しみが、自身が存在する根拠として意味づけられるのだ。
もっとも、この心理を活かすために、必ずしも大きな奉仕をする必要はない。「他人の役に立つ」ことを心がけるだけでも、私たちは十分に深い満足を得ることができる。
他者貢献の重要性を示した調査は多く、たとえばエクセター大学によるメタ分析では、40の先行研究を精査したうえで、「ボランティア活動を定期的に行う人は、そうでない人よりも人生の満足度が有意に高い」と結論づけている。その傾向は文化の違いを問わず、世界32ヵ国から約5万人のデータを集めたマルチレベル解析でも、あらゆる国で「他者に尽くす人ほど人生満足度も高い」という一貫したパターンが見られたという。他者への貢献によって深い満足を得られるのは、人類に普遍の心理なのだろう。
その具体的な方法は無数に存在するが、特に取り組みやすいのは以下の三つだ。
1 他人の幸福に焦点を当てる:
バーリ大学の研究チームが、参加者に「他人の幸福を意識的に考えてください」と指示したところ、「人間としての充実感」や「人生の満足感」といった指標が有意に向上する現象が見られた。つまり、「同僚の成功を心から喜ぶ」や「家族の健康を願ってみる」といったように、日常のなかで他人の幸せを思うだけでも、“人生の意味”にはよい影響が出るのだと考えられる。
2 小さな親切を繰り返す:
オックスフォード大学が4045名のデータを精査したメタ分析によれば、誰かに「小さな親切」を行った被験者は、年齢や文化の違いを問わず有意に人生の満足度が向上した。実験で使われた「小さな親切」は、「見知らぬ人に道を教える」「職場の同僚を励ます」「友人にコーヒーをおごる」などで、いずれも数分でできる簡単な行動ばかりだった。その効果量は「5(★★★記号変換必要★★★)=0.28」であり、これは実生活で変化を体感できるレベルの大きな数値だ。
3 他人のためにお金を遣う:
世界の120ヵ国で約23万人に行った調査では、「人にお金を遣うこと」と「主観的な人生の満足度」のあいだに有意な正の関連があることが確認されている 。誰かに少額の寄付や贈り物をするだけでも、私たちは「私は他者に影響を与えた」という感覚を得られ、人生への満足度が高まるようだ。「自分の満足のために行う寄付」という考え方に疑問を抱くかもしれないが、やらない善よりもやる偽善だ。
これらの例からわかるように、人生の満足感を得るのは意外とたやすい。まずは小さな親切からはじめ、徐々により大きなプロジェクトへ広げていくとよいだろう。もちろん、目の前の快楽を追うのは悪いことではないし、時には気晴らしや娯楽に没頭する時間も必要だ。しかし、そればかりでは快楽と充実のバランスが崩れ、やがては生きている実感まで失われかねないだろう。
この問題を避けるためには、日々の暮らしへ定期的に"苦痛"を取り入れるしかない。言い換えれば、私たちがバランスの取れた幸福感を得られるかどうかは、快楽と苦痛の“スイートスポット”を、いかに探すかにかかっているわけだ。
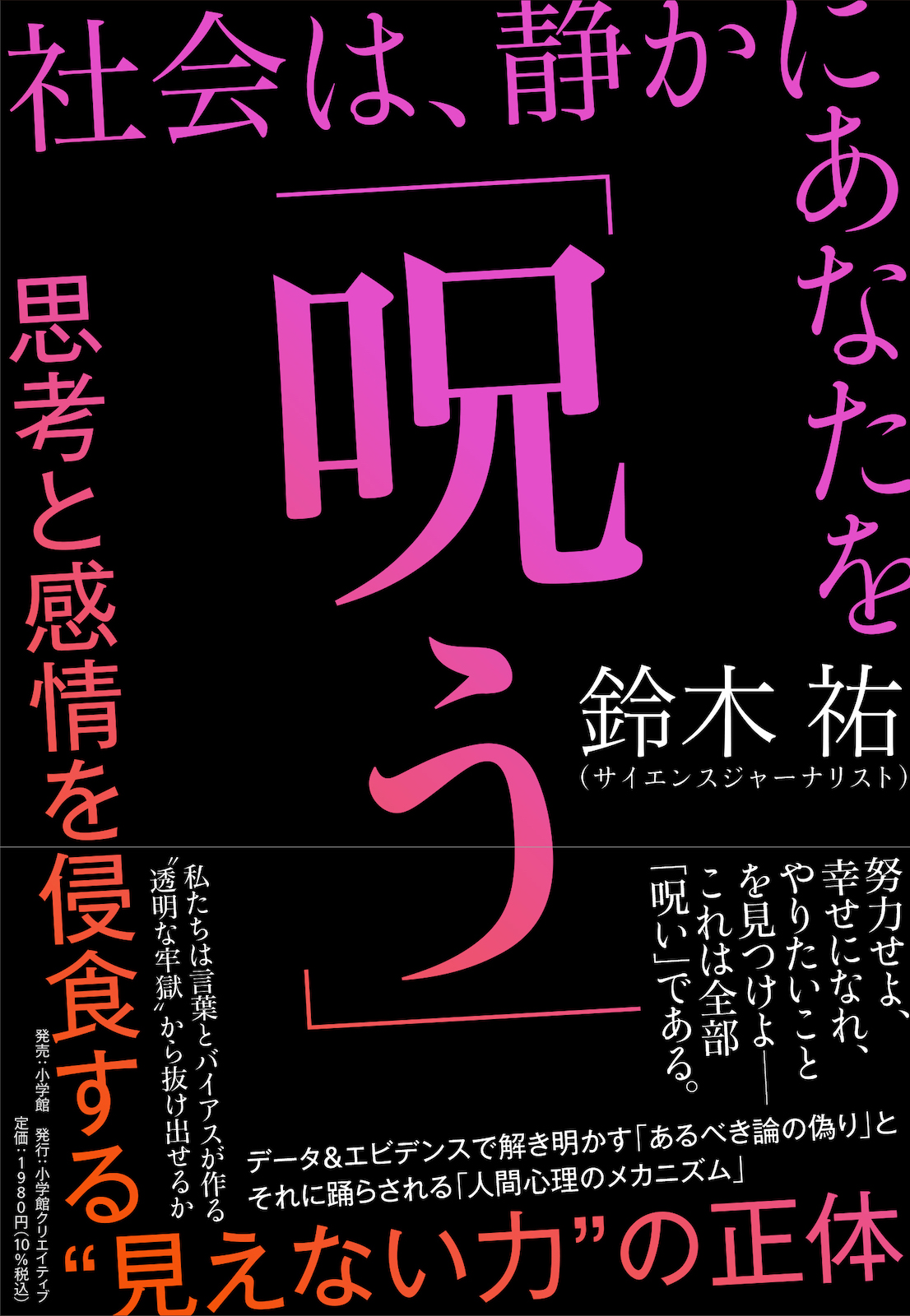
経済や幸福、働き方、遺伝や才能――私たちが「正しい」と信じてきた常識は、果たして真実なのか。人気サイエンスジャーナリスト・鈴木祐氏が、膨大な科学的エビデンスをもとに現代社会の“呪い”を解き明かす。思考と行動を縛る思い込みから抜け出し、真に自由になるための一冊。¥1,980/鈴木祐著/小学館クリエイティブ