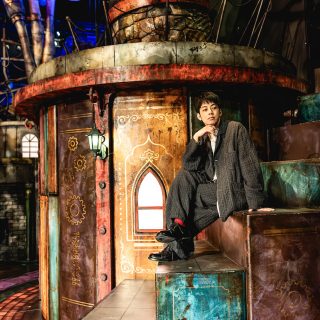他者のメッセージが持つ強い影響力は"呪い"だ。私たちはみな、無意識のうちに他者の意見や価値観を取り込み、それによって人生に絶望を覚えたり、言葉にできない生きづらさを感じてしまうことがある。サイエンスジャーナリスト・鈴木祐の新著『社会は、静かにあなたを「呪う」』を一部抜粋。3回目。【その他の記事はこちら】

「楽しいことだけをやれ」
「人生楽しんだ者勝ち」
「遊び尽くして生きろ」
「楽しめることだけをやれ」
このような言い回しもまた、幸福系の"呪い"の定番だ。たとえば、ある自己啓発本にはこんなフレーズが登場する。
「楽しいことは長続きする。そうでないことは、どんなに強制されても結局は続かない」
「人生を楽しんで生きるには、そして『やりたいこと』を仕事につなげるには、とにかく遊び尽くすことだ」
どちらの言葉も、「楽しさ」こそが人生の指標だと私たちに訴えかけ、苦しさや退屈をできるだけ排除するよう仕向けてくる。自ら進んで苦しい人生を送りたい人は少ないだろうから、「好きなことだけすべき」や「嫌なことは避けるべき」といった考え方が好まれるのは不思議ではない。
しかし、近年のデータからすれば、このアドバイスによって実際に人生の成功や充実感を得られるとは言いづらく、むしろ逆効果になる可能性も高い。
「苦痛のパラドックス」をご存じだろうか。これは心理学の古典的な知見のひとつで、私たちが抱く価値の感覚は、「苦痛の総量」に左右されるという考え方だ。「楽しめることだけしたい」という気持ちは自然なものだが、本当に幸福感を高めたいなら、どうしても苦痛の体験がかせない。
たとえば、多くの登山家は「あえて険しいルートに挑む」という骨の折れる行為そのものに価値を見いだし、困難だからこそ達成時の喜びが大きいと語る。あるいはフルマラソンを走る者は、日々のつらいトレーニングそのものに意味を抱く。これらの行為が楽しいのは、登山やマラソンがもたらす苦しみそのものが、喜びの源泉になるからだ。
当たり前だが、どれだけ楽しいことでも、同じ体験が延々と繰り返されればやがて喜びは失せる。おいしい料理も何日も食べ続けたら嫌になるし、好きな音楽もエンドレスで聴き続けたら飽きが来るだろう。
このような現象は、ヒトの脳が持つ「同じ刺激には少しずつ反応を減らす」という性質を持つからだ。
私たち人類は、同じ刺激に順応"することで今の状態に進化してきた。もしヒトが同じ環境をずっと楽しめる生き物だったら、新しい食べ物を試すこともなく、より獲物が多い居住地を探すこともなかっただろう。そんな生活を続けていたら、天候の変化による食糧の枯渇、動物の移動による狩り場の変化といった場面に対応できず、ただ死を待つしかなくなってしまう。同じ刺激に飽きる能力を持てたからこそ、人類は今の繁栄を手にできた。
「苦痛のパラドックス」を示したデータは多く、苦痛によって人生の満足度が上がる現象が、これまでに何度も示されている。 ノートルダム大学の実験を見てみよう。研究チームは参加者を半分に分け、それぞれに異なる種類のケーキを食べるように指示した。
グループ1 粉末ミックスを使って、参加者が自作したケーキを食べる。
グループ2 グループ1と同じ粉末ミックスで作られた、"完成品”のケーキを食べる。
当然、ケーキの味はどちらも同じなので、普通なら食後の感想に違いは出ないはずだ。しかし、実際の結果はまったく異なり、全員に味の感想を訊ねてみたところ、自分でケーキを作ったグループのほうが「おいしかった」と答える確率が高かった。同じケーキを食べたはずなのに、自分が手間をかけたことにより、ケーキの味わいがよりよく感じられたわけだ。
その他にも「苦痛のパラドックス」の存在を示した研究は他にも多く、おおかたのデータをまとめると、私たちは"苦痛"と"快楽"が入り交じった行為に対して、"楽"だけの行為より150〜400%も強い満足感を覚えるようだ。
それでは、なぜ私たちは、わさわさ進んで苦痛”を得ようとするのか。「楽をしたい」と願う一方で、不快な感情に喜びを抱いてしまう心理は、どのように生まれたのだろう。
この心理には、心理学者のポール・ロジンが「良性マゾヒズム」と名づけた脳の仕組みが関わっている。
良性マゾヒズムとは、「人間の快楽は不快との落差で決まる」という現象のことだ。たとえば、辛い物を食べた後は水の味をより鮮烈に感じるし、怖い映画を鑑賞した後はいつもの日常が心地よく思え、サウナで熱さに耐えた後は水風呂が快い。これらの体験は、いずれもはじめに不快さを味わったことで、その後の快楽がより強調されたせいで起きる。このような快と不快のコントラストで生まれる快楽を、ロジンは良性マゾヒズムと名づけたのだ。
この心理が生まれた背景にもまた、進化論的な理由が隠されている。
今から600万年前、サバンナで狩猟採集生活を始めた人類は、猛獣の襲撃に替えたり、飢えや暑さに耐えたりと、常に複数の脅威に悩まされながら暮らしていた。もしこれらの脅威を"苦痛”としか認識できなかったら、狩りを続けるモチベーションは生まれず、人類は生存競争に敗れたはずだ。
そこで人類は、脳内に「不快さを乗り越えて得たものほど価値がある」と認識する心理を進化させた。「苦しみの先に報酬がある」と思うことができれば、目の前の困難に挑むモチベーションが高まり、ひいては種の生存率も上がるはずだ。ケニアのマサイが成人前の男子にライオンを捕獲させたり、アマゾンのサテレマウェが青年に毒アリに手を噛ませたりといった儀式を行うのも、「試練に価値を見いだす」という進化的なプログラムが背景にあるのだろう。
言い方を変えれば、私たちの脳は、不快な感情を抱くほど、その先にある心地よさや快感をよりよく認識できるように設計されている。生物があえて"苦痛"を求めるのは、ただのマゾヒズムではなく、快楽をより強く味わうために備わった自己調整システムだ。
なればこそ、私たちは「苦痛のパラドックス」から逃れるわけにはいかない。絶え間ない快楽はいずれ日常になり、その代わりに必ず平地な退屈が訪れる。すべての経験は快と不快のコントラストをもとに処理されるのだから、嫌なことを避けて"楽しさ"だけを追ったところで、充足感は遠ざかるばかりだ。
もし本当に幸福を得たいのなら、単なる"楽しさ"の持続を目指すのではなく、苦痛によって体験のコントラストを最大化する必要がある。私たちは、楽しくないことを経験しない限り、本当は楽しいはずのことを、心から楽しめない生き物なのだ。
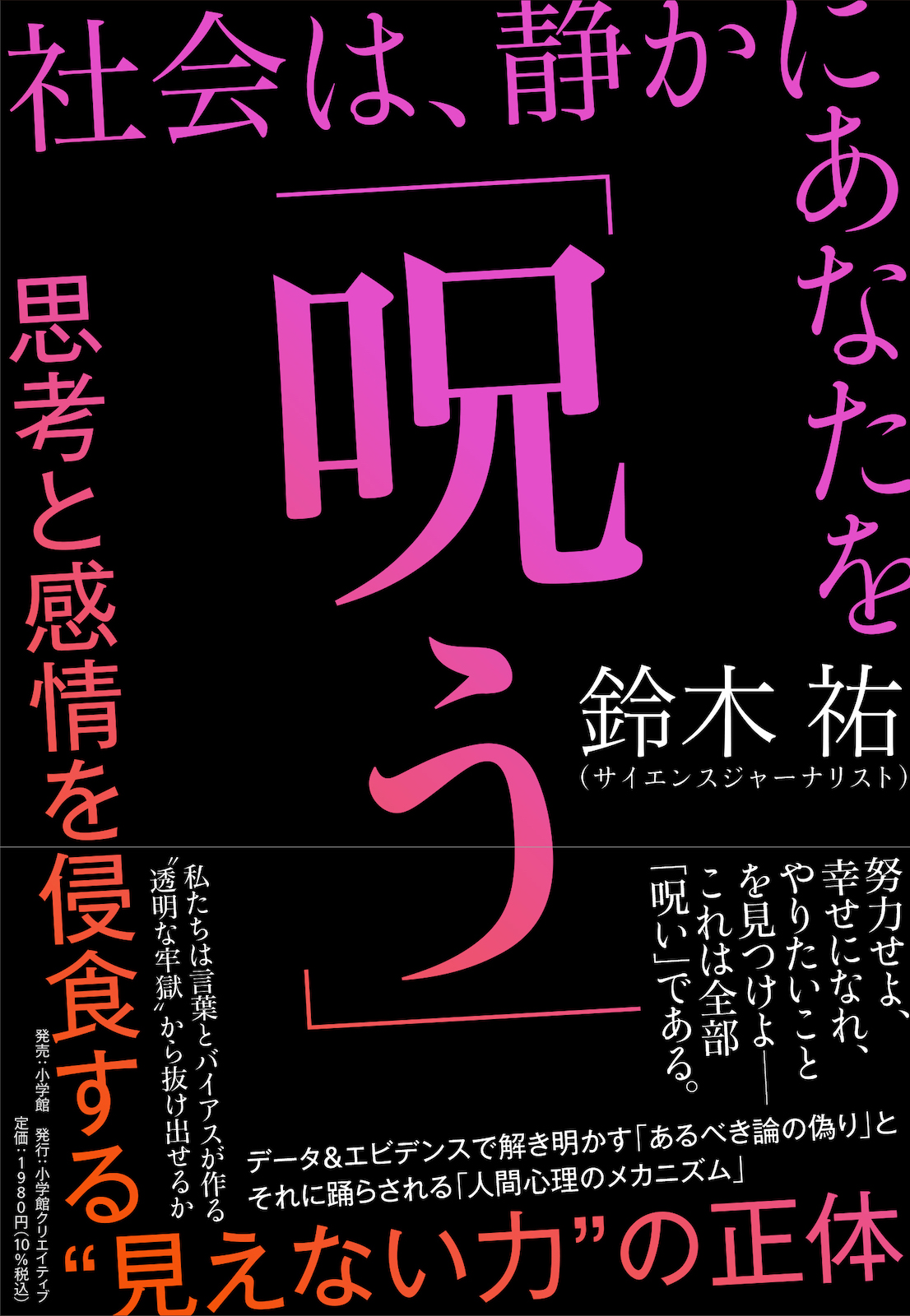
経済や幸福、働き方、遺伝や才能――私たちが「正しい」と信じてきた常識は、果たして真実なのか。人気サイエンスジャーナリスト・鈴木祐氏が、膨大な科学的エビデンスをもとに現代社会の“呪い”を解き明かす。思考と行動を縛る思い込みから抜け出し、真に自由になるための一冊。¥1,980/鈴木祐著/小学館クリエイティブ