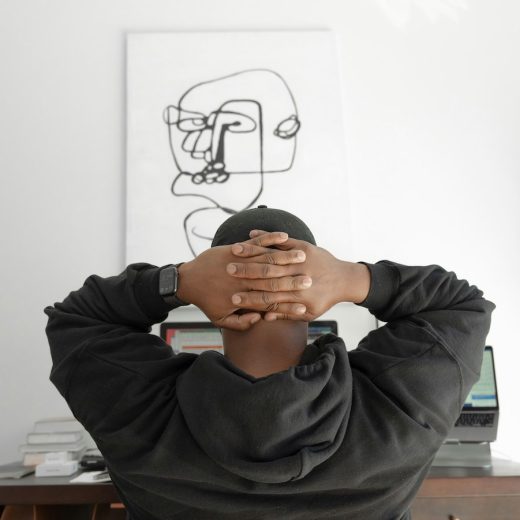世の中には性格が悪い人とそうでない人がいる。「性格が悪い人の正体」とは何なのか? うまくいく人とそうでない人の違いを研究し、3万人以上に脳科学的ノウハウを講演してきた脳科学者・西剛志が考察する。

知らないうちにあなたの心を消耗させる人たち
「なんであの人、圧が強くて文句ばっかりなんだろう…」
職場でも、家庭でも、SNSでも。話すたびに人の悪口を言ったり、急に怒鳴りつけてきたり、やたら人の感情を逆なでするような人、いるかもしれません。
こちらがどれだけ丁寧に接しても、ムッとしたり、見下すような態度をとってきたり…。そんな相手と関わり続けると、心がジワジワと削られていくような疲労感が残ります。
こういう人のことを、私たちはつい「性格が悪い」と呼んでしまいがちです。でも実は、脳科学や心理学の世界では、こうした“人を傷つけやすい性格”には一定のパターンがあることがわかってきました。
“性格が悪い人”の正体とは?
近年注目されているのが、人を消耗させる「ダークパーソナリティ」と呼ばれる性格です(*1)。
世界的な性格の研究では、以下のような「5つのダークな性格」が、他人に強いストレスを与える性格傾向として注目されています。
① ナルシスト:自分が一番でいたい人
• 常に目立ちたがる
• 他人の話に興味がなく、自分の話ばかり
• 他者への共感が薄い
② マキャベリスト:人を思い通りに操る人
• 相手の感情を冷静に読み取って支配しようとする
• 嘘をついても罪悪感を感じない
• 人間関係すら「目的のための手段」
③ サイコパス:他人の痛みに無関心な人
• 怒鳴る、暴言を吐くなど攻撃的
• 平然と嘘をつく
• 恐れや罪悪感を感じづらい
④ サディスト:他人を苦しめて快感を得る人
• 嫌がらせやSNSでの攻撃を面白がる
• 人の不幸話を好む
⑤ ダーク・エンパス:一見“いい人”な共感型の危険人物
• 共感性は高いが、その能力を「人を操る」ために使う
• 態度が急に冷たくなったり、優しさが“ご都合主義”
もともと、性格研究では「ダークテトラッド」といって①〜④の悪の性格は知られていました。しかし近年、第五の性格として⑤のダーク・エンパスも注目されています(*2)。
ダーク・エンパスの人は、一見すると外向性も高く協調性も高いので、いい人に見えます。しかし、その裏では人を操ることに快感を感じるため、気づいたらその人の言う通りにお金を支払ったり、友達との縁を切って孤立してしまったり、操作されてしまっていることがあります。
詐欺や、ブランド品を貢がせるなどホストや夜の仕事系にもこのようなタイプの人がいます。自分の都合のよいときだけ優しいというような気分にムラがある人も注意が必要です。
「この人、もしかして…」と感じる相手が、どこかに思い浮かんだとしたら、その人には少し注意が必要かもしれません。
“悪い性格”は、生まれつき? 育ち?
一卵性双生児を対象とした研究では、これらの性格傾向には遺伝的要素があることが明らかになっています(*3)。
• ナルシシズム:約59%が遺伝
• サイコパス:約64%が遺伝
• マキャベリズム:約31%が遺伝
しかし、この数字を見ると、すべてが遺伝で決まる訳ではないことがわかります。つまり、生まれつきの“性格のクセ”がある一方で、環境の影響も大きいということです。
2025年にコペンハーゲン大学が発表した約180万人の大規模研究では、経済格差や貧困率が高い地域ほど、こうした“ダークな性格”の割合が高くなる傾向があると報告されています(*4)。
また、幼少期に愛情を十分に受け取れなかったり、家庭内で暴力や無視を経験すると、他者への共感が育ちづらくなり、サディスティックな傾向が強まる可能性も指摘されています(*5)。
振り回されずに、静かに心を守る技術
とはいえ、こうした人とまったく関わらずに生きていくことは容易ではありません。
上司がそうだったり、家族だったり、距離を取れない相手もいるかもしれません。
そんなときに有効なのは、「物理的に近くても、心理的に距離を取る」ことです。
おすすめしたいのは、「実況中継メソッド」。
たとえばその人が理不尽なことを言ってきたら、心の中でこうつぶやいてみます。
「あ、また来たぞ。マイワールド炸裂中だな」
「今、支配モードに入ったな。見事なパターンだ」
まるで映画を見ているように、一歩引いて観察することで、私たちの脳はストレス刺激を“自分ごと”として処理しなくなる傾向があります(*6)。
性格が悪い人は「宇宙人」かもしれない
“性格が悪い人”との出会いは、避けられないものです。でも、その人にどう反応するかは、自分で選ぶことができます。一番大切なのは、「巻き込まれない」こと。
害を与える人からは物理的に距離をとることが一番ですが、ただ彼らを「ストレス源」として捉えるのではなく、「他の星から来た人だ」と思えたとき、私自身、ストレスがとても軽くなった経験がありました。
世の中には、どうしても理解不能な人がいます。しかしそれは、進化の過程で様々なパーソナリティーを生み出すことが、多様性につながり生命本来の強さにつながるからでもあります。
私たちは、相手にどこかで変わってほしいと期待してしまうと不幸になります。期待を手放して、是非、相手のノイズを自分の世界に入れないように工夫することも大切かもしれません。

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。武蔵野学院大学スペシャルアカデミックフェロー。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。2002年に博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子供まで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて3万人以上に講演会を提供。『世界仰天ニュース』『モーニングショー』『カズレーザーと学ぶ。』などをはじめメディア出演も多数。TBS Podcast「脳科学、脳LIFE」レギュラー。著書に20万部のベストセラーとなった『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』、『1万人の才能を引き出してきた脳科学者が教える 「やりたいこと」の見つけ方』など海外を含めて累計42万部突破。最新刊『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』も好評発売中。
<参考文献>
*1 Paulhus, D. L., Buckels, E. E., Trapnell, P. D., & Jones, D. N. (2021). Screening for dark personalities: The Short Dark Tetrad (SD4).European Journal of Psychological Assessment, 37(3), 208–222
*2 https://www.wellandgood.com/health/dark-empath
*3 Vernon, P. A., Villani, V. C., Vickers, L. C., & Harris, J. A. (2008). A behavioral genetic investigation of the Dark Triad and the Big 5. Personality and Individual Differences, 44(2), 445–452.
*4 Zettler I, Lilleholt L, Bader M, Hilbig BE, Moshagen M. Aversive societal conditions explain differences in "dark" personality across countries and US states. Proc Natl Acad Sci U S A. 2025 May 20;122(20):e2500830122
*5 Foulkes, L. (2019). Sadism: Review of an elusive construct. Personality and Individual Differences, 151, Article 109500.
*6 Kross E. et.al. “Self-talk as a regulatory mechanism: how you do it matters”, J. Pers. Soc. Psychol. 2014, Vol.106(2), p.304- 24/Eddie Harmon-Joes, et.al. “Does Negative Affect Always Narrow and Positive Affect Always Broaden the Mind? Considering the Influence of Motivational Intensity on Cognitive Scope”, Current Directions in Psychological Science, 2013, Vol.22(4), p.301-307/Moser JS. Et.al. “Third-person self-talk facilitates emotion regulation without engaging cognitive control: Converging evidence from ERP and fMRI”, Sci. Rep. 2017, Vol.7(1):4519.