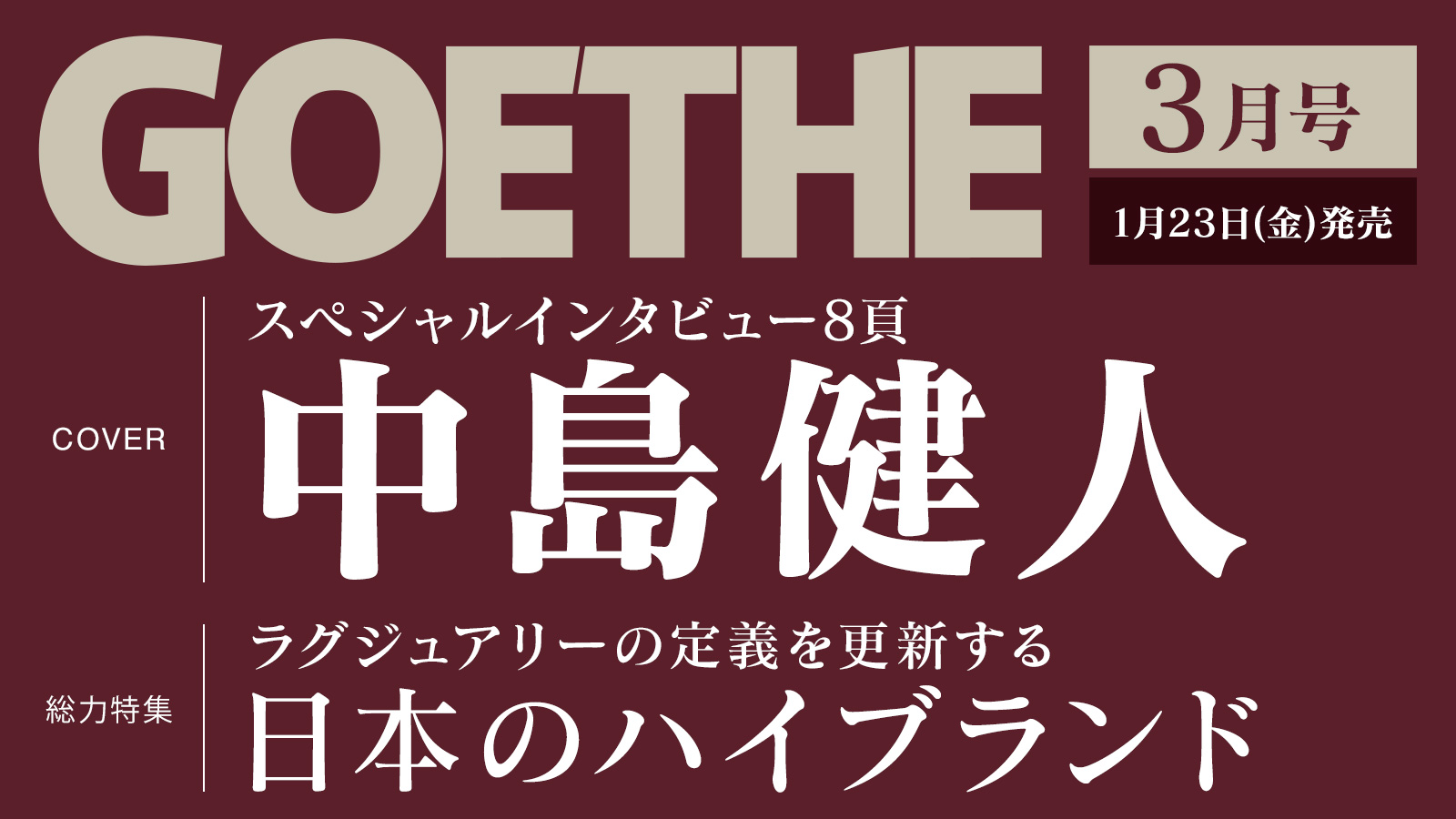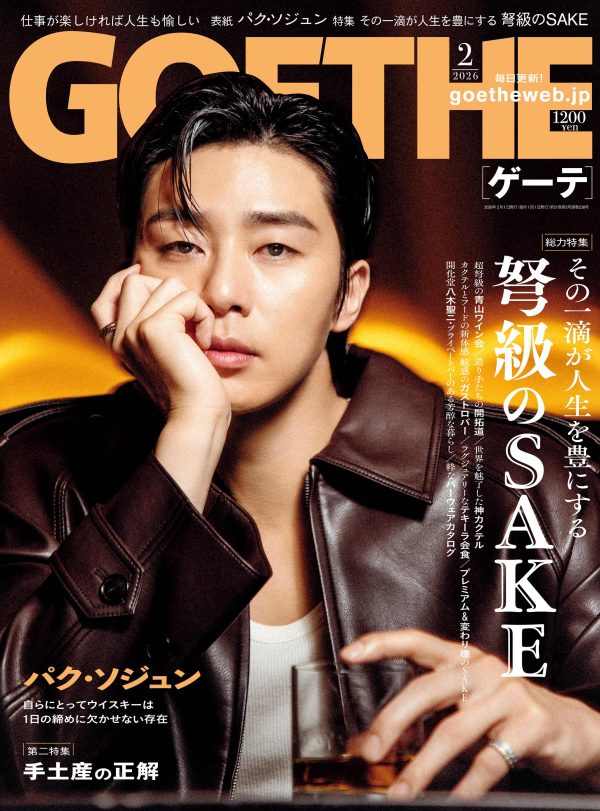一糸乱れない入場行進(同調圧力)、1球ごとに指示を送るサイン野球(指示待ち族の蔓延、上位下達)など、高校野球は日本社会の縮図のようなもの。部員10人からスタートした弱小野球部を甲子園へと導いた青森県「聖愛(弘前学院聖愛高等学校)」の原田一範監督は、その高校野球界の体質に屈することなく、次々と改革を打ち出している。自身の挑戦の日々を綴った著書『1年で潰れると言われた野球部が北国のビニールハウスから甲子園に行った話』を出版した原田監督に話を聞いた。#前編

指示待ち族を自主的に変えたノーサイン野球
高校野球はもちろんプロ野球でも、試合をテレビで観ていると、一球ごとにバッターがベンチを振り返り、サインを確認するシーンをよく目にする。
「高校野球では、『プレーボール!』の掛け声がかかった瞬間から、監督が一挙手一投足を指示することも珍しくありません。私たちも、2013年に初めて夏の甲子園に出場した頃まではベンチからの私の指示で野球をしていましたが、2018年頃から指示なしで選手の自主性に任せる“ノーサイン野球”に変えました」
“金なし実績なし”の弱小だった弘前学院聖愛高校野球部を、青森を代表する強豪校へと育てた原田一範監督は、スポーツ界ばかりではなく、ビジネスの第一線で活躍する人たちからも多くを学び、部の運営に活かしているという。
ノーサイン野球のきっかけとなったのは、実業家で経営者の鴨頭嘉人さんの講演を聞いたこと。そこで「サッカーやラグビーのように、監督の指示やサインがなくても、一人ひとりが自主的に判断する組織でないと、変化のスピードが上がった現代のビジネス環境に適応できない」という話を聞いて、「高校卒業後、部員たちが社会で活躍するためにも、主体性に乏しい“指示待ち族”を育ててはダメだ」と猛省したのだ。

監督が180度方向転換しても、ずっとサイン野球に慣れてきた選手が、すぐさまノーサインでプレーできるわけもない。そこで練習や試合の最中、次に打席に入る準備をしているバッター、攻守交代時の野手などに、「この状況、お前ならどうする?」といった“問いかけ”を粘り強く積み重ねながら、選手自らが考える力を育て、少しずつノーサイン野球を浸透させていった。
「ベンチから見ている監督の方が全体を俯瞰し、多くの情報から正しい判断が下せるはずですが、聖愛はサイン野球時代と比べてノーサインにしてからの方が勝率はむしろ上がっている。監督が一人で考えるより、部員全員が一人ひとりが状況に応じて、自らの立場で臨機応変に考える方が、チームは強くなるのでしょう」
ノーサイン野球の土台になっていると原田監督が指摘するのが、聖愛の1人1リーダー制。投手や野手といったポジションごとだけではなく、道具確認、グラウンド整備、服装といったプレー以外の細やかな分野に至るまで、選手全員が何らのリーダー役を担っている。 「リーダーになると『自分はみんなの役に立っている』という自己有用感が育ち、ベンチ入りできなくても、チームのなかで自分が輝ける居場所が見つけられる。それが何事も他人任せにしない、主体性につながっていくんです」

1977年青森県北津軽郡生まれ。弘前工業高校野球部出身。1996年母校・弘前工野球部コーチに就任。2001年4月、弘前学院聖愛高校野球部創部と共に監督就任。現在まで25年間監督を務め、これまで2度夏の甲子園出場を果たす。その果敢な取り組みは各地の指導者も注目する。思考と言語化でゼロから強いチームを作り上げた挑戦の日々を綴った著書『1年で潰れると言われた野球部が北国のビニールハウスから甲子園に行った話』(幻冬舎)が話題。
監督は管理者ではなく“見守り役”
怒ると叱るは違う。怒るは自分の感情の発露であり、叱るは相手のためを思って行動修正を促すためのもの。ゆえに上司は部下を怒るよりも叱るべきである……。よく聞く話だが、原田監督は怒るも叱るも変わらないという。
「怒るのはダメで叱るのは良いというのは、都合の良い“神話”のようなもの。高校野球の指導者は『あのとき真剣に叱ったから、以来チームの雰囲気が一変して一皮剥けた』といった話をしますが、それはコントロールできなかった感情の爆発を正当化したいだけ。もしも叱ることで相手の行動を変えられるとしたら、普段から一人ひとりと濃密なコミュニケーションを交わし、みんなが『このチーム、この組織に自分は必要とされている』という実感を持っていることが必須条件。必要とされていないと思っていたら、どんな言葉も心には響かないと思います」
とはいえ、未熟で無配慮な行いを怒りたい、叱りたいという気持ちが抑え難い場面もあるだろう。そこで大事なのは、人は誰しも変われるし、いつも成長過程にいるという温かい理解。
「監督やコーチは管理者ではなく、あくまで見守り役。保育園で遊んでいる子どもたちが不注意で転んでも、保育士さんは『なぜ転ぶの!』などと叱責しないですよね。保育園児だけではなく、私を含めて人間は成長の過程にいます。少なくとも上に立つ人間は、次は成功できるように見守り、成長を促す態度が求められると私は思っています。もう一つ不可欠なのは、決して諦めない気持ち。見守り役が相手の成長の可能性を諦めたら、そこで終わりです」

“心”より先に“行動”を整える
心技体と言われるように、野球を始めとするスポーツでは「心」を重視する。技術や身体が十分でも、ここぞというときに心が乱れて平常心が保てなかったら、実力は出せない。それは仕事でも何ら変わりはない。
「でも、いきなり心を整えるのは難しい。心は目に見えないし、つねに揺れ動いているものだからです。ですから、まず目に見える行動を整える。整理整頓、道具の手入れ、挨拶や掃除や食事の作法などです。これらが学べるのが寮生活であり、日常生活での凡事徹底がメンタルトレーニングの基礎となります。心が先ではなく、まず何かを『やる』のが先決だと考えています」
さらに聖愛では、アファメーションやサイキングアップといった心理学のメソッドも取り入れている。アファメーションとは自己暗示の一種で、こうなったらいいという未来を自分の言葉でポジティブに宣言すること。サイキングアップは、大声を出すなどして気分を高める手法だ。この両者を有機的にリンクさせるのが、原田流。
「聖愛の部員は、私が編集したオリジナル野球日誌『SPD』を書いています。そのトップ項目は『予祝日記(今日はどんな1日でしたか?)』。1日の始まりに、『日本一実現に向けて充実した練習ができた』といった理想的な1日を先に書き込み、アファメーションで気分を上げます。
続いてその内容を、一人ひとりが練習時に声に出してサイキングアップします。試合中に円陣を組んで『いくぞ!』などとみんなで唱和するのもサイキングアップですが、聖愛では普段の練習時から『守備練習、絶対ノーエラーでやり切るぞ』といった自分なりの目標を思い思いに声に出して気分を盛り立てているのです」
書く、声を出すといった目にみえる行動の変化が、心を整えることにつながるのだ。
24年前、わずか部員10名でスタートした聖愛だが、2025年、新たに仲間に加わった1年生は27名。全体で67名の大所帯に膨れ上がった。
夏の甲子園に2度出場した際、ベンチ入りメンバーは全員が青森県出身だったが、今年の1年生は秋田や岩手といった隣県ばかりではなく、埼玉、愛知、大阪と全国から集まっている。初の試みとして、台湾から留学生1名も受け入れた。
「私たちの究極の目標は、目の前の勝利ではなく、高校卒業後を見据えた部員たちの人間的な成長。勝利至上主義ではなく、成長至上主義であり、実社会で直面する困難を突破できる人間力を身につけて欲しいと願っています。そのきっかけの一つは、若いうちから異なる考え方や文化に触れてさまざまな経験をすること。県内外の部員と留学生がごちゃ混ぜになり、互いに刺激し合って成長する姿を見ているのが、今は嬉しくてたまりません」