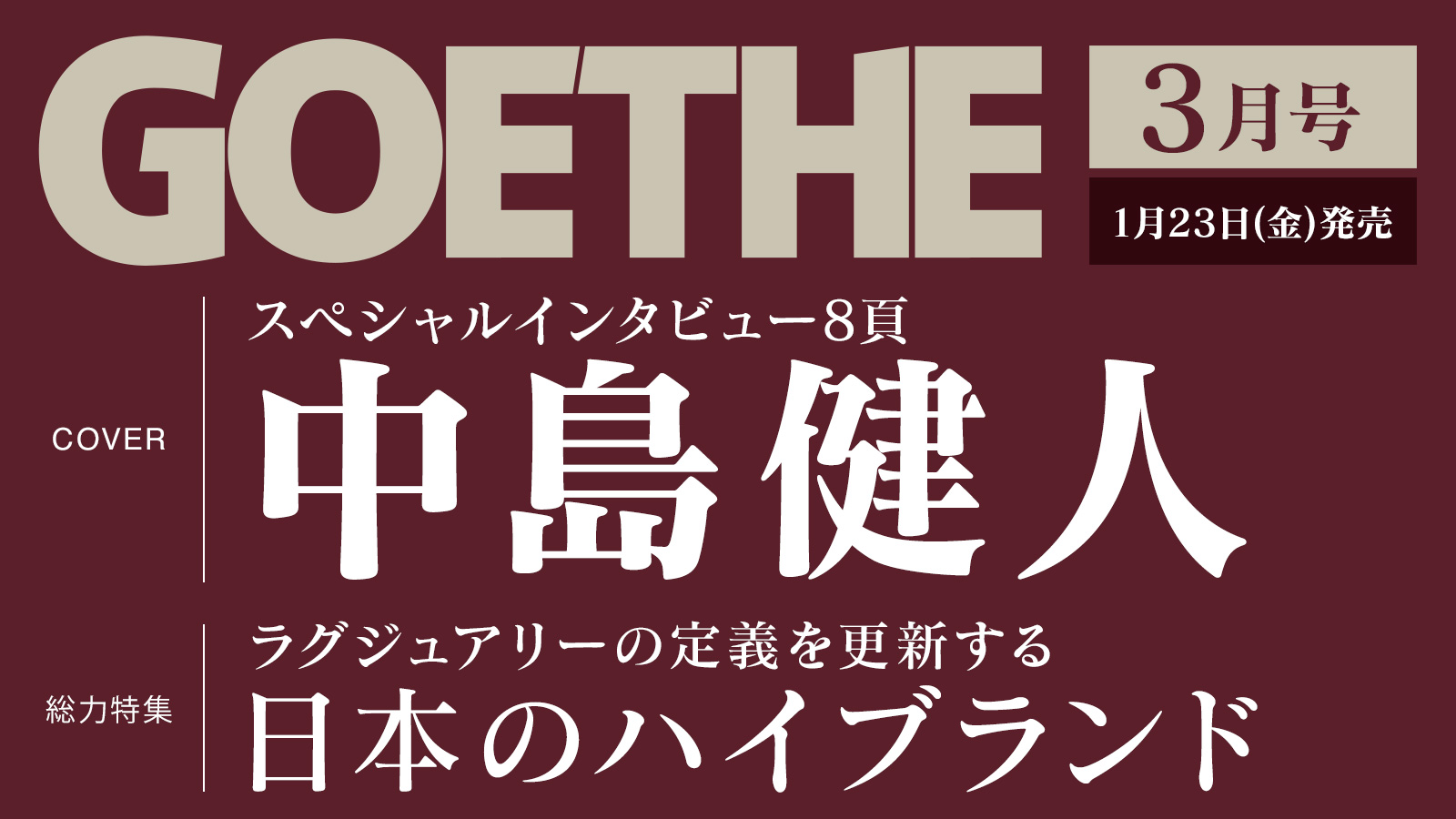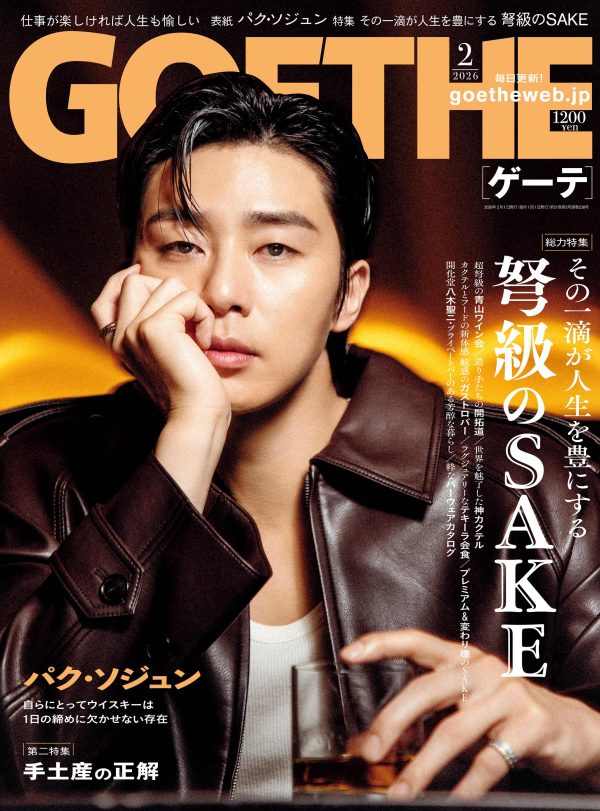青森県の高校野球界は長年、光星(八戸学院光星高等学校)と山田(青森山田高等学校)という全国レベルの2強が牽引してきた。そこへ割って入ったのが、聖愛(弘前学院聖愛高等学校)。2000年、女子校から共学へ移行するタイミングで翌年野球部を新設すると、これまで夏の甲子園に2度出場した。率いるのは、原田一範監督。学歴も人脈もない無名の人物が、どうやって全国レベルのチームを作り上げたのか。その常識破りな創意工夫と挑戦の日々を綴った著書『1年で潰れると言われた野球部が北国のビニールハウスから甲子園に行った話』を出版した原田監督に話を聞いた。#後編

青森の強豪校になった今も“ビニールハウス”は現役
聖愛の代名詞は、室内練習場の変わりに活用している大小二つのビニールハウス。野球部には、雨天時のために室内練習場が欠かせない。1年のおよそ3分の1は雪に閉ざされる青森のような雪国ならなおさらだ。
「でも、建築会社に頼んで本格的なものを建てるとなると、2億円ほどかかります。学校にそんな予算はないので諦めていたところ、部員の保護者から『農業用ビニールハウスを室内練習場として使えませんか?』という提案を受けたのです」
そう語るのは、弘前学院聖愛高校野球部がつくられた2001年から監督を務め、“金なし実績なし”の弱小野球部を甲子園出場まで導いた原田一範氏だ。
2013年、聖愛が夏の甲子園初出場を叶えた後、より大きな二つ目のビニールハウス練習場が完成する。初出場ながら2回勝てたため、長引く甲子園滞在費を賄うために地元民らが多額の募金をしてくれた。その剰余金で建てたのだ。
「どちらも現役。ビニールハウスは密室なので晴天だと20度くらいまで上がり、寒い季節でも快適です。夏場は晴天だと室温は50度以上になりますが、そんな過酷な環境での練習は夏の甲子園の暑さ対策に役立ちました(笑)」

1977年青森県北津軽郡生まれ。弘前工業高校野球部出身。1996年母校・弘前工野球部コーチに就任。2001年4月、弘前学院聖愛高校野球部創部と共に監督就任。現在まで25年間監督を務め、これまで2度夏の甲子園出場を果たす。その果敢な取り組みは各地の指導者も注目する。思考と言語化でゼロから強いチームを作り上げた挑戦の日々を綴った著書『1年で潰れると言われた野球部が北国のビニールハウスから甲子園に行った話』(幻冬舎)が話題。
学歴も人脈もない無名監督の挑戦
聖愛野球部の創設メンバーは10名で、うち野球経験者は5名のみ。いちばん上手だったのは元体操部の女子だった。無名監督が率いるそんな素人集団は、初公式戦では2対29で5回コールド負け。ところが現在は青森県を代表する強豪校に成長しており、夏の甲子園予選では光星、山田と肩を並べるシード校4校の一角を占めている。
ここまで強くなれた秘訣はどこにあるのだろうか。
「いちばんの原動力は、私のコンプレックス。野球好きだったオヤジの影響で小学校3年生から野球を始め、ずっと真面目に打ち込んでいたのに、中学は補欠、高校では夏の甲子園予選で自分のミスから1回戦負けでした。野球部を作る決断を下した聖愛の校長先生からも、『野球に力を入れるつもりはない。そのつもりなら、あなたのような無名の人は呼ばない』と明言される始末。けれど、それで吹っ切れて『このチャンスを絶対モノにして、連敗続きの野球人生を逆転勝利にしてやる!』と闘争心に火がついたんです」
でも、監督一人がコンプレックスを武器に闘争心をメラメラ燃やしても、主役の選手がついてこなければチームは強くなれない。成長の秘訣は、こんな原田監督の積極策にあった。
「自分たち以外は、全チーム強豪校。強いところと試合すれば、必ず学びがあり、監督の私も部員たちも経験値が高まります。創部3年目には、公立校で唯一、甲子園春夏連覇を成し遂げている古豪・箕島高校(和歌山)と練習試合を組みました。私は無名なので、断られても傷つく妙なプライドがないからこそ、果敢に『うちと練習試合をお願いします』と電話できる。名門や強豪と呼ばれる学校の監督さんほど謙虚かつオープンなので、これまで練習試合を断れたことはたった1回しかありません」
ビッグネームと戦えば戦うほど、選手たちのメンタルも強くなる。
「全国的に知られる有名校と試合ができただけでも、部員たちは手応えを感じる。高校生は純粋ですから、少しでもいい試合をしたら大きな自信につながり、『光星、山田、何するものぞ!』という気構えができてきます。その繰り返しでいわゆる“名前負け”をしなくなり、実戦で普段以上の実力が発揮できるようになりました。やがてうちの急速な成長ぶりを目の当たりにして、『ここでやってみたい!』という実力者が青森県内から集まるようになり、徐々に地力が養われていったのです」
驚くことに、平日の練習時間は1日たった3時間。学生の本分である学びの時間を確保するためだが、短いゆえにいかに効率的かつ濃密に練習するかに知恵を絞る。
「野球は状況が常時変わるので、つねに考えることが求められますが、練習が長すぎると流れ作業になり、何も考えなくなる。短時間だからこそ、『何のためにこの練習が必要なのか』をいつも考えながら、結果を踏まえて次は何をすべきかという『仮説と検証』を部員は繰り返します。大事なのは練習時間の長さではなく、仮説と検証の数だと私は思っています」
時間が限られるので動作は自然と機敏になり、移動はつねに駆け足だ。
「対戦相手からは『聖愛の速さにはついていけない』と嘆かれますが、機敏に動いて早く守備位置に着けたら準備が十分できる。そんな小さな積み重ねも、うちの強みですね」

軍隊式を拒否し、開会式の入場行進で帽子を振る
春夏の甲子園大会を頂点とする高校野球開会式の入場行進といえば、まるで軍事パレードのような一糸乱れない軍隊式の行進が定番。ところが、2024年夏の甲子園青森県大会で、聖愛の選手は入場行進で帽子を取り、スタンドに向かって笑顔で帽子を振った。当時の貴田光将主将を中心に、選手たち同士が話し合い、実現に漕ぎつけたのだ。
「オリンピックの入場行進では、代表選手たちは思い思いに手や帽子を振ったりする。同じ高校スポーツでも、2024年の全国高校サッカー大会の開会式では、青森山田はりんご、前橋育英はだるまを持って行進し、地域の魅力をアピールします。聖愛はキリスト教系の学校で平和教育にも力を入れているので、昔ながらの軍隊式の行進に疑問を持ったのです」
この年、聖愛は決勝戦で青森山田に惜敗して甲子園出場を逃したが、2校だけの閉会式でも同じように聖愛は貴田主将の音頭で応援席に笑顔で帽子を振った
「私が貴田に『もし優勝しても、帽子を振ったのか?』と尋ねると、『勝っていたら、振っていません。だって相手が嫌な気持ちになると思うので』と話してくれました。『負けても周囲に感謝を忘れないグッドルーザーであれ』といつも言ってきたことを実践してくれて、彼らの監督であることが誇らしく思えました」
この清々しい一連の行いに対し、一般社団法人日本スポーツマンシップ協会から「日本スポーツマンシップ大賞2025 ヤングジェネレーション賞」が贈られた。
──だが、2025年7月11日の夏の甲子園青森県大会の開会式で、聖愛は帽子を振らなかった。
「4月に青森県高野連理事会から、開会式のパフォーマンス禁止という通達があったんです。5月には理事長から個人的に呼びだされて、『甲子園の伝統を守りたいから、今年は通常通り行進してくれ』と頼まれました。理事長は聖愛を応援してくれていますが、伝統を守りたいという気持ちも人一倍強かったのでしょう。『本当に申し訳ない』と真摯に頭を下げる理事長の気持ちもわかりますから、部員たちと話し合って帽子を振らないと決めました」

高校野球を変えれば、日本が変わる?
Googleで「日本のスポーツ」と検索すると、筆頭に挙げられるのは野球。そして「特に高校野球は国民的行事になっている」と記されている。
だからこそ高校野球が日本のスポーツ界全体に与える影響は大きく、高校野球が変われば日本のスポーツが変わり、ひいては日本社会も変わる。原田監督はそう信じている。そのために見直したいポイントはどこなのだろうか。
「何よりも勝利至上主義。甲子園を始め、高校野球はトーナメント戦オンリー。一度負けたら、そこで終わりです。同じ野球でも、大学野球もプロ野球もリーグ戦であり、高校サッカーにはリーグ戦も用意されています。トーナメント戦だと、勝利至上主義にならざるを得ないから、勝つためにレギュラーをある程度固定して試合に臨むしかない。すると公式戦でベンチに入れないメンバーが出て、『自分はダメなんだ』と誤解して自己肯定感を下げかねない。野球人口の減少が問題視されていますが、一因は勝つために毎日長時間練習し、指導者の指示・命令を絶対視する高校野球モデルを、小学生の段階から押し付けようとするからです」
トーナメント戦主体の仕組みが変えられないのなら、せめてベンチ入りのメンバーを試合ごとに自由に入れ替えられるようにしてほしい。それが原田監督の切なる願いだ。
「甲子園では地方予選も本戦も、ベンチ入りメンバーは20名のみで固定。入れ替えは認められません。長年監督を務めていて何より辛いのは、ベンチ入りメンバーを発表するとき。神奈川県のように、春と秋の大会ではベンチ入りメンバーを25名にして自由な入れ替えを認めているところもあります。そうすれば公式戦により多くの部員が出せる。球児が大切にしている野球で自己肯定感を下げない試みを、青森県を含めて全国に広げてほしいんです」
失敗したら叩かれ、敗者復活戦もない。努力しても、限られた人にしかスポットライトは当たらない。そんな窮屈な日本社会を変える契機を、原田監督は高校野球から作りたいのだ。
※後編に続く(7/20公開)