創業社長の共通点とは、なにだろうか。七転び八起きの人生、生死をかけた壮絶なる体験、事業立ち上げの苦労……。それぞれに悲喜交々(ひきこもごも)のストーリーはあるのだが、必ず持ち合わせているのが、物事を0(ゼロ)から1(イチ)へと推進させた経験だろう。連載「ゼロイチ 創業社長物語」では、そのプロセスをノンフィクションライター鈴木忠平が独自目線でひも解く。二人目は「AR-Ex(アレックス) Medical Group」を創設した林英俊。
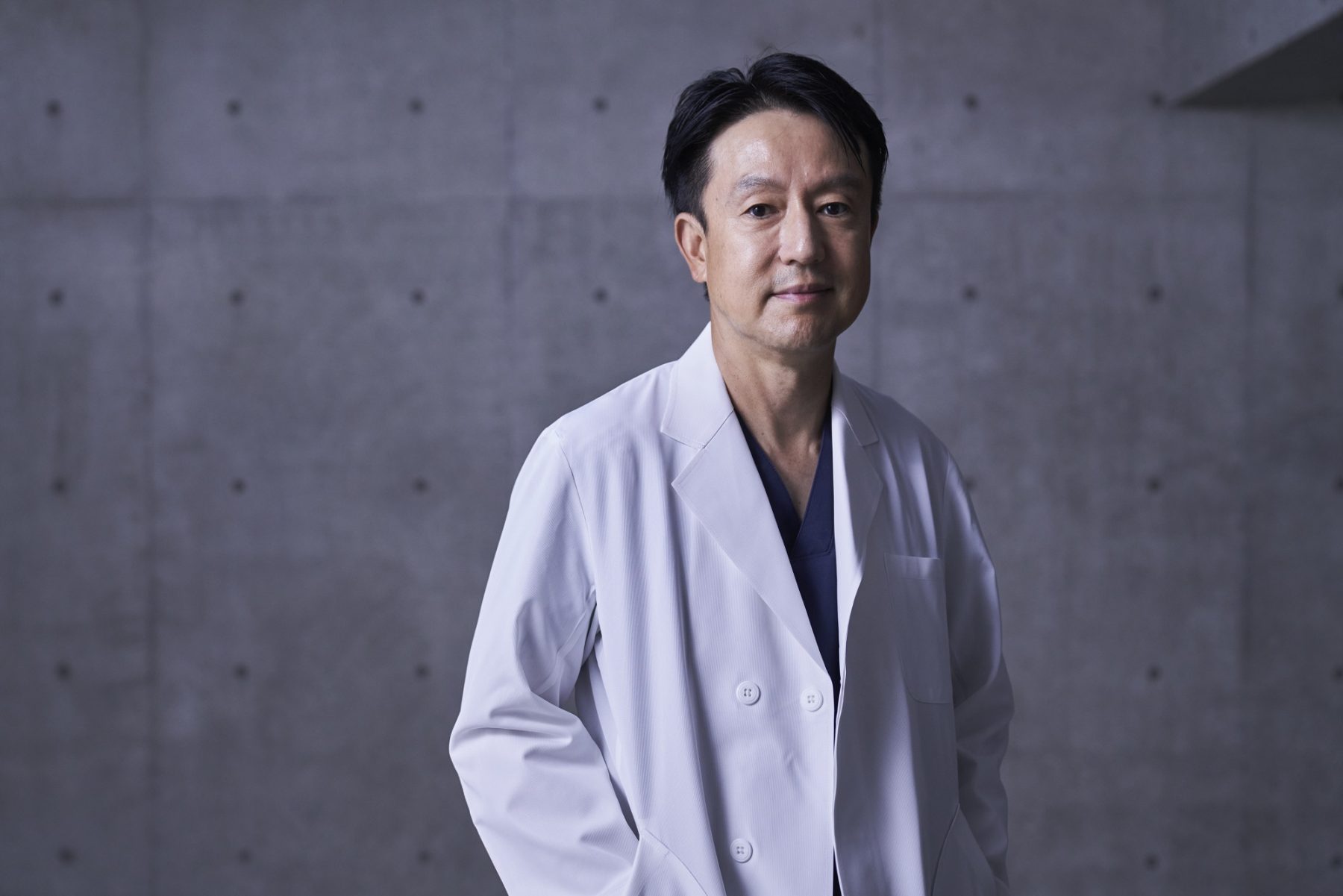
権威の重々しさとは真逆の雰囲気
林英俊という医師がいる。
国内最大級の整形外科グループ「AR−Ex」を創設した人物であるが、触れた者の印象に残るのはそれよりも、思考が溢れ出すように早口で喋り、成すべきことが一刻を争って待っているかのように早く歩くポップな姿かもしれない。
もう10年ほどアシスタント的な立場にいる大川富美子は何度も直言してきた。
「先生、もっとゆっくり喋ってください。何を言っているのか、患者さんがわかりませんよ」
ただでさえ1.5倍速のように生きている林の日常は、金曜日になると少し慌ただしさを増す。オペがあるのだ。
朝、鳥が囀(さえず)りだす時刻になると、東京世田谷区にある自宅の二階から「大川さん、いくよお」という声がして、軽快でどこか愉しげな足音が降りてくる。それを聞くたびに大川は思うことがある。
なぜ、この人はいつまで経っても、いわゆる世間的な「ドクター」のイメージからはみだし、当てはまらないのだろう。
都内に4つ、長野に3つ、埼玉に1つ、と計8つのクリニックをまとめる理事長であり、メスを握れば、何人も立ち入れないような技術を持っている。ただ、どういうわけか、林から権威の重々しさを感じたことはなかった。
その特異性がことさら浮き彫りになるのは、日本プロ野球界の盟主といわれる球団、読売ジャイアンツのチームドクターという肩書きを背負っているときだろう。
「林先生のような人に、ジャイアンツのドクターになってもらいたいんですーー」
そんな声が聞こえてきたのは、10年ほど前のことだった。
大川は当時、世田谷区奥沢にある大脇病院でスポーツ整形外科のトレーナーをしていた。そこへ週に1回の外来と、オペのためにきていたドクターが林であった。初めて会ったときからどこか他の医師とは違っていた。林はトレーナーである自分と接するときはトレーナーのように、理学療法士と接するときは理学療法士のように見えた。つまり接する人間と目線の高さが同じなのだ。
そのころ、大川のもとにはジャイアンツにいる旧知のトレーナーから「今からレントゲンを撮ってもらいたい」「すぐにMRI(磁気と電波を用いた画像検査)を撮ってほしい」という緊急の相談が頻繁に舞い込むようになっていた。
天下の巨人軍には担当医がいるはずが、と大川は思ったが、現場のトレーナーはどこか困っているようだった。聞けば、自分たちが24時間体制で選手たちの治療に従事していても、外部にいるドクター側とは温度差があり、緊急の要請に応じてもらえないことがあるのだという。
その求めに時間を問わず、「いいよ」と応じたのが林だった。
プロ野球はシーズン中になるとほとんど毎日試合があり、現場医療は時間との勝負でもあった。トレーナーたちは次第に林を頼るようになっていった。そうした関係がしばらく続き、やがて故障した選手が訪ねてくるようになった。監督の原辰徳が治療をしてもらいたいとやってきたこともあった。
そして2013年、現場のトレーナーから請われる形で、林は巨人軍のチームドクターになったのだった。
「大川さんはこの仕事で何がしたいの? この話、面白そうだから一緒にやってみない?」
大川が林と行動をともにするようになったのは、それからだった。
プロ野球の医療現場を初めて覗いてみると、現場のトレーナーたちが何に葛藤しているのか垣間見ることができた。当時、ドクターと彼らの関係は上意下達のように映った。
ある選手が怪我をして手術が必要だと診断されると、トレーナーたちの手元を離れて専門医のところへいく。そして「手術は完璧だよ」というドクターのひと言が添えられて、彼らのところへ戻ってくる。
だが、選手にとってもトレーナーたちにとっても、本当の回復とはパフォーマンスを取り戻すことだ。それなのに、メスを入れてから一軍のスポットライトの下に戻るまでの長い過程はトレーナーたちが一手に責任を負っていた。たとえ回復が思わしくなくても、手術に疑義を挟むことはタブーであった。その断絶に彼らは苦悩していた。
巨人軍のチームドクターは代々、学閥推薦によって決められてきたという。東京慈恵医科大に始まり、名だたる大学病院によってドクターが指名され、継がれてきた。そんななか、トレーナー推薦によって担当医となったのは、おそらく球団史上で林が初めてだった。
これは球界の、ひいては日本の医学システムへの挑戦かもしれないーー。
大川は医学界の人間ではなかったが、林を通してスポーツ医療の第一線を見ていると、そんな気がしてきた。そして、なぜ林のようなドクターが巨人軍に請われたのか理解できた。
第一に、林は「わからない」と言える医師であった。球団トレーナーから判断を求められ、「これは僕にはわからない。君はどう思う?」と逆に訊き返すことがあった。最初は呆気にとられていたトレーナーたちが、やがて目を輝かせるようになっていった。
「僕には自分が絶対に正しいとか、偉いとか、そういうプライドはない。ただ、選手のパフォーマンスを取り戻すことについては、プライドはあるよ」
林の治療は断絶を生まず、永続的であった。
例えば、ジャイアンツの外国人選手にスコット・マシソンという投手がいた。2012年の来日から毎シーズン投げ続け、リーグ最多登板と最多ホールドの栄誉も獲得したことのあるリリーバーだった。その鉄腕が34歳になった2018年に、左膝の故障で戦線離脱することになった。
軟骨が激しく損傷しており、現代医療でも回復は難しい状態だった。投手人生において肩や肘に何度もメスを入れてきた右腕はそれでもマウンドに立つことを望んだ。可能性の薄さをよく分かっていたはずの林もそれに応えた。
「僕はスコットのガッツが好きなんだよ」
最終的にマシソンはシカゴで手術を受けることになった。林は同行して、オペに立ち合った。予想した通り、結果は思わしくなかったが、それでも諦めなかった。帰国してからは二軍でリハビリを続けた。林は彼の膝にたまった水を抜き、炎症を抑える注射を打って、なんとかマウンドに立てる状態にした。
「あそこまでやった選手がどうするか、あとは本人の哲学なんだ。本人が望むなら、1分でも1秒でも長く投げられるようにする。僕にできるのはそれだけだよ」
大川は、昼夜を問わずマシソンが林の自宅にやってくるのを何度も見た。リビングの灯りの下で処置が終わると、傷だらけのリリーバーは帰っていく。その後の林のやるせなさそうな表情も見た。
「投手は悲しい。いつか投げられなくなる。それが明日かもしれないし、1年後かもしれない。でも、必ず投げられなくなる……」
2019年、マシソンは夏場まで28試合に投げて、燃え尽きるように引退した。巨人軍の歴史に残る鉄腕は、誇らしげにユニホームを脱いだ。その表情は彼が余すところなく投げ切ったことを物語っていた。
繋げるためのメス
オペが待つ金曜日の朝はあっという間に流れていく。世田谷にある林の自宅を出て車で数分走ると、東急大井町線「尾山台駅」のほど近くに、白い外壁の建物が見えてくる。AR−Ex尾山台整形外科ーーグループの中枢である。そもそも「AR-Ex」とは関節鏡視下手術−リハビリテーション−運動療法からアルファベットの頭文字を取ったもので、この医院はそれらすべてができる施設を備えている。
林はいつものようにクリニックのスタッフルームに入ると、手術着に袖を通した。そして足取りの軽快さはそのままに、消毒用アルコールの匂いに満ちた重たい扉の向こう側へと消えていった。
「いってきます」
大川はその背中を見送った。
林は50歳を超えた今でこそ、後進のドクター育成のために執刀数を減らしているが、すでに5000例以上の関節鏡視下手術をしてきた。当然のようにオペ室ではメスを持つ。ただ、林が握るとメスは何かを切断したり、突き通したりするためのものではなく、繋げるためのものなのだという印象になる。人との関係も、人の夢も断ち切らないのだ。
それが、他の医師とは隔絶したイメージの源泉なのだろうか。
そもそも大川や医療関係者がその不思議な力を目の当たりにしたのは、9年前に林が起こした、ある体操選手をめぐる奇跡によってだった。
#1「はみだしドクター」
#2「希望をつなぐメス」
#3「さらば、白い巨塔」
#4「何がしたいのか?」
#5「アレックスの夢」
創業社長物語「ゼロイチ」スマートエナジー大串卓矢編はこちらから!

Hidetoshi Hayashi
1964年神奈川県生まれ。日本医科大学大学院卒。2003年医療法人アレックスを設立。現在スポーツ整形外科メディカルグループの代表を務める。これまでの手術件数は5,000例を超え、読売巨人軍をはじめ、多くのプロアスリートの治療にも携わる。日本体育協会認定スポーツドクター 日本整形外科スポーツ医学会 日本臨床スポーツ学会評議委員 日本医科大学非常勤講師(スポーツ整形外科) ジャケット¥418,000、タートルネック¥135,300、チーフ¥16,500(すべてエルメネジルド ゼニア/ゼニアカスタマーサービス TEL:03−5114−5300)
AR-Ex Medical Group
国内最大級の整形外科専門クリニック・グループ。長野県に3クリニック、東京都に4クリニック、埼玉県に1クリニックの計8クリニックを展開。グループ名の「AR-Ex」は、Arthroscopy (関節鏡視下手術)、Rehabilitation(リハビリテーション)、Exercise (運動療法)の頭文字からとったもの。スポーツ外傷・関節障害を治療する上で、最も重要なこの3つの治療分野の専門スタッフがチームとなり、外来・入院・復帰まで完全サポートする。公式Instagram
Tadahira Suzuki
1977年生まれ。日刊スポーツ新聞社でプロ野球担当記者を経験した後、文藝春秋・Number編集部を経て2019年からフリーに。著書に『清原和博への告白 甲子園13本塁打の真実』。取材・構成担当書に『清原和博 告白』『薬物依存性』がある。’20年8月から週刊文春で連載していた『嫌われた監督〜落合博満は中日をどう変えたのか〜』が、単行本として刊行予定。
制作協力
POD Corporation
「人生に豊かさを。やりたい事、好きな事で成功を収め、社会に還元する」
東京・ロサンゼルス・ニューヨークをベースに社会的影響力の強いスポーツ、Performance & Arts、アントレプレナーの方々と共に、社会に必要とされる新たな価値創造を目指す会社。公式Instagram





































