創業社長の共通点とは、なにだろうか。七転び八起きの人生、生死をかけた壮絶なる体験、事業立ち上げの苦労……。それぞれに悲喜交々(ひきこもごも)のストーリーはあるのだが、必ず持ち合わせているのが、物事を0(ゼロ)から1(イチ)へと推進させた経験だろう。連載「ゼロイチ 創業社長物語」では、そのプロセスをノンフィクションライター鈴木忠平が独自目線でひも解く。二人目は国内最大級の整形外科グループ「AR-Ex(アレックス) Medical Group」を創設した林英俊。#1「はみだしドクター」
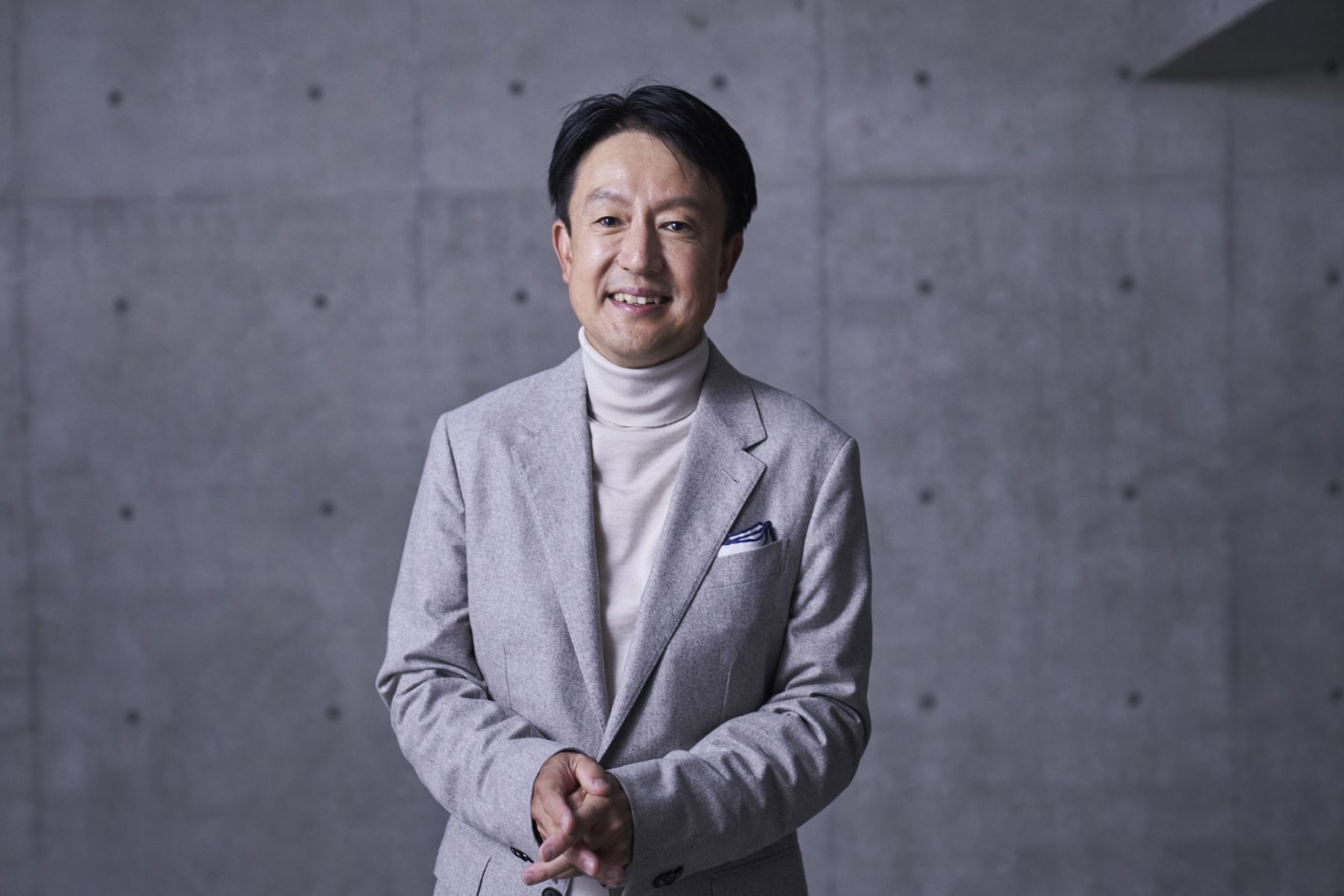
ある体操選手の悲劇
植松鉱治は将来を嘱望された体操選手だった。大学4年のインカレでは2つ年下の内村航平と優勝争いをして勝ったことがある。とりわけ鉄棒では世界トップレベルの力があることを、いくつもの大会で証明してきた。
だから、25歳で迎える2012年のロンドン五輪ではメダルを狙えると、本人も周囲も考えていた。
悲劇はそんなときに起こった。
ロンドン五輪まであと1年あまりとなった2011年4月のある日のことだった。植松は練習で通称「ルドルフ」という技に挑戦した。一直線の美しい伸身を保ったまま、宙返りとひねりを2回ずつ入れて着地しなければならない大技だった。
今日はあまり調子が良くないから、やめておこうか……。いや、オリンピックのためには今からやっておかなければ……。
そのわずかな迷いが、動きに狂いを生じさせた。ひねりが足りず、着地の瞬間にポンと右膝が外に飛び出したような感覚があった。植松は痛みのあまり、マットにうずくまった。
太腿と脛をつなぐ右膝の前十字靭帯が断裂していた。当時の医療では最低でも復帰までに半年は必要とされ、復帰してもパフォーマンスが戻るかどうかはわからないと言われる大怪我だった。
「ああ、切れちゃってるなあ……」
日本代表の選手を担当するナショナルトレーニングセンターの担当医は植松の膝を診断すると、そう言ってかぶりを振った。
ロンドン五輪の選考に関わる大会が5ヵ月後に迫っていた。それまでになんとしても復帰しなければならないーー。植松がそう訴えても、目の前の医師は苦笑いを浮かべるだけだった。植松はその様子を見て、事の深刻さを知った。日本中をまわってでも、5ヵ月で治してくれるドクターを探さなければならなかった。ただ、日を追うごとに、それがいかに困難なことかがわかってきた。焦りの裏に絶望が忍び寄っていた。
林英俊に出会ったのはそんなときだった。
所属するKONAMI体操部のトレーナーからの紹介だった。植松は関節鏡手術のスペシャリストだというその医師に、諦め半ばで会いにいった。
「植松くんはどうしたいの?」
どこか飄々とした細身の医師からは、まずそう訊かれた。
「5ヵ月で復帰したいんです」
すると、林はしばし考えてから、すぐそこにあるものを取りにいくような軽快さで、こう言った。
「よし、じゃあ、やってみようか? 頑張れる?」
植松は呆気にとられた。自分の膝はナショナルトレーニングセンターのドクターも首を横に振るほどの重傷ではないのか?
なぜ、この人はこんなに希望に満ちているのだろうか?
根拠はわからなかったが、林の顔を見ていると、オリンピックへの道に光が見えたような気がした。
手術はあっという間に終わった。少なくとも植松にはそう感じられた。だが、本当の闘いが始まったのは、それからだった。
手術の翌朝、まだ夜が明けきれないうちに、植松が入院している病室の扉が開いた。
そこに林が立っていた。
「膝はどうなっているかな?」
どうなっているも何も、昨日手術したばかりではないか。
植松がそう思って身を起こすと、林は靭帯をつなぎ合わせたばかりの膝に触れ、可動限界を確かめるようにぐいと動かした。激痛が走った。植松は思わず声をあげて、林を見た。すると、執刀医はまるで自分も同様の痛みを感じているかのような鬼気迫る表情をしていた。それを見て、植松はあらためて、5ヵ月で公式戦のマットに立つことが、どういうことなのかを悟った。
それからはリハビリとそれに伴う痛み、瘡蓋(かさぶた)を形成して癒着しようとする患部との戦いだった。1日1日、前に進んでいるのかどうかさえわからない。まるでマッチ箱で塔を建てるような日々だった。
林は検査で前進が見られているときは、「よく頑張っているね」と言ってくれた。その言葉が道標だった。心折れそうな自分を奮い立たせるため、リハビリをかねて富士山に登ったこともあった。
その末に、秋には故障してから初めての公式戦に出場することができた。植松の膝は遠心力と落下速度が加わった着地の衝撃にも耐えた。それはほとんど奇跡であった。
あとから聞いたことだが、林はその会場に足を運んでいて、植松の演技の瞬間には両手で顔を覆っていたという。
「だって、見てられないよ……」
患者の前をずんずん歩く
断裂から1年後、植松はロンドン五輪代表の座をかけた最終選考会のマットに立った。体操選手としての人生をかけた戦いだった。
もてる全てを出した結果は次点ーー。かつてメダルを期待されていた逸材は補欠メンバーとなった。おそらく、ロンドンのマットに上がることはないだろう。そう考えると、植松の目からは涙が溢れた。ただ、不思議と心はかつてないほどに清々しかった。生まれて初めて何かをやり遂げたという実感があった。
普通ならばそれでストーリーは終わりだ。だが、林はオリンピックを逃したあとも植松の側を離れなかった。それどころか、無意識に着地への恐怖心が拭い去れない植松に、こんな注文をつけたのだ。
「まだ、誰もやったことのない技をやってみたらどうか?」
鉄棒でほとんど例のない、大技の4連続に挑戦してみろというのだ。
患者の演技を直視できないドクターが、なぜそんなことを言うのか。植松にはわからなかった。
それからも結果が出ないことが続くと、こんなことを言われた。
「植松くん、メンタルが弱いんじゃないの?」
これには内心、反発を覚えた。どんな大舞台であっても、臆して実力が出せないという経験はなかったからだ。
「いや、心は弱くはないと思います」
「でも、結果が出ないというのは弱いんじゃない? メンタルトレーナーを探してみようよ」
植松は半信半疑のまま、林とともにその分野の第一人者を探した末に、ひとりの人物を京都へ尋ねることになった。
AR−Exグループのトップであり、KONAMI体操部と巨人軍のドクターでもある林はスケジュールの合間を縫って京都駅へやってきた。約束の時間に落ち合うと、植松の前をずんずん歩いていった。
この人はなんでこんなに歩くのが速いのだろう、と植松は思った。
まるで当人になり代わって、ひとりの体操選手が進むべき道を探しているかのようだった。植松はその後ろ姿を見ながら、かつてこういうドクターがいただろうかと、あらためて考えた。
植松が現役最後のマットに立ったのは、2015年9月の全日本シニア選手権だった。その鉄棒の演技で植松は4つの大技を連続で成功させ、着地を決めた。つまり最後の最後で林との約束を果たしたのだ。
会場を包んだどよめきと歓声のなかに、林の姿もあった。
「誰もやったことのない技をやってみたらどうか?」
なぜ林がそう言ったのか、植松はその意味がわかった。オリピックを失った自分にとっては、無謀とも思えるような技への挑戦が、いつしかトロフィーやメダルとは別の新しい目標になっていたのだ。
見ている人がワクワクするような、誰もやったことのない演技をすることーーそれを競技人生のゴールにすることができた。
引退した後、植松はアメリカへ渡った。
あの日、半信半疑で足を踏み入れたメンタルトレーナーの世界を第二の人生と決めた。
今、植松は異国の地で学びながら、こんなことを考えている。
いつか、折れそうになっている誰かの夢を繋げてあげたい。あの早歩きのドクターのようにーー。
#1「はみだしドクター」
#2「希望をつなぐメス」
#3「さらば、白い巨塔」
#4「何がしたいのか?」
#5「アレックスの夢」
創業社長物語「ゼロイチ」スマートエナジー大串卓矢編はこちらから!

Hidetoshi Hayashi
1964年神奈川県生まれ。日本医科大学大学院卒。2003年医療法人アレックスを設立。現在スポーツ整形外科メディカルグループの代表を務める。これまでの手術件数は5,000例を超え、読売巨人軍をはじめ、多くのプロアスリートの治療にも携わる。日本体育協会認定スポーツドクター 日本整形外科スポーツ医学会 日本臨床スポーツ学会評議委員 日本医科大学非常勤講師(スポーツ整形外科) ジャケット¥418,000、タートルネック¥135,300、チーフ¥16,500(すべてエルメネジルド ゼニア/ゼニアカスタマーサービス TEL:03−5114−5300)
AR-Ex Medical Group
国内最大級の整形外科専門クリニック・グループ。長野県に3クリニック、東京都に4クリニック、埼玉県に1クリニックの計8クリニックを展開。グループ名の「AR-Ex」は、Arthroscopy (関節鏡視下手術)、Rehabilitation(リハビリテーション)、Exercise (運動療法)の頭文字からとったもの。スポーツ外傷・関節障害を治療する上で、最も重要なこの3つの治療分野の専門スタッフがチームとなり、外来・入院・復帰まで完全サポートする。公式Instagram
Tadahira Suzuki
1977年生まれ。日刊スポーツ新聞社でプロ野球担当記者を経験した後、文藝春秋・Number編集部を経て2019年からフリーに。著書に『清原和博への告白 甲子園13本塁打の真実』。取材・構成担当書に『清原和博 告白』『薬物依存性』がある。’20年8月から週刊文春で連載していた『嫌われた監督〜落合博満は中日をどう変えたのか〜』が、単行本として刊行予定。
制作協力
POD Corporation
「人生に豊かさを。やりたい事、好きな事で成功を収め、社会に還元する」
東京・ロサンゼルス・ニューヨークをベースに社会的影響力の強いスポーツ、Performance & Arts、アントレプレナーの方々と共に、社会に必要とされる新たな価値創造を目指す会社。公式Instagram





































