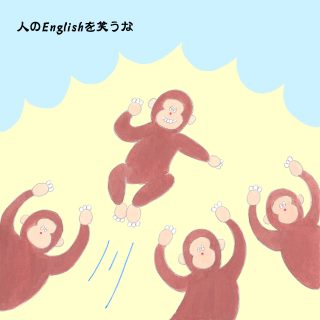「年をとったら記憶力は落ちる…」と言われる一方で、世の中には若い頃と同じ記憶力を保つスーパーエイジャーも注目されている。「物忘れの正体」とは何なのか? うまくいく人とそうでない人を研究し、4万人以上に脳科学的ノウハウを講演してきた脳科学者・西剛志氏が考察する。

「あれ? スマホどこだっけ!?」、「あの人の名前が思い出せない!」「いま何しようとしてたっけ?」――。
誰もが経験したことのある、日常の“ちょっとした物忘れ”。
年を重ねる毎にこうした場面が増え、「記憶力が落ちたのかな」と不安になる方も多いのではないでしょうか。ところが、脳科学の研究を紐解くと、驚くべき事実が見えてきます。
実は、記憶力そのものは年齢ではほとんど低下しないことがわかってきているのです。
「年を取ると記憶力が落ちる」は思い込みだった!
アメリカ・タフツ大学の研究では、18〜22歳の若者と60〜74歳の年配者に、単語記憶のテストを行いました。
「これは普通の心理実験です」と伝えた場合、両者の正答率はほぼ同じでした。
しかし、「これは記憶力テストです。通常、年配の方の成績が下がります」と伝えたところ、年配者の正答率だけが約30%も下がってしまったのです(*1)。
つまり、「歳をとると物覚えが悪くなる」というのは、脳の問題ではなく“思い込み”による影響が大きいことを意味しています。
実際に落ちているのは、記憶力よりも「集中力」や「覚えようとする意欲」だったのです。
覚えられないのは「見ていない」から!?――“0.4秒ルール”で記憶が劇的に変わる
なぜ、こんなことが起きるのでしょうか?
私たちは、1日に数えきれないほどの情報を目にしています。しかし、記憶に残るものはほんの一部。その違いを生むのは、「どのくらい見ているか」です。
ある実験では、画像を一瞬だけ見せて、どのくらい覚えているかを調べました。
結果、0.17秒以下しか見なかった場合は、1〜2分後に半分以上を「見た記憶がない」と回答しました。一方で、0.3〜0.4秒以上見た場合には、長期記憶と結びつき、忘れにくくなったのです(*2)。
つまり、物忘れとは「見ていない」ことから起こる可能性があります。
子どもの頃は見るもの全てが新しく、違う角度から何度も見たり、自然と注意を向ける時間が長くなります。
ところが、大人になると、「ああ、これね」と感覚や経験で処理するため、視線を向ける時間がどうしても少なくなってしまうのです。
脳の集中力のピークは平均43歳と言われています(*3)。特に40代から50代以降の人は注意が必要です。脳に慣れが生じやすく、部下の管理や上司としての責任感、家庭や子どもの進学に関わることなど、1日の中でさらされる情報も若いときよりも多くなり、必要以上に注意力が下がっている可能性があるからです。
鍵の置き場所、駐車場で車をどこに停めたかを忘れたくないなら、たった0.4秒、しっかりと見つめるだけで、記憶が格段に定着しやすくなる効果が期待できます。
「同じ場所」にいる人ほど、記憶力は落ちる
もう一つ、物忘れを防ぐ方法として注目されているのが「場所を変えること」です。
アメリカ・ミシガン大学の研究では、単語暗記を「同じ部屋」で行ったグループと、「途中で場所を変えたグループ」とを比較しました。
すると、場所を変えたグループの方が覚えた単語の数が50%も多くなったのです(*4)。
この違いを生むのが、脳の「場所細胞」です。
場所細胞は、空間を移動することで活性化し、記憶を司る海馬の歯状回を刺激します(*5)。
仕事で行き詰まったとき、カフェに行ったり、別の場所で人と話すと気分が変わることがありますが、これは気のせいではなく、場所が変わるだけで脳が活性化するからです。
幸福度が高く、海馬などが発達している人ほど、1日の移動範囲が広いこともわかっています(*6)。また、新しい刺激が好きな人は知能が落ちにくい傾向もあります(*7)。
毎日同じ人と話す、同じ店で同じメニューを注文する、同じ道を歩く――。
もしこんな“日々のルーチン”が多い人は、注意が必要です。そうした何気ない小さな習慣が、脳を老化させている可能性があるのです。
“忘れない脳”をつくる3つの習慣
物忘れを防ぐ方法は、とてもシンプルです。
- 移動する —— 場所を変える頻度を高めて、脳を刺激する
- 見つめる —— 覚えたいものを0.4秒以上しっかり見る
- いつもと違う行動をする —— 同じルーチンを避け、新しい刺激を取り入れる
脳は、新しい刺激を受け取るたびに活性化します。
私がサポートする経営者やエグゼクティブも、1日の移動が多く、新しい情報が好きな人ほど、スケジュールを時間単位で覚えていたりして、驚くことがあります。
同じことを繰り返すよりも、“いつもと少しだけ違うことをする”小さな勇気。
このような小さな習慣が、脳をいつまでも若々しく保つ秘訣になっていきます。
「物忘れ」は、脳が生きている証拠
そして最後に、物忘れは決して「悪いこと」ではありません。
忘れることは、脳が情報を整理している証拠です。脳は常に、不要な情報を捨てて、必要な情報を残しています。つまり、忘れるからこそ、次の新しいことを覚えられるのです。
「最近、物忘れが増えたな」と感じたときこそ、新しい場所に出かけ、目の前の景色を0.4秒だけ見つめてみてください。その瞬間、あなたの脳は更に若返り、見える世界も変わっていくでしょう。

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。武蔵野学院大学スペシャルアカデミックフェロー。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。2002年に博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子供まで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて4万人以上に講演会を提供。『世界仰天ニュース』『モーニングショー』『カズレーザーと学ぶ。』などをはじめメディア出演も多数。TBS Podcast「脳科学、脳LIFE」レギュラー。著書に20万部のベストセラーとなった『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』、『1万人の才能を引き出してきた脳科学者が教える 「やりたいこと」の見つけ方』『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』など海外を含めて累計43万部突破。最新刊は『脳科学でわかった仕事のストレスをなくす本』(2025年10月30日発売)。
<参考文献>
(*1)Thomas AK, Dubois SJ. Reducing the burden of stereotype threat eliminates age differences in memory distortion. Psychol Sci. 2011 Dec;22(12):1515-7
(*2)Potter MC, Staub A, Rado J, O'Connor DH. Recognition memory for briefly presented pictures: the time course of rapid forgetting. J Exp Psychol Hum Percept Perform. 2002 Oct;28(5):1163-75
(*3)Fortenbaugh FC, DeGutis J, Germine L, Wilmer JB, Grosso M, Russo K, Esterman M. Sustained Attention Across the Life Span in a Sample of 10,000: Dissociating Ability and Strategy. Psychol Sci. 2015 Sep;26(9):1497-510.
(*4)Steven, M. Smith, Arthur Glenberg and Robert, A. Bjork, “Environmental context and human memory” Memory & Cognition, Vol.6(4), p.342-53, 1978
(*5)Tuncdemir SN, Grosmark AD, Turi GF, Shank A, Bowler JC, Ordek G, Losonczy A, Hen R, Lacefield CO. Parallel processing of sensory cue and spatial information in the dentate gyrus. Cell Rep. 2022 Jan 18;38(3):110257
(*6)Heller AS, Shi TC, Ezie CEC, Reneau TR, Baez LM, Gibbons CJ, Hartley CA. Association between real-world experiential diversity and positive affect relates to hippocampal-striatal functional connectivity. Nat Neurosci. 2020 Jul;23(7):800-804
(*7)西田 裕紀子, 他、「中高年者の開放性が知能の経時変化に及ぼす影響:6年間の縦断的検討」発達心理学研究、2012, 23(3),p.276-86