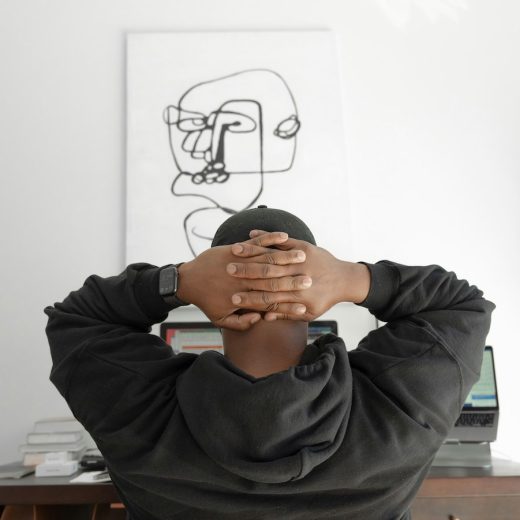伝えたはずなのに、伝わっていない……。言葉で伝えても、なかなか伝わらない。いくら言葉を尽くしても“うまく伝わらない”ことは、ビジネスや男女関係、子育てでもよくあること。うまくいく人とそうでない人の違いを研究する42万部のベストセラー著者である脳科学者・西剛志が、その秘密を伝える。

伝えるためには言語化だけでは限界がある
商品のよさを伝えたい、このシステムの長所を上司に伝えたい、この人の素晴らしさを伝えたい。でも、どんなに伝えても“伝わらなかった”経験はないでしょうか?
最近、言語化という言葉が流行っていますが、米国デンバー大学の研究でも、言語化には限界があることがわかってきています(*1)。
言葉だけでは伝わらない仕組みがあるということです。
好感度が伝わることに影響する!?
伝えても伝わらない理由は、少なくとも20以上ありますが、その1つが“好感度の低さ”です。
人は好感度が低いものを、受け取ろうとしません。
好きでないものをあげると言われても、受け取りたくはありませんよね。
つまり、伝えたいものの好感度が相手にとって低いからと言えます。
それでは、相手の好感度を上げるためにどうすればよいのか?
普通に思いつくのは、相手にそのメッセージのメリットを伝えることです。しかも、メリットは1つよりも2つ、2つよりも3つ、3つよりも4つ伝えたほうがより効果があります(*2)。これは言語化で伝える方法です。
そして、もう1つの大切な方法が、接触頻度。認知科学の世界では有名な「単純接触の法則」を使うことです。
ある刺激に触れれば触れるほど、その対象を好きになっていく法則で、1960年代にザイアンス博士によって発表され、社会心理学の分野で研究されてきました(*3)。
たとえば、最初は興味がなかったとしても、CMを繰り返し見ているうちに、その商品が気になったり、好きになっていくということがありますが、これは単純接触の法則です。
好感度が高まる回数があった
しかし、何でもかんでも、接触回数が増えたからと言って好きになる訳ではありません。 毎回会うたびに怒られていたら、その人を好きにはなりません。脳は痛みを感じるものに何度も接していると、より嫌いになってしまいます。
一方で、ニュートラルなものであれば、何度も見せているうちに好きになる効果があると言われています。1回、9回、 27回、243回、同じ漢字をコマ送りで見せると、 27回までは好感度が上がったそうです(*4)。 ただし、回数が多すぎるとマイナス効果が出てきて、243回で好感度が減少したそうです。
また他の研究では、新しい衣服の写真をサブリミナルで1回、10 回、20回、30回、40回見せた結果、20回見せたときに最も親しみやすさが上がったが、 30回以降は下がってしまうという結果も出ています(*5)。
1回以上のコンタクトがあると、回数が増えるほど認知は変わっていきます。でも10回を超えると対象物への好意は横ばいか、下がるという報告もあります(*6)。 30回までは増えて、それ以降は下がるという報告もあります(*7)。 このあたりを総合すると、1回で認知は変わり、 10回〜30回で好意は下がり始めるということです。単純接触の回数が多ければ多いほどいいということではないわけです。
意外と知られていない単純接触の法則の真実
単純接触に関してはいろいろな調査結果が出ています。
たとえば、同じ顔写真を21回見せるよりも、7つの表情を3回ずつ見せたほうが、 その対象を好きになりやすいという調査結果もあります(*8,9)。
つまり単純接触効果は、「親近性(慣れ親しむ) × 新規性」の掛け算で、より効果が大きくなるのです。
これは、商品であれば、同じメリットを何度も伝えるよりも、いつもと違った側面やメリットを伝える方が、より相手に伝わりやすくなるということです。 CMでも同じものを繰り返し流すよりは、商品は同じでもレパートリーがあると、その商品やサービスをより好きになりやすくなります。
また直接、その商品を見せるのではなく、似たものを見せることで、実際の商品を見せたときに好感度が上がる効果があることも知られています。
たとえば、野球の試合を一緒に見に行きたいけど、相手が野球に興味がなかったとします。 そこで、大谷選手のプレー映像を相手に何度も見せると、野球に対する親近感が上がっていきます。すると、大谷選手の試合ではなくても、日本の野球を見に行きたいとなる可能性があるわけです。 単純接触効果をうまく活用することで、伝わる状態を生み出せるのです。
これまでの研究で、ビジネスでも子育てや夫婦関係でもうまくいく人たちは、このような言葉を超えた、伝えるための48種類のコツを使っていることがわかってきました。
私自身も以前はコミュニケーションが苦手なタイプでしたが、こうしたうまくいく人たちの伝えるコツを知っていくうちに、今では1000名を超える講演会でも自信をもって自然に伝えられるようになりました。
コミュニケーションの質は幸福度にも比例します。成長していくことで、幸福度はさらに上がります。皆さんも、ぜひ積極的に“伝える技術”を磨いてみてください。

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。武蔵野学院大学スペシャルアカデミックフェロー。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。2002年に博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子供まで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて3万人以上に講演会を提供。『世界仰天ニュース』『モーニングショー』『カズレーザーと学ぶ。』などをはじめメディア出演も多数。TBS Podcast「脳科学、脳LIFE」レギュラー。著書に20万部のベストセラーとなった『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』、『1万人の才能を引き出してきた脳科学者が教える 「やりたいこと」の見つけ方』など海外を含めて累計42万部突破。最新刊『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』も好評発売中。
<参考文献>
*1 Howieson & Priddis (2015).Howieson J, Priddis L. A mentalizing-based approach to family mediation: harnessing our fundamental capacity to resolve conflict and building an evidence-based practice for the field. Family Court Review. 2015;53(1):79–95/Kidder (2017).Kidder DL. BABO negotiating: enhancing students’ perspective-taking skills. Negotiation Journal. 2017;33(3):255–267
*2 西剛志著『結局、どうしたら伝わるのか?脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』アスコム、2025年2月
*3Zajonc, R. B. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 35(2), 151–175. /Zajonc, R. B. (2001). Mere exposure: A gateway to the subliminal. Current Directions in Psychological Science, 10(6), 224–228.
*4 Osada, M. & Kobayashi, S., “Effects of subliminal mere exposure by means of increasing the number of exposure times -A discussion using dress as a stimulus –“, Japanese Journal of Sensory Evaluation, 2007, Vol.11(2), p.89-98/ Zajonc RB, Crandall R, Kail RV Jr. Effect of extreme exposure frequencies on different affective ratings of stimuli. Percept Mot Skills. 1974 Apr;38(2):667-78.
*5 Bornstein, R. F., & D'Agostino, P. R. (1992). Stimulus recognition and the mere exposure effect. Journal of Personality and Social Psychology, 63(4), 545–552・Newell, B. R., Lagnado, D. A., & Shanks, D. R. (2007). Straight choices: The psychology of decision making. Psychology Press.
*6 Stang, D. J. (1974). Methodological factors in mere exposure research. Psychological Bulletin, 81(12), 1014–1025./ Szpunar KK, Schellenberg EG, Pliner P. Liking and memory for musical stimuli as a function of exposure. J Exp Psychol Learn Mem Cogn. 2004 Mar;30(2):370-81./
*7 Bornstein, R. F., Kale, A. R., & Cornell, K. R. (1990). Boredom as a limiting condition on the mere exposure effect. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), 791–800.
*8 Zebrowitz LA, White B, Wieneke K. Mere Exposure and Racial Prejudice: Exposure to Other-Race Faces Increases Liking for Strangers of That Race. Soc Cogn. 2008;26(3):259-275.
*9 Gordon, P. C., & Holyoak, K. J. (1983). Implicit learning and generalization of the "mere exposure" effect. Journal of Personality and Social Psychology, 45(3), 492–500