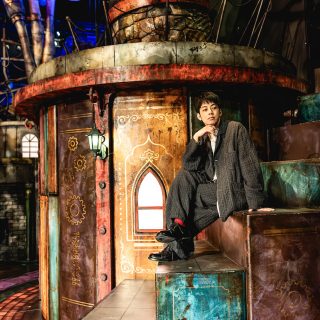クルマ生活を豊かにしてくれるセカンドカーを考える不定期企画。今回は、はじめての電気自動車をパートナーとシェアすることを提案したい。

MINIファミリーの電気自動車専用モデル、登場!
「三歩進んで二歩下がる」というペースかもしれないけれど、長い目で見ればクルマが電動車両に移行するのは間違いない。わが愛車をいつBEV(バッテリー式電気自動車)に切り替えるのか、そのタイミングを図っている人も多いかもしれない。
ここはまず、パートナーが普段使いしているわが家のセカンドカーをBEVに切り替えてみるのはどうだろう。“はじめてのBEV”の有力候補として推したいのが、MINIファミリーに新たに加わったBEV専用モデル、MINIエースマンだ。SUV風味のMINIカントリーマンと、3ドア/5ドアハッチバックのMINIクーパーはエンジン車とBEVの両方をラインアップするけれど、MINIエースマンはBEVだけの設定となる。
2024年に発表されたこのMINIエースマン、2025年の年明けよりいよいよ本格的なデリバリーが始まった。早速、試乗に連れ出してみた。

MINIエースマンを薦める理由は、そのデザインやドライブフィールで、オーナーを喜ばせたい、移動を楽しんでもらいたいという意思が明確に伝わってくることだ。ただの移動の道具ではなく、所有する喜びがある。
まず外観は、長い時間をかけて培ってきたMINIらしさと、新しさが見事に融合している。それを象徴しているのが新デザインのLEDヘッドランプと八角形のフロントグリルの組み合わせで、ひと目でMINIだとわかるのに、いままでに見たことのない新しいクルマだという印象を与えることにも成功している。

インテリアも同様。直径240mmという円形有機ELセンター・ディスプレイやドライバー正面のヘッドアップディスプレイで新しいインターフェイスを提案しつつ、センター・ディスプレイの下にはクラシックMINIを思わせるスイッチ類を残して、MINIらしさを表現している。
新しさと古典的なクルマの楽しみ方が共存している
「Hey MINI」と呼びかけてインテリジェント・パーソナル・アシスタントを起動、音声会話でエアコンの温度や目的地を設定して走り出す。ちなみにAI技術を活用することで、より普通の会話に近い形で音声操作ができるようになっている。
走り出してまず感じるのは、全長4メートルをわずかに上回るコンパクトなサイズが扱いやすいこと。パートナーが買い物やジム通いをするのにうってつけのサイズ感で、全高も低いから機械式駐車場への入庫もまるで問題がない。
静かで、街中の速度から高速道路まで滑らかに加速するのはBEVの特長。MINIエースマンで興味深いのは、MINIエクスペリエンス・モードを切り替えることで、車両のキャラクターとインテリアの雰囲気がガラッと変わること。「エフィシェント」モードを選べば航続距離の長い穏やかなキャラになり、「ゴー・カート」モードに切り替えるとメーターがレーシィな雰囲気になるのと同時に、アクセル操作に対するレスポンスが鋭くなる。
つまり、静かに穏やかに走りたいという人も、ちょっとヤンチャに走りたいという人のどちらも満足できるのだ。これも、パートナーとシェアするセカンドカーに推したい大きな理由だ。

MINIエースマンをセカンドカーにするにあたって、問題があるとすればやはり充電だろう。ただし、買い物や送り迎えをメインにするセカンドカー的な使い方であれば、無事にこなせそうだ。一般社団法人日本自動車工業会の統計によれば、乗用車の1日あたりの平均走行距離は約22キロ。つまり1週間で15Oキロ程度だから、一充電あたりの走行距離を300km以上確保しているMINIエースマンの場合、週に一度、急速充電器に30分ほどつなげばOKということになる。
スマホにダウンロードした充電アプリを見ると、区役所やショッピングモールなど、意外と近場に急速充電器が設置されていることがわかる。買い物や映画鑑賞、あるいはジムでのワークアウトなど、週に一度の充電を生活に組み込むことができれば、この問題はクリアできそうだ。
MINIエースマンは、新しい時代の電気自動車だと感じるいっぽうで、ペット的な愛らしいキャラクターと、きびきびと走るファン・トゥ・ドライブというコンパクトカーの古典的な魅力も備わっている。このクルマをセカンドカーとして迎え入れれば、それぞれの家庭のアイドルになりそうな予感がする。

全長×全幅×全高:4080×1755×1515mm
ホイールベース:2605mm
モーター最高出力:184ps/5000rpm
モーター最大トルク:290Nm/1000〜4000rpm
一充電走行距離(WLTCモード):327km
価格:506万8000円〜(税込)
問い合わせ
MINIカスタマー・インタラクション・センター TEL:0120-3298-14
サトータケシ/Takeshi Sato
1966年生まれ。自動車文化誌『NAVI』で副編集長を務めた後に独立。現在はフリーランスのライター、編集者として活動している。