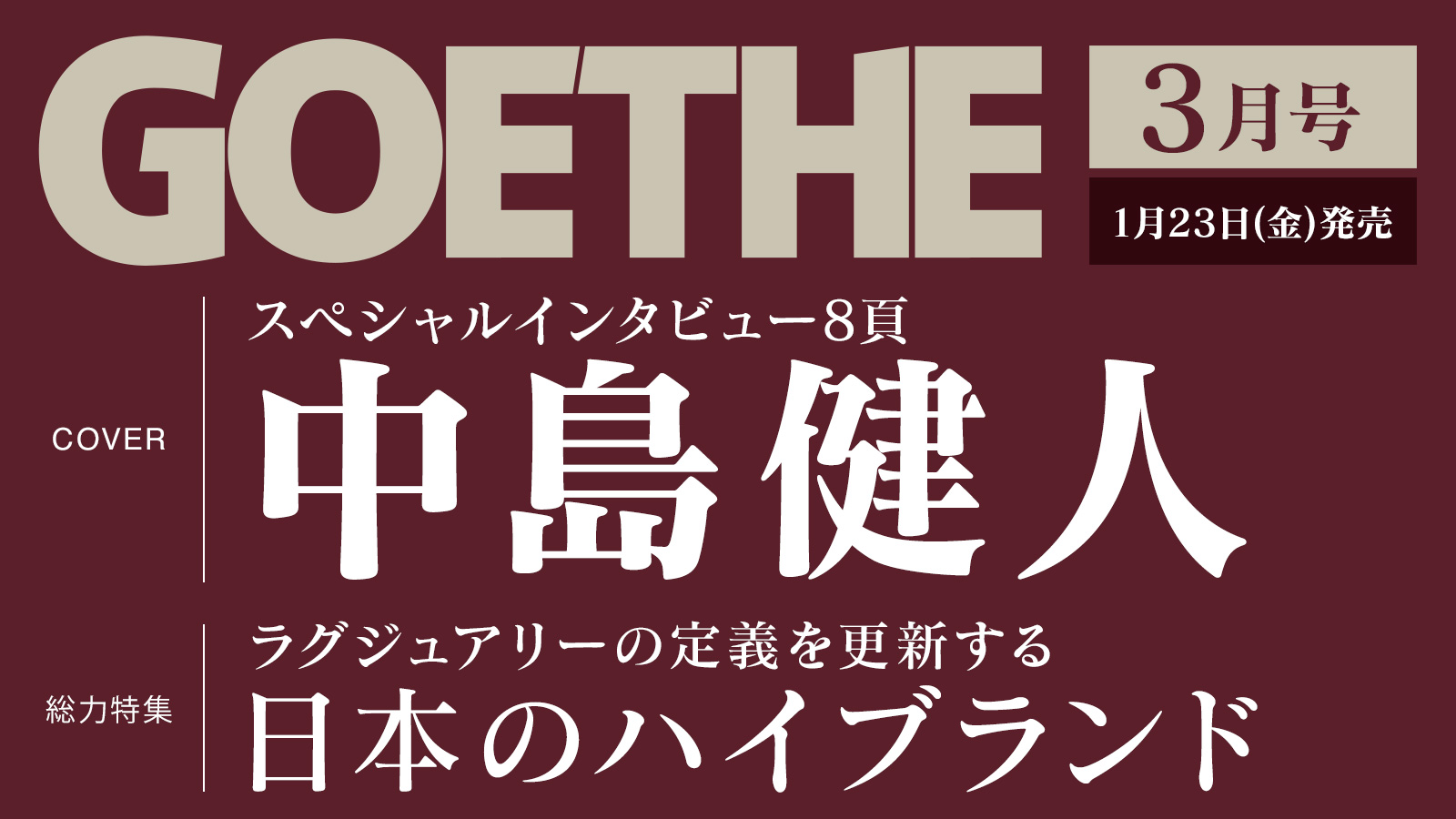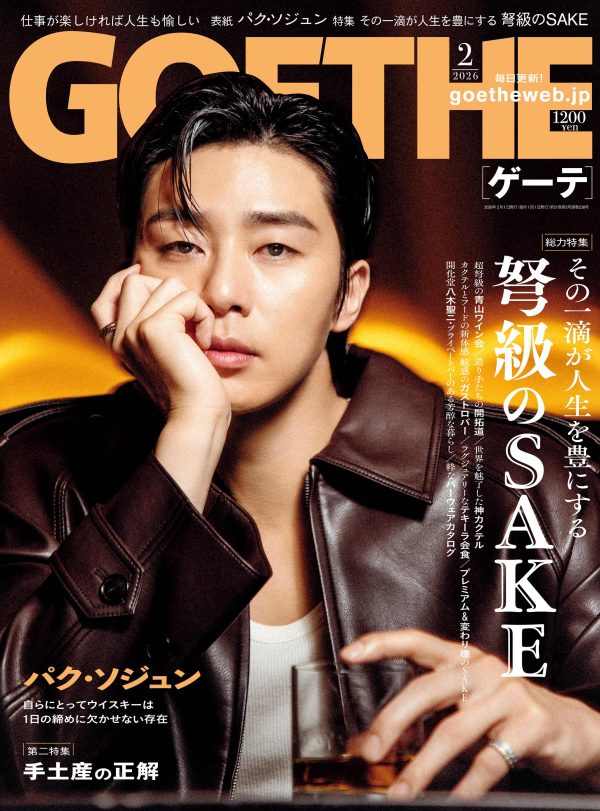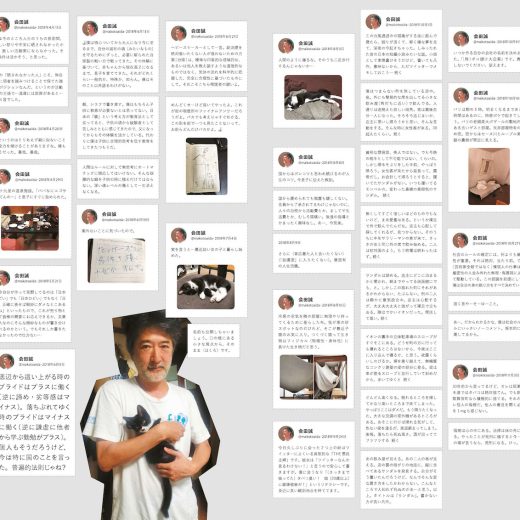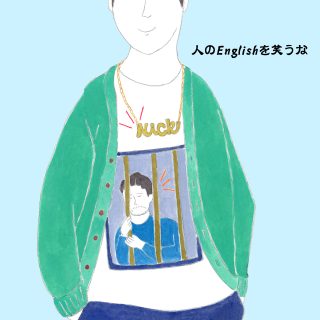「工芸」を主軸にした芸術祭が今年も開催されている。「GO FOR KOGEI 2025」。北陸のものづくり地域を舞台に展開されるが、2025年は岩瀬エリア(富山県富山市)と東山エリア(石川県金沢市)。テーマは「工芸的なるもの」だ。その中からいくつか作品を見ていこう。

工芸とは社会の美意識や様式に基づいたもの
芸術祭は各地にいろいろあるのだが、「GO FOR KOGEI」は「工芸」を前面に押し出している点が特徴的であり、特別である。工芸と現代アートが交歓し、伝統に寄り添いつつ、時代の気分を伝えている点で注目しておかなければいけない芸術祭なのだ。
2025年のテーマ「工芸的なるもの」とはなにか。これは民藝運動の主唱者として知られる柳宗悦(1889-1961)の論考「工芸的なるもの」(『工藝』第8号[1931年]所載)から引いた言葉だそうである。そこでは柳は伝統的な工法や職人的な仕事が生み出す美的器物に限らず、たとえば、車内アナウンスの抑揚や理髪師の鋏さばきを「工芸的なやり方」だと記し、人の行為あるいは態度にさえ、工芸性を見出した。
柳宗悦は、父は軍人出身の貴族院議員、本人は学習院で優秀な成績を収め、東京帝国大学文科大学哲学科で心理学を学び、のちに東洋大学の教授を務めるという超エリートなのだが、民衆の暮らしの中から生まれた美の紹介者となっていったのである。
そんな柳にとって、工芸とは、個人の自由な表現というよりも、社会全体で共有される美意識や様式に基づいたものであり、そこに美や価値が宿るものであった。有形無形を問わず、ものごとを「工芸的」と捉えることができるならば、「工芸」は今日の我々が想定、イメージする以上に社会とつながり、広がりをもったものとして立ち現れることになるだろう。
以上はアーティスティックディレクターの秋元雄史氏による提唱だ。彼は「GO FOR KOGEI」立ち上げ以来、総合監修・キュレーターを務めてきた。秋元氏は東京藝術大学名誉教授、金沢21世紀美術館特任館長。1991年から直島のアートプロジェクトに携わった。同地の地中美術館館長、金沢21世紀美術館館長、東京藝術大学大学美術館館長・教授、練馬区美術館館長などを歴任。
トップの画像《⽊桶と茅葺き屋根の茶室》。桶でできている茶室。作者は中川周士(1968年生まれ)。重要無形文化財保持者(いわゆる人間国宝)の父・清司に師事し、室町時代から続く伝統的な桶づくりを中心に、手作りの木製品を制作している。日本では木桶は産湯に使う桶から、棺桶まで、人の一生に寄り添うものだった。ビニル、プラスティックなど石油化学製品にとって代わられたが、ここで茶室の出現だ。短時間で設置、解体ができる。桶の茶室に茅葺きの屋根をつけたのは相良育弥(1980年生まれ)。伝統的な民家や文化財の屋根葺きから現代的な内装や装飾まで手がける。かつて、ヒップホップのDJだったりもした異色の経歴の持ち主。昨年「LOEWE Craft Prize 2024」でファイナリストにも選出されている。

壁に掛けられた布は海岸に漂着したプラスチック製の魚網をほどき、それを織り直し、繊細なタピストリーとして再生させたもの。アリ・バユアジ(1975年生まれ)はインドネシア出身。土木工学を学び、技師を経て、モントリオールのコンコルディア大学で美術を学んだ。一連の作品は、バリ島が観光に依存しない持続可能な経済や資源の活用のあり方を模索・提示している。

上出惠悟は1981年、石川県生まれ。1879年創業の九谷焼窯元・上出長右衛門窯の後継者として、職人と協働しながら伝統の枠に囚われないユーモラスな発想で九谷焼に取り組んでいる。東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻を卒業しており、美術作家・画家としても精力的に活動し、油画に加え、水墨画や瓷板画(じばんが:磁器に絵付けをし焼成する)、磁土を用いた彫刻的作品などにも取り組んでいる。

カラフルでポップな色彩を用いつつ、伝統的な技法である「梅花皮」や「石爆」「点滴」などを過剰に施す陶芸で知られる桑田卓郎は1981年広島県生まれ。「GO FOR KOGEI」には3回目の参加。今回、「酒蕎麦くちいわ」では、蕎麦のフルコースを桑田の作品で通して食するメニューを展開している。
また、陶器ではなく、ポリエチレンという素材を使い、大きな作品も手がけた。

坂本森海(さかもと かい)は1997年、長崎県生まれ。陶芸の作家ではあるが、制作から使用に至る「陶芸」のプロセスそのものに着目し、それを作品化する試みを展開している。土を掘り出し、成型し、自作の土窯で焼成する。そのプロセスを映像作品に収めている。作り上げた七輪でバーベキューを振る舞ってくれた。

寺澤季恵は1997年、静岡県生まれ。主に吹きガラスの技法を用い、溶解したガラスが自身の呼吸によって膨らむ様に生命力を見出し、手の内で蠢くマテリアルに寄り添いながら造形を行なっている。熟した果実のような、あるいは生命の臓器のようなその造形は生命への賞賛なのかもしれない。

松本勇⾺ は1977年群馬県生まれ。新潟で開催される「大地の芸術祭」に2000年からサポーターとして関わる中で藁による彫刻と出会った。作品制作で用いる藁は穀物の副産物だ。米や麦といった穀物は、人類の生存を支えてきたが、その副産物の藁もかつては燃料や飼料、また履物や建材などとして用いられ、生活に欠かせないものであった。そうした素材で象ることでその彫刻は、人類の農耕文化そのものを象徴している。基本的に展示場所の地域住民との協働によって制作される。

吉積彩乃は1991年、愛知県出身。金型を用いた吹きガラスを軸に、ガラスによる絵画的表現を探求する作家。矩形に整形されたガラスを「三次元のキャンバス」と捉え、色ガラスの重層性やエナメルなどによる直接的な描画で構成していく。立体であること、透明であること、有機的でもあり、中空があり内と外がある。独自の色彩表現を展開し、既存の工芸や絵画の概念を軽やかに飛び越えている。
GO FOR KOGEI 2025
テーマ:工芸的なるもの
会期:2025 年9 月13 日(土)〜10 月19 日(日)
休場日:水曜
時間:10:00〜16:30(最終入場16:00)
会場:富山県富山市(岩瀬エリア)、石川県金沢市(東山エリア)
料金:一般 2,500円、学生(大学生・専門学生)2,000円
Yoshio Suzuki
編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。