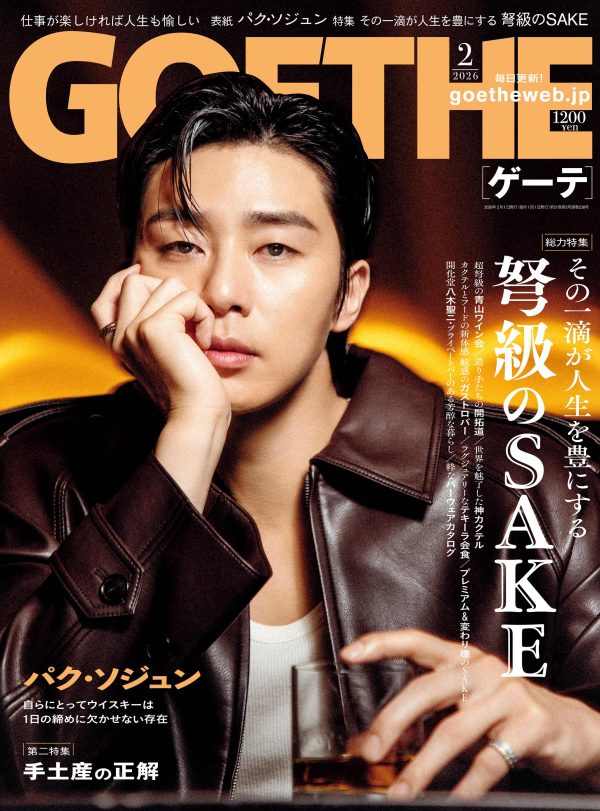菊地翔豊氏が保育園施設を立ち上げたのは、2014年、19歳の時だった。保育士どころか社会経験がない若者が、なぜ保育業界に乗り込んだのか。その経緯について話を聞く。2回目。

日本の教育に疑問を持ち、高校から海外へ
子どもの主体性を伸ばす「探究型保育」を掲げ、創業から10年にして、東京・埼玉・神奈川で12の保育園と2つの児童発達支援施設を運営するまでに急成長しているエデュリー。保育園としては珍しく、SNSを利用してユニークな活動を発信するなど、若き経営者ならではの取り組みも注目されている。
そもそも菊地翔豊氏は、なぜ19歳で保育事業を立ち上げようと思ったのか。きっかけとなったのは、ニュージーランドでの高校留学で出会ったアクティブラーニングだった。
「我ながら、僕は変わった子どもでした。皆と一緒に決められたことを決められたとおりにやるというのが苦手というか嫌いで、日本の保育とか教育にはまったく合わなかったんですよね。ランドセルを背負いたくなかったので、『壊れたから』と言い訳してリュックで学校に行ってたこともありました。
幼稚園は、入園してすぐに行かなくなり、2歳下の妹が幼稚園に入るからというので同じ園に1年間通っただけですし、ひきこもっていたわけではないんですが、中学もあまり通っていなくて柔道だけしていました(苦笑)。高校は1年で退学していますしね」
日本の学校はおもしろくない。そう思った菊地氏は、留学経験がある友人の勧めもあり、海外の高校に進学を決意。予算や環境などを考慮した結果、ニュージーランドへと旅立つ。3ヵ月間語学学校に通った後に入学したのは、現地ではごく一般的な高校だったが、そこで行われていたのは、学生それぞれが自分の興味関心に基づいて学びを深める教育だった。

1994年東京都生まれ。16歳でニュージーランドに留学し、現地で高校を卒業。帰国後の2014年、エデュリーの前身となる「KIDS ONE」を設立し、2016年に江戸川区にて「First step Ⅰ」を開園。2019年、社名をEduleadに、2022年エデュリーに変更。現在は東京・埼玉・神奈川で14園を経営している(グループ全体)。2015年、慶応義塾大学総合政策学部に入学。著書に『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』がある。
待機児童解消のための施策が追い風に
個々の潜在能力を伸ばすのは、日本の一斉型、画一的な教育ではなく、主体性を尊重した教育なのではないか。その想いを強めた菊地氏は、帰国後、教育事業での起業を志す。もっとも社会経験ゼロの青年が、幼少期から青年までの大規模な学校を創立するのは現実的ではない。そこで、ターゲットを“保育”に絞った。
「首都圏を中心に待機児童が社会問題化していた時期で、この解決に貢献したいという想いもありました。それに、資金力がない自分にとって、認可外であれば小規模で始められるという点も魅力でしたね。企業内保育所も増えていたので、その運営を受託する形でスタートすれば、大きな資本がなくても始められるのでは。我ながら良いアイデアだと思ったんですが、現実はそう甘くありませんでした(苦笑)」
社内に保育所を有する企業を訪ねて熱い想いをぶつけたものの、保育事業経験ゼロの19歳の若者に運営を任せるところは皆無。10数社回ったところで、「まずは自分で保育園を立ち上げ、実績をつくるしかない」と、菊地氏は腹をくくった。そして2015年、埼玉県川口市に開園のハードルが低い認可外保育園をオープンする(現在運営している施設はすべて認可保育園)。
「両親に連帯保証人になってもらって地元の銀行から1000万円を借り、居ぬき物件で小さな園を開きました。母の知人で保育士の方に園長を務めてもらい、保育者も伝手をたどって集めるなど、手探りでのスタートで。開園当時は園児3人程度で3ヵ月間は赤字でしたが、駅から近かったからか、徐々に園児数が増え、最終的には10数人に。開園1年目で黒字に転換できました」
「探究」というキーワードとの出会い
2015年といえば、当時の安倍政権が「子ども・子育て支援新制度」を打ち出し、運営事業者への補助金をアップするなど、待機児童解消に本腰を入れ始めた時期だ。これが、菊地氏にとって”追い風“となり、2016年に東京都江戸川区に、2017年には埼玉県川口市に同社初となる認可保育園を開設し、神奈川県藤沢市の病院内保育園の運営も受託するなど、事業は順調に拡大していった。
もっとも、最初から菊地氏の理想通りの保育ができていたわけではない。インタビュー1回目で触れた通り、「子供の主体性を育てる保育を」という理念は掲げていたものの、それを実現するための具体的な方策が整っていなかったため、実際に保育を担当する保育者たちが困惑する場面も少なくなかった。
そこで菊地氏は、2017年から全国各地の保育園を見学し、時には研修を受けながら、主体性を育てる保育のシステムづくりを模索した。
「いいなと思う取り組みをしている保育園はいろいろあったのですが、その共通点は何かと考えた時に、思い当たったのが“探究”というキーワードでした」
この言葉を軸に数年かけてブラッシュアップしてできあがったのが、「子どもたちの主体性を育むには、子どものつぶやき(興味関心)から始まるテーマをベースに保育者が仕掛け、共主体な保育をデザインするのが有効」という、探究保育の核である。核が決まったことで、保育者の採用基準が明快になり、具体的な方策が確立し、現場がスムーズに回るように。
また、2020年に大学の同級生で起業家としてすでに活躍していた田中滋之氏をCOOとして採用。菊地氏ひとりでは手が回っていなかった社内組織の整備が行われると同時に、新たな事業にも着手する。
最終回では、新事業について、また、菊地氏が今後目指すことなどをインタビューする。
※3回目に続く