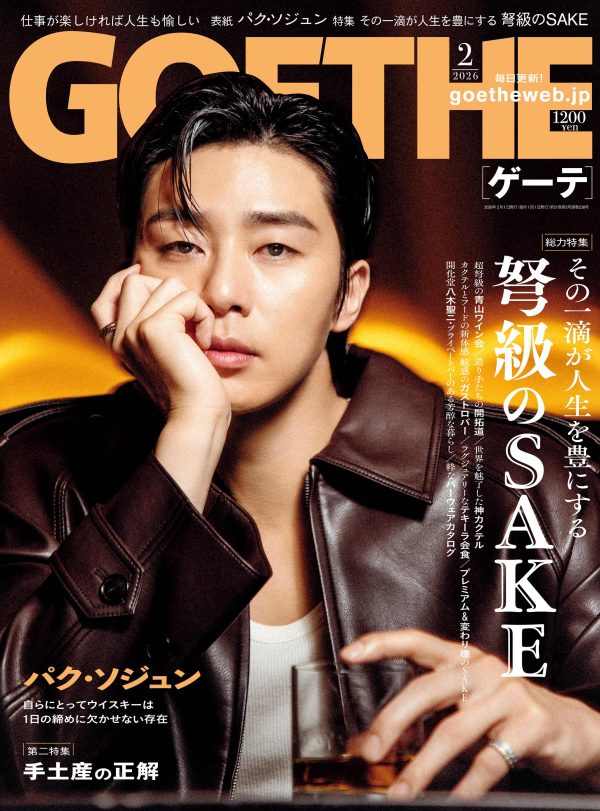2014年、弱冠19歳で保育園施設を立ち上げ、現在は首都圏で14園を展開するエデュリー代表取締役・菊地翔豊氏。「次世代を生き抜くキモとなる」と、同園が柱に据える「探究型保育」に迫る。1回目。

探究心の根底にあるのは自己肯定感
“美容院ごっこ”をしていた子どもたちが、実際に美容院を見学し、道具を研究。後日、ロール芯やダンボール、紐などを活用し、本格的なシャンプー台やヘアカタログなどをつくる。散歩の際に見かけたミックスジュースショップを参考に、ペットボトルや絵具、折り紙などを使って“ジュース屋さんごっこ”が園内で流行したのを機に、本物の野菜やフルーツを用いたジュース作りに挑戦する。こうしたユニークな取り組みを行っている保育園を展開しているのが、菊地翔豊氏が創業したエデュリーだ。
同社が目指すのは、子どもの主体性を育む「探究型保育」。耳慣れない言葉だが、その定義は、「『子どもが自ら課題を設定し、その課題を自ら解決できる能力』である主体性を最大化するために、(子どもの)興味関心を起点に保育をデザインしていく、そのプロセスを指しています」と、菊地氏。
「出生率が年々低下し、労働力の不足が懸念されている日本が、世界と伍するには、ひとりひとりの生産性を上げることが不可欠です。AIが益々台頭していくなか、人間に求められるのは探究心、専門性を突き詰める力だと思うんですよね。
AIは莫大な情報の中から、大多数の人が『これが正しい』と思えるような解を導き出すことはできるけれど、その枠にとらわれないユニークな“外れ値”を提案できるのは、人間の鋭い視点があってこそ。そして、そうした”外れ値“がイノベーションを起こすのだと思います。
探究心の底には自己肯定感や自己効力感があり、それらは、『自分が仮説を立てたことが合っていた』『自分だから出来た』という成功体験を幼い頃から重ねることで育まれます。それらが将来に良い結果を及ぼすことは 2000年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカのジェームス・J・ヘックマン教授の研究でも証明されています。
社会的幸福は就学前に決まる⁉
その研究というのは、ヘックマンが引用した1960年代にアメリカで実施された大規模調査「ペリー就学前プロジェクト」のことだ。
3歳~4歳の子供に2年間、アクティブラーニングを中心とした自主性や自己肯定感を育む教育を施し、その子たちの追跡調査を実施。すると、この教育を受けたグループは、受けなかったグループに比べ、雇用率や平均年収、持ち家率など、社会的幸福度が高いことが証明された。
このプロジェクトをベースに作成された「ハイスコープカリキュラム」は、2004年にOECDが“科学的根拠のある幼児カリキュラム”のひとつとして発表。それを機に日本でも広まり、主体性や自己肯定感を重視した教育は、家庭はもちろんのこと保育園や幼稚園、学校において重要視されつつある。とはいえ、うまく機能しているケースは少ないのが現状だ。エデュリーでは、どのように実践しているのだろうか。
「探究心を育むためにエデュリーが重視しているのは、子どものつぶやきを拾い、タイムリーに発展させること。保育者は、子どもが『やってみたい』と口にしたことはもちろん、視線や表情、しぐさなどからも、その子が何に興味を持っているかを読み取り、その熱が冷めないうちに、タイムリーに次のステップに発展させるサポートをします。
子どもは『電車をつくりたい』と思っても、具体的にどうすればいいかわかりません。それを、保育士が『どんな電車が好きなの?』『電車にはどんな部品があるかな?』などと、対話しながら、提案や助言をしていくといったイメージですね。
なかには、自分がやりたいことを言いだせない、やりたいことが見つからないという子もいます。ですが、他の子の“探究”にいっしょに関わっているうちに、だんだんと主体性が身に着いてきますし、『おもしろそう』と思えるものが見つかるんですよ。
また、当社の運営している保育園は規模が大きいところで園児数が80名、小さいところは30名です。一番大きな園の1クラスの人数でも14〜15名に抑えています。数百名の園などと比べて規模を小さくすることで、一人ひとりの探究に寄り添うことができるし、子どもたちそれぞれが今何に関心を持っているか、把握しやすいことも、短期間で”探究型保育”が成功している理由だと思います。
今後は大規模な園でも探究型の保育が実現できる仕組みの開発を進めていきたいと考えています。そんな風に、 “誰も置いていかれない保育”が実践できる仕組みになっているのも、当園の強みです」

1994年東京都生まれ。16歳でニュージーランドに留学し、現地で高校を卒業。帰国後の2014年、エデュリーの前身となる「KIDS ONE」を設立し、2016年に江戸川区にて「First step Ⅰ」を開園。2019年、社名をEduleadに、2022年エデュリーに変更。現在は東京・埼玉・神奈川で14園を経営している(グループ全体)。2015年、慶応義塾大学総合政策学部に入学。著書に『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』がある。
保育者採用で重視するのはキャリアより可能性
仕組みは完璧だとしても、それを実践するのは“人”だ。子どものつぶやきを見逃さず、上手に発展させるサポート力のある優秀な保育者の確保は、なかなか難しいようにも思える。
「保育者を採用する際に重視するのは、能力値ではなくポテンシャル。保育士としてのキャリアではなく、探究型保育に対する共感度や実践できるかどうかを基準にしています。なので、保育者の10%は別の業界からの転職組で、採用後に保育士資格をとった人もいるんですよ。内定率は13%程度と、保育業界では珍しいくらい厳しいと思います」
もっとも、この採用方法を導入し、現在の探究型保育が形を成したのは、2020年頃から。それ以前は、5年間で8つの保育園をオープンするなど急拡大したこともあり、保育士の応募があればほぼすべて採用していたという。しかし、「理念ばかり大きくて実務が伴わず、現場がどんどん疲弊し、保育者が辞めていった」(菊地氏)ため、一時離職率は30%に。業界の平均離職率は9.3%(厚労省発表の2017年度データ)を考えると、危機的状況に陥っていたことが伺える。
「一番の原因は、僕が『主体性を育む』という志を唱えるばかりで、具体的にどうするかまでうまく落とし込めず、保育者と理念を共有できなかったから。未熟だったと反省しています」
そもそもなぜ菊地氏は、19歳、保育士経験ゼロで保育園の起業に踏み切ったのか。次回はその経緯について語ってもらう。
※2回目に続く