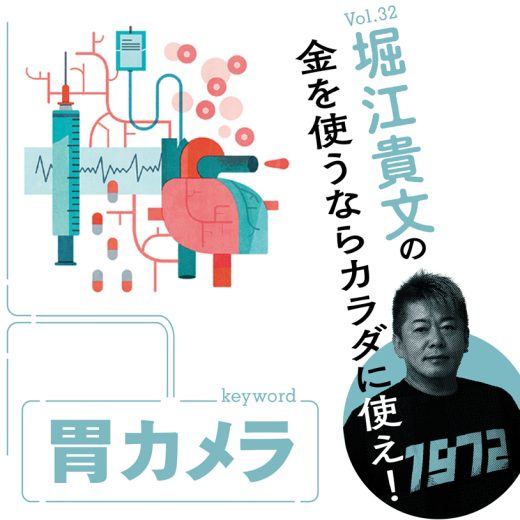AND MORE
2025.01.02
脳腫瘍、悪性リンパ腫、白血病、大腸がん、肺がんを乗り越えたIT社長…闘病と体力回復のリアル
40歳で最初のがんになり、53歳の現在までに脳腫瘍、悪性リンパ腫、白血病、大腸がん、肺がんを乗り越えた高山知朗さん。30歳で起業し「会社=自分」だったIT社長が、闘病を経て、会社売却を決断するに至るまで、どう“人生の方向転換”を果たしたのかを語る。『5度のがんを生き延びる技術 がん闘病はメンタルが9割』より一部を抜粋して掲載します。

急性骨髄性白血病が見つかる
2017年2月下旬、いつものように、虎の門病院血液内科で血液検査を受けました。悪性リンパ腫の再発チェックのため、2か月に1回のペースで検査を受けていたのです。
2013年に患った悪性リンパ腫の治療から約4年が経過していました。
その間、定期的に受けている検査で異常が見つかったことはなく、主治医のGY先生の診察は「問題ないですね」とすんなり終わるのが当たり前になっていました。
しかし、この日は違いました。
血液検査の結果に異常が見つかったのです。
先生によると、白血球や赤血球や血小板などの血球の数がいつもより少なく、特に好中球(白血球の一種)の数が非常に減っているといいます。
一瞬、再発が頭をよぎりましたが、再発であれば血球以外の数値にも影響が出ることが多いという説明を伺い、まずは安心しました。
多くのがん患者にとって、一番怖いのは再発が見つかることです。ですから、先生から再発ではなさそうだと聞いてホッとしました。ちょっとした異常に過ぎないに違いありません。
それでも詳しく調べるために、骨髄検査を受けることになりました。
骨髄検査はマルクとも呼ばれ、白血病や悪性リンパ腫の患者の間では痛いことで悪名高い検査です。注射針をお尻に近い背中から腸骨(骨盤を構成する骨)に刺して、骨髄液を吸引します。
注射針が骨を貫通するときのググッという鈍い衝撃、骨髄が吸引されるときのキューッとした不快感。
最初に受けたとき、噂で言われているほどには痛くないなと思ったものの、あの独特の不快感は忘れられません。
検査の結果は次回の診察で聞くことになりました。
ところが翌日の夕方、病院から携帯電話に着信がありました。
悪い予感がします。
電話をとるとGY先生からでした。
先生は話しにくそうに言います。
「急性骨髄性白血病でした」
急性骨髄性白血病、つまり血液のがんです。
先生によると、過去2回のがん(脳腫瘍と悪性リンパ腫)の再発や転移ではなく、別の新しいがんだそうです。
悪性リンパ腫も血液のがんなのですが、その治療時に行なった化学療法が原因で発症した、治療関連の二次がんだと説明されました。
私にとっては3回目のがんということになります。
まったく想像していなかったので、純粋に驚きました。再発か、なんでもないか、の2つの可能性しか考えていなかったのです。これまでと別のがんだとは予想していませんでした。
病名を聞いて、新たな不安がよぎります。
「ということは、今回は移植を避けられないということでしょうか」
「そうですね、今回の病気は、移植しないと治すことはできませんね」
これを聞いてまた衝撃を受けました。
移植、つまり造血幹細胞移植は、前回の悪性リンパ腫のときに勧められたものの、さまざまなリスクを考えて最終的には受けないことに決めた治療です。
2013年当時、私のタイプの悪性リンパ腫は、日本の学会における標準治療のガイドラインでも、化学療法だけで治るのか、移植が必要なのかは結論が出ていませんでした。
ただ虎の門病院の先生たちの感覚としては、どちらかというと移植したほうが治る可能性は高いだろう、とのことでした。
しかし、移植は抗がん剤の副作用や、移植した造血幹細胞による免疫反応、そして長く続くGVHD(移植片対宿主病)などと闘うことになる、非常に苦しく辛い治療です。
さらに、治療自体が原因で命を落とす治療関連死のリスクも小さくありません。できれば避けたいと思っていました。
そのため、悪性リンパ腫の治療のときは、移植をせず化学療法のみで治した事例はないかと海外の論文を自ら調べ尽くした結果、アメリカの論文で成功例を見つけ、その論文を根拠に、移植を避け、化学療法のみで治療をすることを選択しました。
ところが今回の急性骨髄性白血病では、移植は避けられないというのです。
後に自分でも調べてみましたが、国内のガイドラインでも海外の論文でも、私のような急性骨髄性白血病の場合は、移植が治療の第一選択となっていました。
当然ながら、先生たちも経験上、移植しないと治すことはできないとおっしゃいます。
先生からはすぐに入院したほうがいいと言われ、数日後から虎の門病院に入院することを決めて、電話は終わりました。
その夜、妻と娘に、また別の病気が見つかったことを伝えました。
当時6歳だった娘は号泣しました。それまでに見たこともないような激しい泣き方です。
「パパ、もう病気にならないって約束したのに! もう入院しないって約束した!」と、涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら繰り返しました。
「5日で帰る? 1か月で帰る?」
「……もう少しかかるかな」
「今度のはがんじゃない?」
「……今度の病気もがんだけど、でもまた治して帰ってくるよ。だって前のときも、その前のときも、ちゃんと治したでしょう?」
納得しない娘は、大泣きしながら「パパが欲しいものなんでもあげるから、すぐに帰ってきて。300枚入りの折り紙全部あげるから、早く帰ってきて!」と、小さな体全部で訴えてきます。
そんな娘を見て、妻と私と、3人で身を寄せ合って泣きました。がんの告知でこんなに泣いたのは初めてのことでした。
なぜこのときの告知が一番辛かったか
急性骨髄性白血病の告知は、それまでの2回のがんの告知よりも何倍も辛く、そして悔しいものでした。それは私自身の置かれていた状況によるところが大きいです。
私はこの告知の3週間前に、2001年に設立した株式会社オーシャンブリッジを売却していました。
それまで脳腫瘍、悪性リンパ腫と度重なるがん闘病を経験して、これ以上自分が経営を続けていくことは難しいと考えたのです。
病気になるまでは「死ぬまで会社を経営し続けること」が人生の目標だった自分にとって、自分が立ち上げた会社を売却して経営から退くというのは、まさに苦渋の決断でした。
2011年に脳腫瘍の摘出手術と放射線治療と化学療法を受けて退院したときは、体力的なダメージはそれほど大きくはなく、2か月ほどの自宅療養を経て、仕事に復帰しました(化学療法は退院後も通院で継続しました)。
手術の後遺症として視野の左下4分の1を失うという視覚障害が残ったことから、PC操作ではいろいろと不都合がありましたが、作業のやり方を工夫してなんとかしようとしていました。
しかし、2013年に悪性リンパ腫の治療を終えて退院した後は、体重が10キロほど減り、脚力や体力が衰え、仕事をするどころか会社に行くのも難しい状況でした。
身長176センチで体重46キロになってしまったので本当にガリガリで、脂肪も筋肉も大きく失われていました。
脚力は、床に座った状態から自分の足だけでは立ち上がれないほどに落ちていて、いつも窓枠や妻の体につかまって立ち上がっていました。
家の階段は四つん這いになったり両手で手すりにつかまったりして上り下りするしかありません。
2~3分も歩くと足が疲れ、近所を散歩するのもままならない状態でした。
それでも一日でも早く会社に戻りたいと、自分なりに毎日ウォーキングなどのリハビリに努めました。
数か月して、多少体力が回復してきたころ、週に1回くらいのペースでタクシーに乗って会社に顔を出せるようになりました。
とにかく早く仕事に復帰したい、またビジネスを通じて社会に貢献したいと必死でした。
私が設立したオーシャンブリッジは、海外のIT企業が開発したソフトウェアをローカライズ(日本語化)して日本市場で販売し、サポートを提供するビジネスを手掛けており、大企業や官公庁、自治体など幅広いお客様を抱えて事業を展開していました。
お客様から「オーシャンブリッジさんのおかげで業務効率が上がりました!」といった喜びの声をいただくたびに、世の中に貢献できているという手応えを感じていました。
海外と日本の「架け橋」としてのオーシャンブリッジの存在価値を実感することができました。
30歳で人生をかけて立ち上げたオーシャンブリッジという会社は、自分のアイデンティティの大きな部分を占めていたのです。
起業した会社に戻りたいのに戻れない
しかし、リハビリを続けながら少しずつ会社に顔を出せるようになってしばらくすると、幹部社員から、
「高山さんがたまに会社に来て社員に指示を出すと現場が混乱します。100%働けるようになったら会社に戻ってきてください。それまでは会社は自分たちが守りますから、高山さんは療養に専念してください」
と言われてしまいます。
思いがけず老害の一歩手前、いや老害そのものになっていました。
早く体力を回復して会社に戻りたい、と焦ってリハビリをがんばるのですが、体力は思ったようには回復しません。病気になる前を100%とすると、感覚としては50~60%程度がせいぜいです。
そして、あるとき気づきました。
ここからどんなにリハビリに励んだとしても70%程度まで回復するのがいいところではないか。100%、いや90%にすら戻すのは無理なのではないか、と。
つまり、もう以前のように仕事をすることはできないと悟ってしまったのです。
もはや経営者として以前のように自分が納得できるような働き方ができないのであれば、自分はどうすべきか。
自分にとって、会社にとって、社員にとって、どうするのが一番いいのか、何か月も悩みました。
そうして悩みに悩んだ結果、仕事も、経営者の立場も、そして会社そのものも手放すのが、自分にとっても会社にとっても一番よいという考えに至りました。
中途半端に会社にぶら下がり、創業者で大株主であるというだけで、大した仕事もせずに会社から給料を吸い上げるようなことはしたくありません。
だったらきっぱりと会社から身を引こう、と思ったのです。
そして、会社は意欲にあふれた新しい社長に任せて引っ張っていってもらうのが、会社と社員の今後の成長のためにもよいのではないかと考えました。
健康不安を抱えた社長の経営する会社では、社員も取引先も先行きに不安を感じて当然です。
とは言え、自分のアイデンティティでもある会社を本当に手放せるのか。
会社と仕事を手放した後、自分は何をして生きていくのか。
働く父親の背中を子どもに見せなくていいのか。
そもそも自分の収入がなくなったら、家族3人でどうやって食べていくのか。
何もしないで生きていく
再び悶々と思い悩む日々が続きます。自分の存在価値を揺るがすアイデンティティ・クライシスにおちいっていました。
しかしある日、妻の言葉で目が覚めました。
「会社を売却したら、もう何もやらなくていいんじゃない? 私も仕事をしてるんだし」
そして妻は続けました。
「仮に働く必要がなくて、やりたいことだけやればいい状況になったとして、それでもどうしても仕事がやりたいのであれば仕事をすればいいけど、そうでないなら無理に何かをしようとする必要はないよ」
この言葉には衝撃を受けました。
「何もしないで生きていく」ということを考えたこともなく、人間は一生、何か仕事をして生きていかなければならないと信じて疑わなかった自分としては、「何もしなくてもいい」という考えは純粋に新鮮でした。
「そうか、何もしないという選択肢があったのか」と。
自分が勝手に縛られていた固定観念を初めて疑うことになりました。
人間は働かなければならない、働かざる者食うべからず、という固定観念。
戦争から帰ってきてから長野で文具問屋を始めた祖父は、晩年も病床で帳簿をめくり、まさに死ぬまで働いていました。
そんな祖父の姿を見て育った私自身も、死ぬまで会社を経営し続けるのが人生の目標でした。
そんな自分が2011年に脳腫瘍になってからは、人生の優先順位を仕事から家族へと大きく見直し、人生の目標も「娘の二十歳の誕生日を家族3人で乾杯してお祝いする」というものに変わっていました。
それでもさすがに仕事を辞めるなんてことはまったく考えたことがなく、プライベートも大事にした上で仕事はずっと続けていくものだと、なんの疑いもなく思っていました。
それが、働かなくてもいい、何もしなくてもいいとは──。
そんな生き方があろうとは思いもよりませんでした。自分にとってはコペルニクス的転回でした。
会社に固執せず、思い切って手放すことで、また新しい人生がひらけるかもしれない、と思うようになっていきました。
友人や先輩に相談しながら、会社の売却について具体的に検討し始めました。ベンチャー企業のM&Aの専門家を何人か紹介してもらって相談していきました。
いろいろな方からアドバイスをもらいながら、1年ほどかけて売却先企業を選定し、売却条件を交渉していきました。
PICK UP
-

LIFESTYLE
PR2026.1.9
絶景と美食を満喫できる、“海最前列”の1日2組限定オーベルジュ「UMITO KAMAKURA KOSHIGOE」【ラウンジ会員限定プレゼント】 -

LIFESTYLE
PR2026.1.16
松田翔太「発進から力強くてレスもいい」。軽量&高性能PHEV「マクラーレン アルトゥーラ」に惹かれる理由 -

LIFESTYLE
PR2026.1.19
北海道・ニセコのバックカントリー拠点「ARC’TERYX NISEKO HUT」を体験。そこで触れた真の豊かさとは -

WATCH
PR2026.1.23
TASAKI、ジャパンメイドの高技術ドレスウォッチ -

WATCH
PR2026.1.23
日本が誇る、G-SHOCKの最高峰「MRG-B2100D」 -

LIFESTYLE
PR2026.1.23
鈴⽊啓太、肌ケア“10秒投資”。大人の美容液「SHISEIDO MEN アルティミューン」 -

GOURMET
PR2026.1.23
世界に2つだけ。グッチ大阪の秘密のミクソロジーバーに潜入 -

PERSON
PR2026.1.23
【アイヴァン】市村正親「演技とは、役を生きること」 -

LIFESTYLE
PR2026.1.30
メジャーリーガー・吉田正尚と「レンジローバー スポーツ」。進化を体現する者の邂逅 -

LIFESTYLE
PR2026.2.5
“不可能を可能にする”──ディフェンダーラリーチームがダカールで見せた証明。その挑戦の軌跡 -

GOURMET
PR2026.2.7
【14名限定募集】3/4 最高峰シャンパーニュ「ローラン・ペリエ」を堪能する、GOETHEプレミアムディナー開催
MAGAZINE 最新号
2026年3月号
今、世界が認めるジャパンクオリティ「日本のハイブランド」
仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ3月号』が2026年1月23日に発売となる。特集は、今、世界が認めるジャパンクオリティ「日本のハイブランド」。表紙は中島健人!
最新号を購入する
電子版も発売中!
GOETHE LOUNGE ゲーテラウンジ
忙しい日々の中で、心を満たす特別な体験を。GOETHE LOUNGEは、上質な時間を求めるあなたのための登録無料の会員制サービス。限定イベント、優待特典、そして選りすぐりの情報を通じて、GOETHEだからこそできる特別なひとときをお届けします。