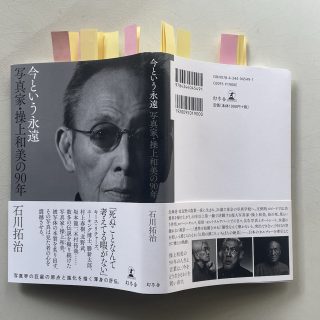前年度の赤字6億2000万円。そんな会社を2年で黒字化させた経営者が行った驚くべき改革とは!? 役職も部署もすべて廃止、社員全員をフラットにした人事を、ITサービスの「Colorkrew(カラクル)」中村圭志社長が語る。後編は、フラットな人事制度の給与と評価システムについて。#前編

「フェアである」その確信が働く人にとっては大事
中村圭志氏が社長に就任した前年の2009年には、6億2000万円の赤字を出していたというカラクル。明確な人事評価システムもなく、毎年赤字を出し続けてきた社員の士気は最低まで下がり切っていた。そのなかで中村氏は5年の歳月をかけて、すべての部署と役職をとりはらい、誰もが自由に意見を言いプロジェクトに参加できる制度をつくりあげる。
しかし、部署もなければ上司も部下もない。いったいどうやって、それぞれの評価や給与を決めていくのだろうか。
「給与は、当人が指名する数名と会社が指定する数名からの評価を集めて決めています。この評価の内容も給与も透明化し、完全公開しています。
まず給与を透明化するにあたって、なぜ上がったのか、下がったのかを明確に説明できる基準を数年かけてつくり、公開に踏み切りました。すると社内から『それなら、評価理由も公開すべきだ』と声が上がったんです。
評価してもらう人は各社員が自分で指名していますから、その人がどんなことを言うのか、それを知るのはこわいし、評価する方も『高い評価をしてくれなかった』と僻まれるリスクはあるでしょう。私ですら『そこまで透明化するのはどうなんだろう』と思ったくらいです。
けれどその頃には、役職をなくしすべての情報を全員が知ることができる環境になっていて、社員たちの間では「オープンにすることがいいことである」というカルチャーができ上がっていました。『誰かが誰かに甘い評価をしているんじゃないか』、そういうふうにモヤモヤするくらいなら、すべてを公開すべきだと90%以上の社員がアンケートに回答したんですよ。うちの社員すごいな、そこまでオープンなんだと驚きました」
時間をかけて年々、組織を透明化。そのなかで業績も伸びていく。
「透明化した、フラット化したことが業績と実際どのような因果関係にあるのかはわかりませんが、それでも業績は徐々に上がっています。会社は自分も仲間もフェアに扱っている、その確信が働く人にとっては大事なのではないでしょうか。
そもそも誰もが『自分はこんなもんじゃない』と、自己認識と他者からの評価にギャップを持っています。けれど誰が誰をどう評価しているのか、すべてが透明化されていれば、その評価を見比べて納得することもできると思うのです。ひとりに嫌われたら終わりなんてことはけっして起こらない、機会が平等にあるということ。それが社員のやる気につながっていくと考えています」

1970年新潟県生まれ。1993年豊田通商入社。営業を務めた後、2004年にToyota Tsusho Europe S.A. ドイツ・デュッセルドルフ支店へ出向。2006年にToyota Tsusho ID Systems GmbH設立・代表就任。帰国後にISAO(現Colorkrew)代表取締役に就任。2020年に社名をColorkrew(カラクル)に変え独立。ソフトウェア設計・開発・運用などを行う。自身が制作に携わったプロダクト『Colorkrew Updates』が2025年1月にローンチしたばかり。
透明な状態では、不正は極めて起こりにくい
給与の完全公開。それはつまり誰がどれくらい給与をもらっているのか、日常的に当たり前のようにわかっている状態にカラクルの社員はあるということだ。
「そうなってくると、もう他の人と比べるというより、自分自身との戦いなんです。自分が成長しさえすれば評価は上がって給与に反映されますから」
とは社員からの言葉である。
「あいつは自分よりサボっているのに、給料が高そうでムカつく」などと無駄に悶々とすることもなく、嫉妬も足を引っ張り合う競争も生まれはしない。比べることに意味がないからだ。
また、自分を評価する人に賄賂やお歳暮なんかを事前に送って高く評価してもらう、ということをしたとして、そもそも評価内容が公開されるうえ、複数人で評価するしくみのなかでは不自然な高評価は簡単に見破られる。さらに賄賂を受け取った人物も評価される側になるので、自分で自分の首をしめることになってしまう。
「カラクルでは、誰がどう経費を使っているのかも公開しています。自己決済はいっさい禁止で、事前に申請し承認された分のみの使用が可能です。会食の際は写真を撮り、本当にその会食が申請通りの人物とともに行われていたかどうかも報告するんです」
もちろん社長でも役員でも、一般社員でもこのルールに例外はない。このように完全に透明な状態であれば、不正は極めて起こりにくいのだ。
キャリアの形成過程も透明化
カラクルで透明化されているのは給与や評価だけではない。社員ひとりひとりが、入社時から現在までどんなプロジェクトに関わりどんな仕事をしてきたのかを、システムに記録、誰もが見ることができるのだという。それはつまり、成長を遂げた社員やお手本となる先輩社員の活動を参考にするこができるということ。
「裏技としては、そうやって自身のキャリアを築くためにも透明化された情報は役に立つかもしれませんね。そもそも通常、組織の中間管理職になると、部下のマネジメント、上司との調整などにほとんどの時間を割かれ本来の業務ができなくなります。けれど弊社の社員はマネジメントの仕事に価値を置いておらず、もちろんそういうことをしなければいけないことはありますが、基本的にみんな何かをつくりたい、それを広めていきたい、そのなかで自分を磨いていきたいという人たちなんです」
とはいえ会社を運営するにあたってマネジメントは必須だ。
「経営チームはありますが、そのメンバーもそれぞれプロジェクトに入って、システムをつくったり売ったりする仕事もしています。私も含めてチームや組織のトップであることにまったくこだわりがなく、みんな1日の大半はプロダクトをつくることに費やしていますね。僕は社長ですが、それは会社の最終責任をとるということにおいてだけ。経営の仕事は全体の仕事の30〜40%くらいでしょうか。プロダクトづくりにおいては社長としての意見なんて言いませんし、リーダーやデザイナーと協力して、チームみんな同じ目線でつくっています。リーダーから『中村さん、これ来週までに仕上げてよね』なんて今も急かされていますよ(笑)」
実際に中村氏が制作を担当したプロダクト「Colorkrew Updates」もローンチしたばかり。仕事の進捗状態を常に共有できるシステムだという。
「こういうものがあればいいな、そう思ったものをつくって広められるのがこの仕事の醍醐味ですから」
そう笑って自分が関わっているプロダクトを説明する中村氏は終始笑顔だ。社内政治、出世争い。そんな煩わしさから解き放たれ、誰もが本来の業務に夢中になれる。それがフラットで透明化された会社で起きていることなのだ。