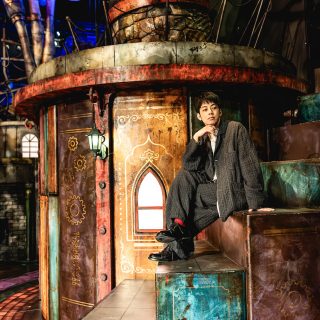1万人以上のストレスに向き合ってきた脳科学者・西剛志氏が、「仕事のストレス」を断ち切る方法を伝授。最短1分、誰もが気軽に取り組める科学的メソッドに、きっと心が軽くなるはず。『脳科学でわかった 仕事のストレスをなくす本』(アスコム)から一部抜粋して紹介する。【その他の記事はこちら】

<ネームチェンジ法>
・やり方 :苦手な相手の携帯などの登録名を、記号やアルファベットに変える
・得られる変化 :苦手な相手を思い出し、ストレスを感じることがなくなる
・効く相手 :理不尽な上司、好きでない同僚、もう忘れたい人など
・こんな場面で :目の前にいない苦手な相手をどうしても思い出してしまうとき
驚きの変化! プライベートから上司が「消えた」
ご紹介するのは、自宅でも通勤電車の中でも、どこでも今すぐできる「ネー ムチェンジ法」です。これは、簡単かつ非常に強力な方法であり、たった1分で脳にバリアを張り、苦手な人からのストレスを減らすことができます。 私のクライアントで、広告関係の会社に勤めるMさん(30代女性)の上司は、とにかく気分屋でした。
朝は機嫌よく挨拶していたのに、午後になると些細なことで感情的に怒鳴る。金曜の夕方に「月曜までに」と理不尽な指示を出すことも日常茶飯事。特に良くなかったのは、時々、休日にも電話をしてくることでした。Mさんの会社には社用携帯がなく、個人の携帯で仕事をせざるを得ない状況でした。仕事柄、休日に急な連絡が入ることもあるため、上司や同僚の番号も登録しておかなければなりません。
ただでさえ、上司がストレッサー(ストレスの原因)になっているのに、「休日にごめんなさい。どうしても確認したいことがあって」と、それほど緊急でもない内容で電話をかけてきたこともあり、Mさんは困っていました。ある日、「もう限界です」と相談に来たMさんに、私が最初に提案したのが、「携帯電話の、上司の登録名を変えること」でした。
携帯やスマホなどの登録名を変え、「苦手な人」「好きでない人」に扁桃体を反応させないようにする。この方法を、私は「ネームチェンジ法」と呼んでいます。
ネームチェンジ法は、「ネームコーリング効果」を利用した、脳科学的に実証された方法です。ネームコーリング効果は、「相手の名前を呼ぶことで親近感を抱かせる」というものであり、営業や恋愛の場でもよく使われています。
「ネームチェンジ」をする際には、自分や家族のイニシャルを避け、自分にとってもっとも縁遠い、もっとも無機質な、もっとも「何の感情も湧かない」文字や言葉を選びます。携帯やスマホなら、アルファベット一文字でもいいかもしれません。Mさんは本人の要望で、携帯の上司の登録名を「B」という文字に変更しました。
登録名を変更して3日後、Mさんから「着信画面に『B』と表示されても、前ほど大きなストレスを感じなくなりました。それに、会社を出た後、上司のことを思い出す回数がすごく減ったんです」との報告がありました。さらに1か月後には、「以前は休日も『月曜日になったら……』と考えてばかりだったのに、とても楽な気持ちで休日を過ごすことができるようになりました。本当にビックリです」との報告も。もちろん、会社での関係性は変わっていません。でもMさんは、少なくともプライベートの時間では、「扁桃体にバリアを張る」ことに成功したのです。
名前を変えたとき、脳内で起こること
上司の名前を変えると、Mさんの脳内では次のようなことが起こります。
①感情の自動起動が止まる
たとえば、携帯電話に相手の名前を「田中部長」と登録していたら、「田中部長」という文字を見ただけで、相手の役職や顔、怒鳴られた声、理不尽な要求、相手への恐怖感など、すべてが一瞬でよみがえります。
しかし、「B」という記号を見ても、脳は「これは誰だっけ?」と一瞬考える必要があります。このワンクッションが、扁桃体の過剰反応を防ぐのです(これを専門用語で、「介入」といいます)。
また、私たちの脳には「連合記憶」という仕組みがあります。脳は名前を「インデックス(見出し)」として使い、その人に関するすべての情報を整理しています。「田中部長」という名前には、顔、声、匂い、過去の出来事、感情まで、すべてが紐づいており、名前を見た瞬間、脳はこれらすべてを自動的に再現しようとします。条件反射で心拍数が上がり、手に汗をかき、胃が痛くなる。これを意志の力で止めることはできません。
しかし、「B」という記号には、何の情報も紐づいていません。「B」を見ても、脳が「過去の田中部長に関する記憶」を再現しにくくなるのです。さらに、マイナスなものに脳が過剰に注目し続ける「注目バイアス」も、「B」という無意味な記号には働きません。つまり、名前を変えることで
・記憶の自動連鎖が断ち切られる
・感情的な反応が起きにくくなる
・その人への注目が自然に薄れていく
といったことが起こり、結果として、扁桃体の過剰反応もストレスホルモンの分泌もなくなり、ストレスを感じにくくなるのです。
②連絡先リストからも「消える」効果
携帯電話の連絡先は「あいうえお順」で表示されますが、英数字は一番最後。「B」に変更すると、その上司は連絡先リストの最下部に移動し、日常的に目に入る回数が減ります。その結果、相手を意識して思い出す回数が物理的に少なくなり、ストレスを感じる頻度も自動的に縮小していきます。
③脳はコントロールできるとき快感を感じる
ここがもっとも重要なポイントです。扁桃体は、コントロールできないものに反応して恐怖を感じます。たとえば、車の運転席にいきなり知らない人が乗ってきてアクセルを踏まれたら、どんな気持ちになるでしょうか。多くの人が怖いと思うでしょう。しかし、自分でハンドルを握って操作できると大きな安心感が戻ってきます。
実際の研究でも、私たちはコントロールできる状況にいると、「楽観主義バイアス」といって、プラスに考える力が高まることがわかっています。「B」はただの記号であり、「人」ですらありません。そのため、心理的距離が大きくなるだけでなく、自分にコントロール感が戻ってきやすくなるのです。
名前の力を利用して親近感を作るのではなく、逆に、名前から力を奪い取ることで、コントロール感を取り戻す。この方法は、実はハリー・ポッターの世界でも描かれています。
魔法界の人々は、ヴォルデモートのことを「例のあの人」「名前を言ってはいけないあの人」と呼んでいました。名前を口にすると、恐怖がよみがえるからです。だから名前を封印し、別の呼び方をすることで、恐怖をコントロールしていたのです。作者のJ・K・ローリングは、名前が持つ心理的な力を知っていたのかもしれません。
苦手な人の名前を「B」や「あの人」(または別の名前)に変える。たったそれだけで、自分に本来のコントロール感が戻り、相手はあなたの脳内で「力を失った存在」になっていきます。これは魔法ではなく、脳の仕組みを利用した、れっきとした技術なのです。
あだ名選びの重要なコツ
あるクライアントは、苦手な上司に「パープル」というあだ名をつけました。自分の好きでない色が紫だったからだそうです。ところが、これは大失敗でした。道を歩いていて、紫の服や紫の髪の色を見るたび、上司を思い出す。ネットを見ていても、紫色が目につく。「苦手な色」×「苦手な上司」で、ストレスが再現されてしまったのです。
ネームチェンジ法を成功させるためには、名前を変える際、
・日常的に目にしないもの(食べ物、動物、日用品、地名、有名人などはNG)
・自分にとって縁遠いもの(趣味や好きなものに関連しないもの)
・無機質で感情が動かないもの(記号や数字、アルファベット、元素名、関心のない名称など)
を選ぶ必要があります。
携帯の登録名を変えるだけでなく、メールの振り分けフォルダ名や、スケジュールに書く相手との打ち合わせ予定を「B案件」などにするのも効果的です。もちろん、上司との関係性が変わるわけではありませんが、少なくともストレスを感じる頻度は確実に少なくなっていきます。
なお、言うまでもないことですが、ネームチェンジ法は相手をバカにしたり見下したりするものではなく、あなたの脳にコントロール感を取り戻すための方法であり、あくまでも、あなたの脳に住み着いていた「あの人」から自由になるための、「緊急避難」的な方法です。
ストレスで押しつぶされそうになっている、つらい思いをしていて自分らしい時間を過ごすことができない……。そんな人にとっては、ネームチェンジ法によって、自分の扁桃体を守ることが最優先です。しかし心が回復し、ストレスが軽減されたり、相手の関係が改善されたりすれば、また普通の登録名に戻してもいいかもしれません。

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。武蔵野学院大学スペシャルアカデミックフェロー。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。東京工業大学大学院生命情報専攻修了。2002年に博士号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子供まで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて4万人以上に講演会を提供。『世界仰天ニュース』『モーニングショー』『カズレーザーと学ぶ。』などをはじめメディア出演も多数。TBS Podcast「脳科学、脳LIFE」レギュラー。著書に20万部のベストセラーとなった『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』、『1万人の才能を引き出してきた脳科学者が教える 「やりたいこと」の見つけ方』『結局、どうしたら伝わるのか? 脳科学が導き出した本当に伝わるコツ』など海外を含めて累計43万部突破。