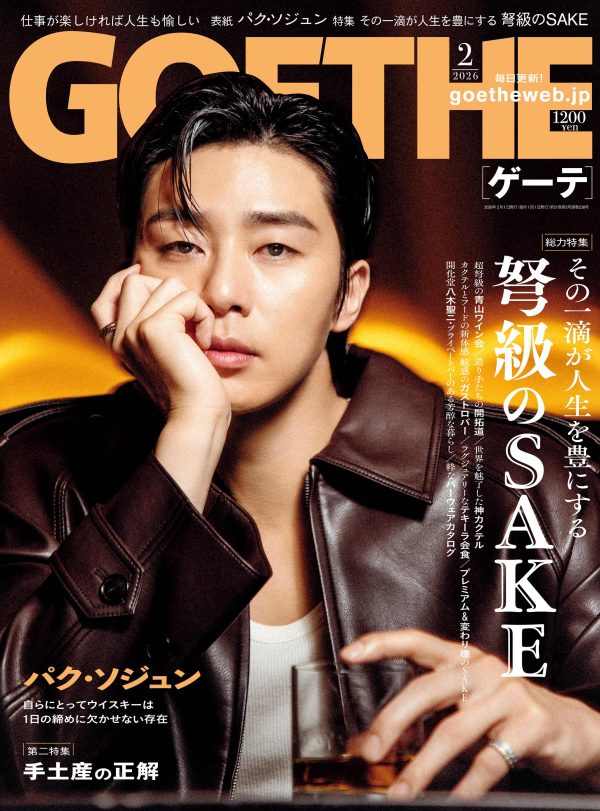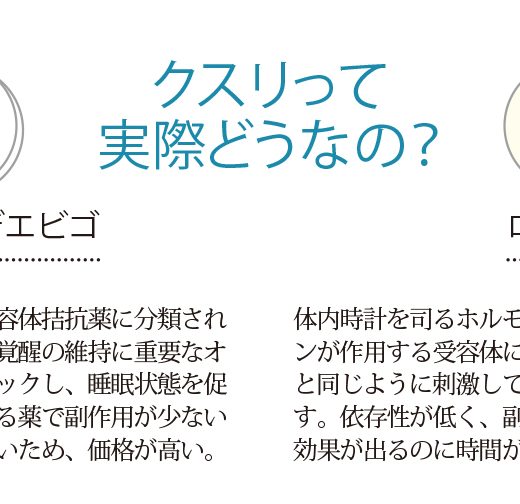ガンや認知症、肥満予防のためにも良質な睡眠は欠かせない。寝苦しい夏でも、ぐっすり眠るための秘訣とは? 睡眠学の権威・スタンフォード大学西野精治教授に伺った。2回目。

夏の眠りは深部体温と体内時計のコントロールがカギ
寝苦しさに悩まされる日本の夏。なかなか寝つけない、夜中に何度も目が覚める、早朝目が覚めてしまうといった悩みを抱えている人も少なくないだろう。実際、厚労省の『健康づくりのための睡眠ガイド2023』によると、四季を通じて夏が最も平均睡眠時間が少なく、冬に比べると10~40分も短くなるという。
夏の寝苦しさの一番の理由は、気温の高さにある。
「皆さんご存じの通り、赤ちゃんは眠たくなると手足がポカポカと温かくなります。これは、手足の動静脈吻合から熱を放散し、深部体温(身体内部の体温)を下げるため。日中の活動時よりも深部体温を低くすることで、脳や身体を休息モードにするのです。
ところが、日本の夏は気温も湿度も高く、熱放散がされにくいので、深部体温が下がりづらくなってしまいます。結果、なかなか寝つけない、ぐっすり眠れないといった問題が生じてしまいます」
眠るのに快適な温度は、18~26℃、湿度は50%前後とされている。夏はいずれもオーバーしているので、エアコンを活用し、適切な室温と湿度をキープしたい。
「本来は一年を通して同じ室温、湿度が理想ですが、光熱費を考えるとそうはいかないので、夏は25~26℃に設定してはいかがでしょうか。寝具は、熱や湿気がこもらないよう、通気性や放湿性に優れたものがおすすめです。寝ている間にコップ1杯分の汗をかくので、パジャマは通気性と吸湿性のある素材で、身体を締めつけないものを選んでください」
深部体温を下げるには、寝床につく90分前にバスタブにつかるのも効果的だ。
「深部体温は大きく上がると、その分大きく下がろうとします。40℃のバスタブに15分つかると深部体温は0.5℃程度上がり、その後90分かけて入浴前の体温より下降します。つまり、就寝90分前に入浴すれば、スムーズに寝つけるのです。ただし、シャワーの場合、深部体温はそれほど上がらないため、入眠効果は期待できません」

1955年大阪府生まれ。1987年、当時在籍していた大阪医科大学大学院からスタンフォード大学精神科睡眠研究所に留学し、2005年、同大学睡眠生体リズム研究所所長に就任。『スタンフォードの眠れる教室』をはじめ、著書多数。
“光”を利用して体内時計のリズムを整える
気温と共に夏の眠りの大敵となるのが、日照時間の長さ。日の出が早く、日の入りが遅いため、体内時計のリズムが狂ってしまうのだ。
「体内時計は24時間より少し長いので、油断していると後ろにずれがちです。そのずれを、朝日を浴びることでリセットしているのですが、夏は日が昇るのが早いため体内時計が前にずれてしまいます。その分日が沈むのが早ければ問題ないのですが、長時間外が明るいため、なかなか休息モードに切り替わりません。それも、夏の睡眠時間が短くなる原因です」
体内時計が前倒しされるのを防ぐには、朝日を浴びる時間をコントロールするのが有効。寝室の窓の位置にもよるが、早朝から朝日が注ぐようなら遮光カーテンを活用し、光が目元を刺激しないよう調整を。
「これは夏だけに限りませんが、夜の照明にも注意が必要。眠りを促すホルモンとして知られるメラトニンは、光を浴びると分泌が抑えられ、暗くなると分泌が促進されるという特徴があります。目が光の刺激を受けると、網膜にあるメラノプシンが青い波長の光を感知し、脳の視交叉上核を経由して松果体に信号を送り、メラトニンの分泌を抑制してしまうのです。青い波長の光は太陽光にも含まれ、覚醒作用や気分高揚作用があるので日中に浴びる必要ありますが、夜間は青白い照明ではなく暖色系の照明をほの暗く灯すのが望ましいです。
パソコンのモニタやゲーム機器、スマホもなども、ブルーライト領域の比率が高いLEDが用いられており、メラノプシンを刺激してメラトニンの合成や分泌を抑制してしまいます。なので、少なくても就寝1−2時間前には遠ざけてください。なお、就寝中は、できれば室内は真っ暗にしましょう。暗いのが苦手ならば、フットライトなどを用い、眼に光の刺激が入らないようにしてください」
次回は、睡眠に関する疑問のあれこれに答えてもらう。