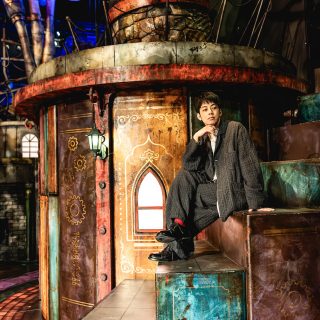練習量や内容など、さまざまな課題を抱える“パパコーチ”チームが強くなるにはどうしたらいいのか。平日の自主練から練習試合の相手まで、育成歴30年のFC町田ゼルビアのアカデミーダイレクター・菅澤大我氏がアドバイス。#第4回 連載記事はコチラ

チームを強くする方法とは。練習量は大人がコントロールしなくていい
――平日仕事を持つ保護者が指導しているチームの場合、練習は週末だけのこともあります。それでは練習量が不十分なので、平日は、サッカースクールに通わせるなどした方が良いですか?
菅澤 Jクラブをはじめ、いろいろなサッカースクールがあるので、それを活用するのも一案でしょう。ただし、大切なのは、子供たちがスクールを楽しんでいるかどうか。“習わされている”感が強くて、つまらないとか飽きてしまっているようなら、無理に通わせる必要はないと思います。
子供が一番上達するのは、「楽しいからボールに触れている」「好きだから、毎日やっても飽きない」という気持ちで取り組んでいるとき。理想は、やっぱりストリートサッカーですよね。空き缶をゴールに見立てたりして、2対2とか3対3、時には5対5でゴールを競い合う。子供たちなりにいろんなルールをつくるでしょうし、限られたスペースをどう使い、どう攻略すれば勝てるかなど、工夫を凝らすでしょう。やっているうちに、自然とボール扱いがうまくなっていき、動き方もわかっていくと思います。そもそも、大人に言われたことをやるより、子供同士で自由にやった方が楽しいに決まっていますからね。
ただ、公園をはじめ、子供たちがボールを蹴れる場所が減ってきているのは大きな課題。例えば、学校の校庭を解放してもらうなど、我々大人が解決してあげないといけないですね。
――であれば、練習試合などは、子供たちで相談してポジションを決めさせるなど、自主性を重んじた方が良いのでしょうか?
菅澤 うーん、今は“子供の自主性”が叫ばれる時代ではありますが、指導者が帯同するのは週末中心というチームで、そうする必要はないと思います。子供だけで考え、行動するのは、ストリートサッカーでやればいいこと。せっかく指導者がいるのですから、その適度な緊張感の中、モラルを持ってサッカーをすることも大切です。
それに、自分たちでポジションを決めさせると、小学生の場合、うまくいかないことが多いんじゃないでしょうか。右サイドが手薄になるとか、中盤が緩すぎるなど、対戦相手にとって物足りない試合になってしまうでしょうし、トレーニングで強化してきた部分が生かしづらくなってしまう。なので、練習試合は、指導者が日頃の練習の“狙い”通りに選手を配置した方がいいと思います。
――練習試合を組む際、どんな相手を選べば良いですか? 格上の相手と対戦した方が上達しますか?
菅澤 練習試合は、自分たちが目指すサッカーを実行できる相手をメインにした方が上達すると思います。言葉を選ばずに言うならば、自分たちより弱いチーム。これは、J下部のチームにもいえること。格上の相手だと、主導権を相手に握られてしまい、ボールを持てない時間が長くなりがちです。それでは、自分たちが日頃練習し、目指すサッカーを試すことすらできません。それに、相手が強豪チームだとしても、試合に負け続けていると、子供たちのテンションが下がってしまう。練習試合が楽しみどころか、憂鬱に感じてしまいますよ。
ただ、月に1回くらいは強い相手にチャレンジするのがおすすめです。トーナメントなど、強い相手と当たった時の緊張感や強度などに“場慣れ”しておくことも大切ですし、自分たちの目指すサッカーがどれくらい通用するかを試す機会にもなりますから。
基本は勝てる相手を選び、数回に1回は、「負けたけれど、良い試合だった」と思える相手と対戦できるとベストですね。
――小学生年代におすすめの戦い方はありますか?
菅澤 先日観戦したチームは、2-1-3-1というシステムを取っていました。センターフォワード、トップ下、アンカー、両サイドにオフェンシブハーフがいて、ツーバック気味という配置ですね。で、指導者がしきりに「広がれ!」と声をかけていたんです。そのせいか、選手間の距離がすごく離れていました。
小学生の場合、ボールを受けた際、近くに味方がいないと結構難しいんですよ。遠くにいる味方に正確なパスを通せないので、ソロ(ひとり)でなんとかしなければならず、選択肢が限られてしまいますから。ドリブルも、パスも選べて、方向も変えられるなど、選択肢は多い方がその子の良さは出やすい。なので、どんなシステムであっても、選手間の距離は近い方がいいと思います。

1974年東京都生まれ。1996年、選手として所属した読売クラブ(現・東京V)育成部門コーチとなり、元日本代表の森本貴幸氏や小林祐希氏ら、数々の逸材を発掘。その後、名古屋グランパスや京都サンガF.C.へ。ジェフユナイテッド市原・千葉ではTOPチームとアカデミーを指導。ロアッソ熊本などで育成年代のコーチや監督を歴任し、2021年からFC町田ゼルビアのアカデミーダイレクターを務めている。
――ドリブルといえば、小学生年代は、ボールを取られるまでどこまでもドリブルで突き進む子が珍しくありません。ボールを持ち過ぎた結果、チャンスがつぶれることも多々あります。それは、注意した方が良いのでしょうか?
菅澤 状況に合わせて、ドリブルかパスかを選択できるのが理想ですが、小学生年代は無理に是正しなくてもいいのではないでしょうか。ドリブルで、相手を抜きまくってゴールを決めるのは、子供にとって最高のロマン。それを禁止するのは、サッカーの楽しみを奪うようなものだと思います。失敗しながらでもチャレンジする中で、自然と「この場面はパスした方がいいな」と気づいていくはずです。
試合に勝ちたいというあまりに、普段攻撃の練習が絶対的に多いのに、ゲームで攻撃を尊重せず、単調な攻撃を繰り返し、守備的なプレーをよく見かけます。当然ネガティブな試合になり、培ってきた攻撃的なパフォーマンスを発揮しきれないで終わるのはもったいないと思います。若い時にはたくさんチャレンジさせたいですね。
※第5回に続く
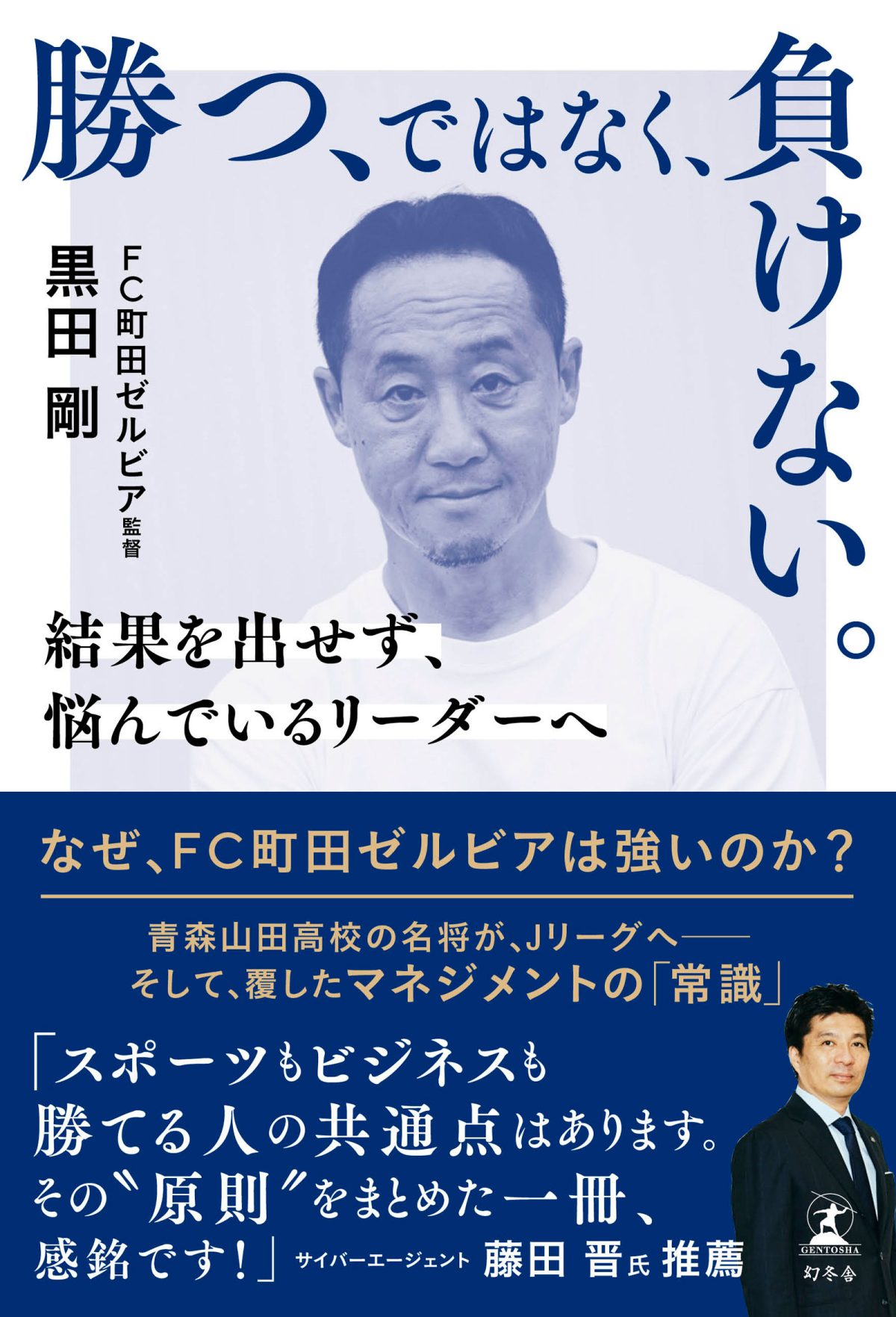
FC町田ゼルビア大躍進の裏には、アマでもプロでも通用する、黒田流マネジメントの原理原則があった。組織・リーダー・言語化など、4つの講義を収録。結果を出せず悩んでいるリーダー必読。黒田剛著 ¥1,540/幻冬舎
▶︎▶︎▶︎購入はこちら