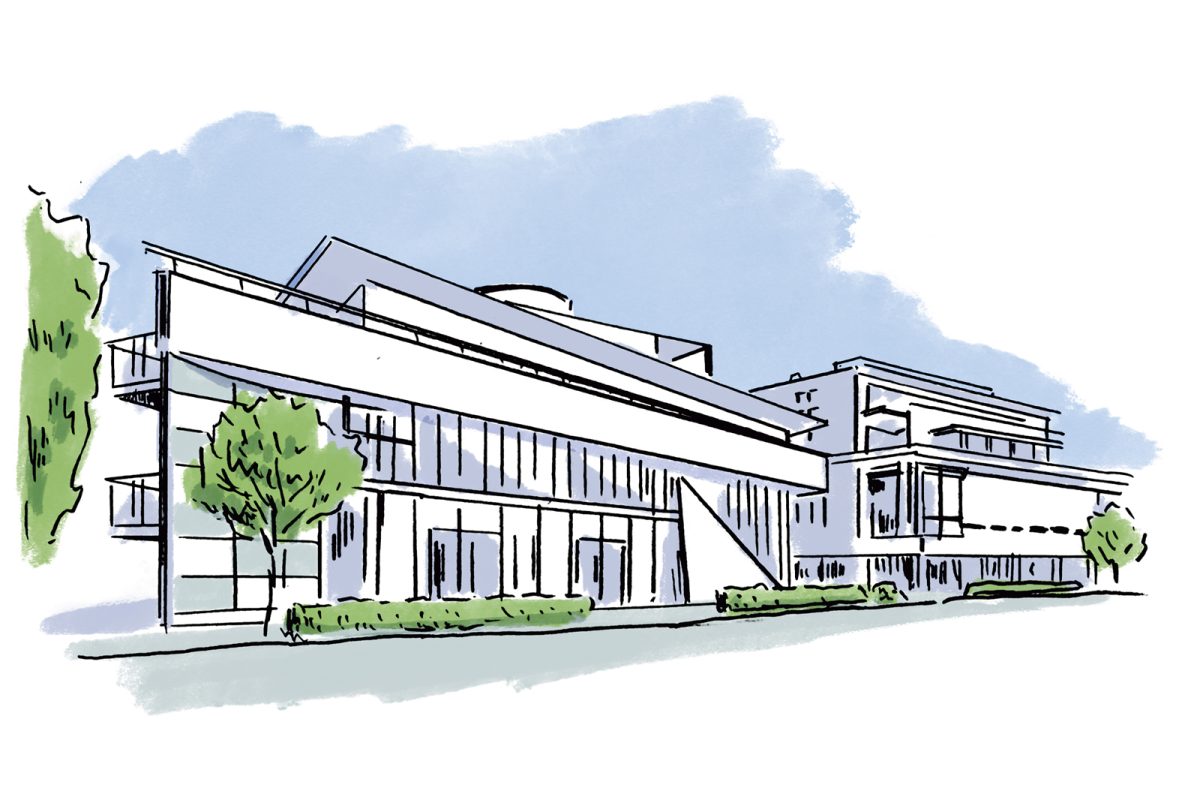東京23区の中古マンション平均価格が「億超え」 となって話題だが、ここで紹介する住まいは、そのはるか上を行く。直近の坪単価1000万円超の物件も含まれる「東京ヴィンテージレジデンス」はいかにして育まれたのか。【特集 超絶レジデンスとシェア別荘】

現代では見られない希少な仕様を凝縮
住宅業界の通説に則ってヴィンテージレジデンスを定量的に説明すると「築10年以上」「直近の坪単価300万円以上」となる。いずれも高いハードルだが、中古マンションの価格高騰が続く現在、この2項目を満たす物件は東京に数多い。
しかし、ここで紹介する東京ヴィンテージレジデンスの草創期は1960年代だ。高度経済成長期当時は、富裕層の住まいといえば山手線外側の城南、城西エリアに立つ一戸建ての意識が強い時代。ただ、多忙を極めていた経営者らから都心部の会社に近いエリアに住みたいというニーズが生じていた。
それを受けて登場したのが千代田区、港区、渋谷区といったエリア内の繁華街や幹線道路から少し離れた閑静な環境に佇む、ハイスペックな集合住宅だ。’60年代には東京への人口集中対策として都下や臨海地区に大規模な公営住宅が建てられたが、それらとは一線を画す、富裕層のステータスを満たす住まいである。そして、希少な立地や個性的な外観の意匠、敷地・専有面積の広さ、緑に恵まれた環境など、諸条件の際立った物件がヴィンテージへと成熟していった。それらは坪単価1000万円超えの物件も含まれる、まさに異次元の住まいだ。ここでは、そのなかから代表的なレジデンスを紹介していく。
デザインの観点で今でも街のアイコンとなっているのが、「ビラ・ビアンカ」「代官山ヒルサイドテラス」だ。共通している建築様式は、’60~’70年代に欧米で活躍した建築家、ル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエらが牽引した「モダニズム」。鉄筋コンクリート、鉄骨、ガラスなどを駆使した直線的な造形は“建築作品”とも呼べる。今もその芸術性に惹かれて入居する文化人やクリエイターが少なくない。
日本で暮らす欧米のエグゼクティブ向け高級住宅として、1965年に登場したのが「ホーマット」シリーズだ。外構の特徴は日本初といわれた総タイル張りの外壁や、鉄平石の重厚なエントランス。専有面積は200㎡台も珍しくなく、ゲストを招く生活様式に即してパブリックとプライベートを完全分離したプランが主流。’60年代はもちろん、現代のマンションでもなかなか見られないゆとりを誇っている。

専有面積115.14~258.21㎡、ベッドルーム数2~4。ホーマットシリーズではおなじみのBBQ施設完備。2006年に耐震補強工事が完了。
1971年に竣工した「三田綱町パーク・マンション」は、19階建てのツインタワー。竣工当時は都内で3番目の高さであり、眺望が住まいの価値となることを知らしめた。また、各フロア4戸限定で1戸当たり約115~128㎡を確保しているプランニングや、全147戸につく自走式駐車場も希少だ。
敷地入口は第一京浜に接しながら、歴史ある邸宅街「城南五山」のひとつ「八ツ山」の高台に立っているため、「ペアシティ・ルネッサンス」は喧騒と無縁の環境を確保している。隣接する三菱グループの迎賓館「開東閣」の緑を借景にできるのも得難いアドバンテージだ。
豊かな緑との共生では「広尾ガーデンヒルズ」は特筆に値する。広尾駅徒歩3分ながら、敷地は山手線内の集合住宅で最大規模の約5万7000㎡。そこに欅80本、桜43本を含む約370本の樹木を配置し、「広尾の森」との別名もある。約1200戸、計15の住宅棟は5街区にゾーニングされ、ロンドンのタウンハウスにならったデザインや雁行型、特注タイルの外壁など異なる意匠も特徴だ。そのため圧迫感は皆無で、都心とは思えない穏やかな時間が流れている。
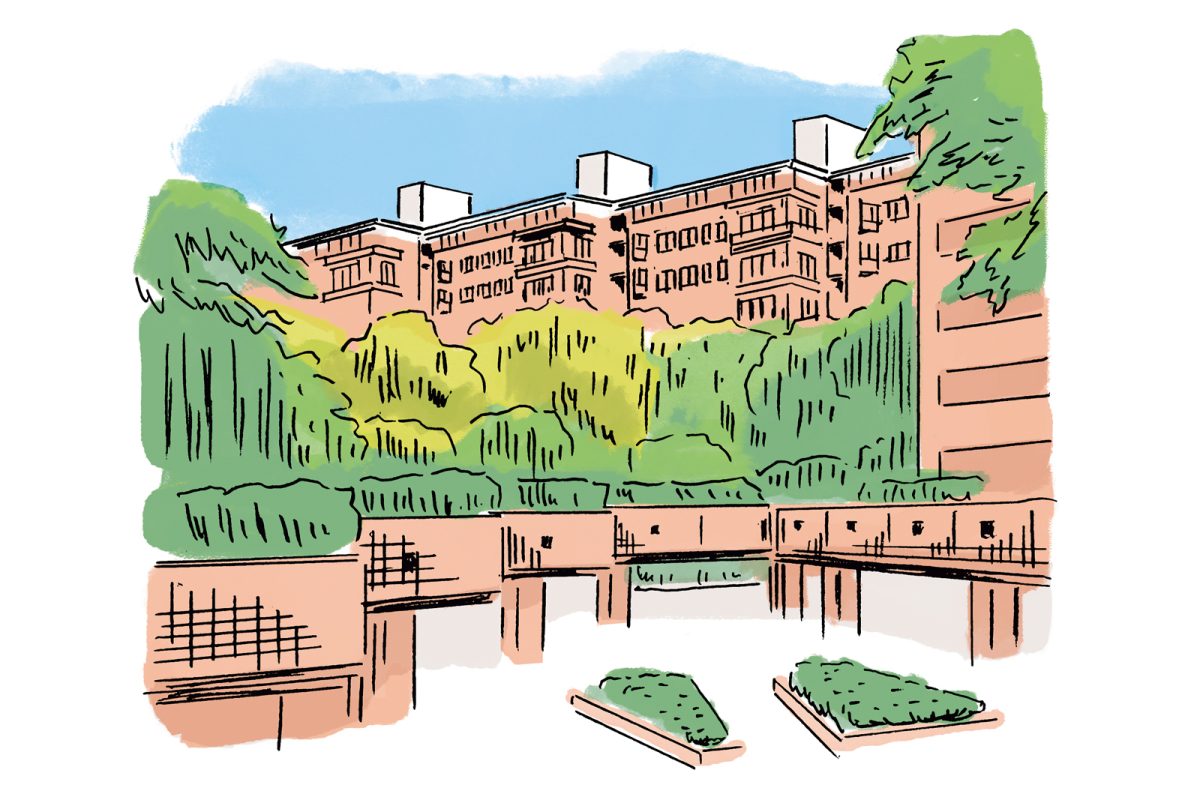
1983年の最初の分譲街区・イーストヒルの最高抽選倍率は約209倍。”億ション”も多く含まれていたが即日完売し、話題を集めた。
最後は独自の高級路線を堅持する「ドムス」シリーズ。全19物件中、多くは赤坂・青山・麻布の“3A”内に立ち、平均専有面積は約200㎡、天井高は約3m。シリーズ最高峰の呼び声が高い「ドムス南麻布」ではバカラのシャンデリア、ベルサイユ宮殿でも採用されるフォンテーヌ社製ドアノブ、カナディアンメープル張りの家具などが全戸標準仕様。贅を尽くしたマテリアル、仕様は近年のマンションではまず見ることができない。

全15戸。2025年9月現在の参考坪単価は1000万円以上。外壁タイルはイタリア国内の山を購入し、そこに作った窯で焼いた特注品。
住人の不断の努力で価値が持続可能に
ここで取り上げた東京ヴィンテージレジデンスは、現代ほど都心部の開発が進んでおらず、高度経済成長期~バブル期にかけて潤沢に資金を投入できた時代の産物だ。ゆえに、言わば“先駆者利益”で高い付加価値を得たとも言える。しかし、今もそれが維持されているのは、住人で構成される「管理組合」の努力があればこそ。管理会社任せにせず、植栽の育成管理、セキュリティの改良、住人コミュニティ活性化などを提案し、価値を維持・向上させている。
基本的にセラーで寝かせておけばヴィンテージになるワインと違い、レジデンスがヴィンテージであり続けるには、多くの住人の努力と住まいへの愛着が欠かせないのだ。
この記事はGOETHE 2025年12月号「総力特集:超絶レジデンス+シェア別荘」に掲載。▶︎▶︎ 購入はこちら