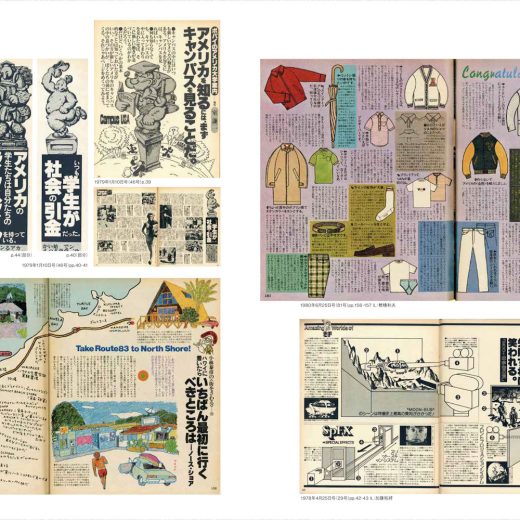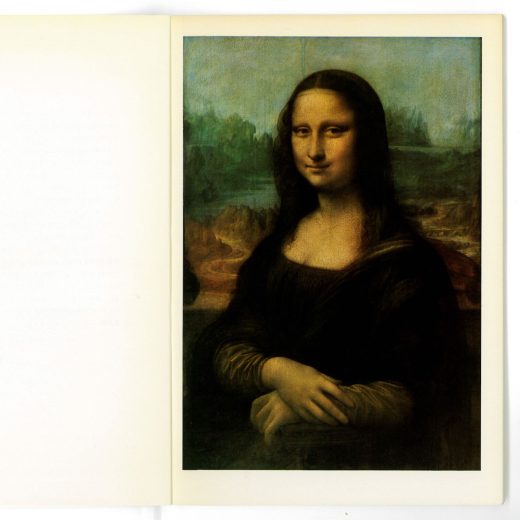広告や出版メディア、映像などジャンルを横断して目覚ましい活動をし、国内外で高く評価されている写真家が、コロナ禍に独りでライカを携え、野の花や古都の寺社を撮影した。ただ写真が撮りたいという衝動に駆られての行動だったが、自分を見つめ直すこと、宇宙を感じることだと気づく。それは見事な2冊の写真集に結実し、写真家の想いを伝えてくれる。

コロナ禍で取り戻した、初めてカメラを手にしたときの高揚感
写真家、瀧本幹也(1974年愛知県生まれ)は広告、エディトリアルなど第一線で活躍し、多くの賞を受賞する一方で、自主的な作品制作活動とその展覧会や作品集出版などでこれまでにも注目を集めてきた。映像の仕事では、コマーシャルフィルムも手がければ、メジャーな映画の撮影者として、カンヌ国際映画祭はじめ国内外の賞もものにしている。
そんな瀧本のオフィスから、次に出す写真集では、高価で最上の用紙を惜しみなく使い、しかも、すべてのページの印刷に立ち会っていると聞いて、それだけでただごとではないと思っていた。その写真集が製本され、完成したところで話を聞きに行った。
写真集は『LUMIÈRE』と『PRIÈRE』。LUMIÈRE(ルミエール)は光。PRIÈRE(プリエール)は祈り。それぞれどういう写真集なのだろう。

――瀧本さんはこれまでにも、巨視的な視点で地球を捉えて見せてくれたり、スペースシャトルに独自の視点で迫ることで人類の宇宙に対する夢や想いを写真にしたり、また地球上の自然遺産や人類の遺産が観光地となっていて、そこに集まる現代人をやや風刺的に眺めたシリーズも名作ですね。
宇宙がもともと好きで、小学校の頃から趣味が天文だったんです。僕の原点は天体望遠鏡にカメラを取り付けたところから来てるんです。赤道儀の軸を北極星に合わせ、観察、観測するような撮り方から入ってます。だから、写真家になってからも、4×5(インチ)とか8×10(インチ)などの大判カメラの方が入りやすかったというのがあります。スナップ写真とかファッション写真とか、そういうところからじゃないので。撮影の仕方が、ちょっと遠くから客観的に見てるみたいな。
スペースシャトルの打ち上げを撮影するためにNASAに4回通ったんですが、毎回4×5とか8×10のカメラを持っていきました。あとは遠隔撮影用の6×8(センチ)、これはフィルムが自動で送られるカメラで、スペースシャトル打ち上げの爆音でシャッターを切れるように改造したものです。僕以外、他の報道で来ている写真家たちは最新鋭のデジカメに望遠レンズがあたりまえなわけで、そんな旧式で大掛かりな機材を持ち込んだ僕はそうとう奇異に見えたと思います。

コロナ禍の初めの頃、うちの子供たちもみんな休校になってリモートで授業をやるようになって、一家のなかで僕だけCM撮影とか、大人数が集まってする撮影があるわけです。僕が家に帰るとウイルスが帰ってきた、みたいな感じになってしまって。2020年の4月、5月くらい以降、さらに緊急事態宣言が出て、人と接触をしなくなってからも一週間くらいは家に帰らず、渋谷のホテルに泊まっていました。
どこにも行くな、写真も撮るな、って言われる。ホテル暮らしもけっこう気が滅入る。一週間くらい小さな部屋にいたんですけど、さすがにちょっと頭がおかしくなると思って、西伊豆の方の温泉宿、部屋にお風呂がついているところに引っ越すことにしました。感染もしてないんだけど自主隔離っていうか、終わったら家に帰ろうって思ってたんです。部屋にいないといけないんだけれど、近くの川に行くくらいはいいだろうって思って、ライカを持って、菜の花の写真を撮りに行ったんですね。

菜の花が咲いてるのかわからないまま、河原に行ったら菜の花が一面に咲いていて。それまでの世界と何ら変わらずに。人も全然外にいないときでした。それで、撮れたのがこれでした。これらの花々は何十年、何百年、何世紀もこの場所で命をつないでいるんだなと。大地に根を張り、太陽からの光を受けてきたんだなと。
こっちはそれまで大人数で大きな機材を持って、スタッフと共にやってたのが、ライカを持って、地面に転がって、地面から空を見上げる。視点が変わったんですよ。まったくこういうこと考えてなくて。人間目線じゃない視線で撮った感じとか。コロナが本当に早く収まってほしいっていう気持ちで撮ったのがこれです。これを撮ってるときは、本当に気持ち良くて。やっと写真が撮れた。子供の頃、初めてカメラを手にしたときの高揚感を覚えながら、無我夢中に撮り続けました。
――与謝蕪村の「菜の花や月は東に日は西に」(安永3年/1774年)を思い浮かべました。「菜の花=地球」と「月」と「日=太陽」、つまり太陽系、宇宙をたった17音に織り込んでいる。

自然にたどり着いた小さな精神宇宙
――『LUMIÈRE』に収められているのはそういう経緯で撮影された写真なのですね。『PRIÈRE』の方はどんな被写体なのでしょう?
2020年、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭2020』でお寺での展示をしました。妙満寺という岩倉の方のお寺です。江戸時代の歌人、松永貞徳が作庭した「雪の庭」という庭が現存しているところで。枯山水では岩を山に見立てていて、白い石を海に見立てている。お寺の空間は展示する壁面がほとんどないので、どういうふうに展示するのが最適なのか考えました。
そこで、雪山の写真を枯山水の岩のように見立て、室内に配置しました。「雪の庭」というテーマから、回遊式庭園のように、雪山で岩をつくって、中に入って上から見てもらおうと。神の視点じゃないけど、見下ろして見てもらおうというコンセプトでした。襖もつくりました。白い漆喰の壁に映像を投影したり、Bluetoothスピーカーを和紙で巻いて音が出るようにして。炎がメラメラメラってなるように。
例年だと4月5月に開催される『KYOTOGRAPHIE』がコロナで9月10月に延期になってので、毎週末、会場に立つためにお寺に行っていたんです。それも夕方4時くらいに近くのお寺にサッと行って、枯山水の庭とかを見に行ったりしてました。まったく人がいなくて、ひとりで貸切状態でした。

1時間ずっと目を閉じて、ぼーっとしていても、誰ひとり来ない。それはこれまで経験した京都のお寺とは違っていました。本来のお寺の姿、流れる時間というのはきっとたぶん、こういうものだったんだろうなと気づいて、その頃からお寺にすっかりハマってしまったんです。もともと、お寺とか仏教美術とか茶道とかにまったく興味がなかったのに、コロナの3年間くらいの期間、ずっと京都のお寺めぐりをしていました。
仕事が忙しくなるとなかなか京都や奈良に行けなくなってしまうじゃないですか。それはまずいと思って、京都の和菓子屋さんの仕事を入れたんです。1日40カットから80カットとか撮る仕事です。それがあれば2〜3ヶ月ごとに必ず行かないといけなくなりますから。そのために日帰りで行っていたらもったいないから、その前後数日つけて、作品も撮ることができるなって。そうしたら、そっちの和菓子の仕事でADC賞を獲ってしまったんですけど。
――今回、写真集にまとめ、そして写真展も開催されます。
ただ撮っていただけでした。花もそうだし、お寺の方もそうだし、最初はまとめるつもりはなくて、ただ、きれいだなとか、行くたびにちょっとスナップしていたくらいです。それがどんどん自分の中で大きくなって。
これまでは、NASAでスペースシャトルを撮るとか、僻地を撮るとか、広告を撮るとかだと、あたりまえにラフスケッチを自分で描いて、それを設計図のようにして、どうやったら撮れるかとか、作戦を立てて撮影してきたわけですが、たとえばお寺にひとりでフラッと入って、そこですごい景色に出合えることに気づいてしまった。撮り方も全然違うんです。
よくよく考えてみると、というか、撮っていくうちに気づいたのですが、大きな宇宙を撮ろうとしていたのが、ミクロ、マクロを超えて、小さな精神宇宙に自然にたどり着いたということですよね。
ちょっと話が長くなりましたけど、そういうわけで、宇宙あってのこれなんです。

「円融」という言葉を、お寺の住職の方から教えていただきました。円が融けあうって書くんですけど、水が一滴落ちて、それが小川に流れていって、大きな川になって、海になって、それが空に上がる。循環していく。すべてのものは融けあってつながっているっていう仏教の言葉だそうですが、一滴の水が海を想像させるということですね。
――以前、このオフィスにうかがったときは、こんなに古美術品はなかったですよね。
そうですね。古美術品そのものは、何百年、何千年前からずっと存在しているものです。残っていくものにすごく惹かれていまして、最近。こういう器とかも、中国の三千年前とかのものだったりする。それがちゃんと残っていて、僕が死んだあとも誰かの手に渡っていく。僕はある期間ちょっと預かっているという感覚です。広告写真の仕事をやっていると、やっぱり消費されているなという思いがどうしてもあります。僕は今年、50歳になるんですけど、あらためて、残っていくものをやっていかないとダメだなって、そういうことを感じるようになってきました。

是枝(裕和)監督作品に撮影者として携わるなかでも感じたのですが、是枝さんの映画って絶対残っていくじゃないですか。もしかしたら百年後も誰かが観たり、自分の子供とか孫とかが大人になったときに、おそらくもう1回観たりするだろうなって思います。そういうことをしていきたいという気持ちがすごく強くなってきました。
東京に住んでいると、街では建てては壊し、ばかりじゃないですか。そういうのってどうなんだろうって考えるようになってきました。一方で京都は、一千年以上前のものがきちんと丁寧に残っている。そういうことに惹かれるようになってきたのは自分の年齢のせいもあると思いますし、コロナがあったからかもしれないですね。

¥13,200 / MT Gallery / 青幻舎
248ページ 、165点 、303×223×30mm
寄稿 : 森田真生

¥13,200 / MT Gallery / 青幻舎
248ページ、170点、303×223×30mm
寄稿 : 安藤礼二
【写真展情報】
東京/代官山ヒルサイドフォーラム
2024年12月5日〜12月15日
京都/Gallery SUGATA
2025年2月8日〜3月9日
Yoshio Suzuki
編集者/美術ジャーナリスト。雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がける。また、美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。前職はマガジンハウスにて、ポパイ、アンアン、リラックス編集部勤務ののち、ブルータス副編集長を10年間務めた。国内外、多くの美術館を取材。アーティストインタビュー多数。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。