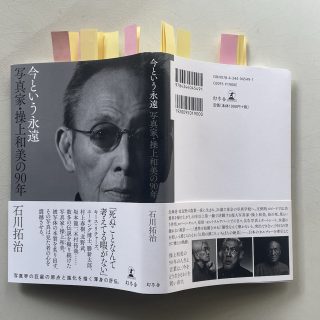とある児童養護施設で暮らす子どもたちの日常をていねいに追ったドキュメンタリー映画『大きな家』。2024年12月6日の公開を前に行われた、企画・プロデュースを担った齊藤工氏と監督を務めた竹林亮氏のインタビュー後編では、私たち大人は子どもたちとどう向き合うべきか、そして、家族の在り方について話を聞いた。#前編

児童養護施設には、病気や貧困、虐待など、さまざまな事情から親といっしょに暮せない子どもたちが入所している。被写体となった子どもたちも、それぞれの事情を抱えているが、『大きな家』では、彼らのバックグランドにはあえて触れていない。それでも、観る者はきっと感じるに違いない。明るく振舞っている彼らが、親に対する複雑な気持ち、将来への不安、社会の理不尽さ、そして、認めたくない現実と戦っていることを。
斎藤氏は、1日限定のイベントでの訪問をきっかけに4年前から、竹林氏は、映画の企画が立ち上がった2年半前から、たびたび施設を訪れ、そんな子どもたちと向き合ってきた。斎藤氏と竹林氏は、今、何を想うのだろうか。

児童養護施設の職員がもっとも重視すること
――お二人は撮影期間中、長きにわたって舞台となった施設に通い、子どもたちと接していらっしゃったと思います。一番印象に残ったのはどんなことでしょうか?
竹林亮(以下竹林) 子どもたちは原則、18歳を過ぎると、施設を巣立っていかなくてはなりません。職員さんたちはその時が来るまでに、子どもたちが社会で強く生きていくために、どう自立させるかを意識しながら、日々、彼らと接しているんですね。そこで何を一番、子どもたちにインプットしたいかと聞くと「自己肯定感」と。それがあれば、折れない心を持てるからだという話を伺いました。
施設の子どもたちは、和気あいあいと暮らしていますし、周りの大人からとても大事にされています。でも、施設にいることをオープンにしたくないという子もいれば、自分が暮らすべきところは他にあって、ここは仮の暮らしだという子もいたりして……。今の生活を認めたくないみたいなものは、どの子にも一貫してあるように感じました。
それが垣間見えた時に、職員さんたちが、「自己肯定感があれば、心が折れることなく、社会でやっていける」と話していたのが、理解できました。同時に、僕らを含め、彼らに接する周りの大人がちょっと意識を変えて、働きかければ、(子どもたちのモヤモヤは)ちょっと緩和できたりするんじゃないかということにも、気づかせてもらいました。

斎藤工(以下斎藤) 実は、撮影の間は、僕はあまり現場には行かず、子どもたちとは極力接しないようにしていました。彼ら全員が(芸能人である)僕のことを知っているわけではなかったんですが、僕の存在がノイズになりかねない気がしたんです。
むしろ、僕が担当すべきは、職員の方々。日々の生活の中に長い時間カメラが入るわけですから、不安やストレスもあるはず。それに対し、安心していただけるようにするのが、僕の役割だと思っていました。
施設の子どもたちの声に耳を傾けようとしてこなかった
―― 『大きな家』を観て、子どもを取り巻くさまざまな社会問題に想いを馳せました。自分が招いたわけではない、本人たちにとっては、ある意味理不尽な理由から施設で暮らす子どもたちに対して、我々大人は何ができるでしょうか?
斎藤 一撃で解決できるような社会問題はないと思いますが、その問題に興味を持つ、意識する、愛情をもって心を傾けるのが、第一歩ではないでしょうか。関わり方は人それぞれですが、多くの人たちが、この問題に気づくきっかけに、この映画がなったらいいなと思っています。
そもそも僕がこの作品を企画したのは、これまで自分が見て見ぬふりをしていた世界と、向き合うためでした。この作品を観た施設の職員さんが、「児童養護施設に入所している子どもたちの声が社会に直接届く機会はあまりない」とおっしゃっていた通り、僕も、その声に耳を傾けようとしてこなかった大人のひとりなんです。
4年前、あるイベントのボランティアとしてこの施設を訪れました。その時、ひとりの子が、「あなたも、またもう二度と来ない大人なんだね」という目をしていたのが忘れられず、その後何度か、施設を訪れるようになりました。そうする中で感じたのは、“質より量”というか、会う回数がモノを言うのだということ。
撮影が終わった後も、竹林さんやプロデューサーの福田文香さんたちは、子どもたちとごはんを食べに行ったり、遊びに出かけたりしているんですよ。俳優志望の子が、僕のドラマの撮影現場に来たこともあります。そんなふうに、“続編”がずっと続いていますし、頻度は変わったとしても、この先もずっと、この関わりは続くだろうと思っています。
竹林 この作品に関わる前は、児童養護施設がどういう所なのか、まったく知りませんでした。初めて施設を訪問してから2年半、子どもたちにとって、親や周りの大人がどんな役割を果たすべきかというヒントを、本質的な部分で感じられた気がします。
齊藤さんが言う通り、子どもたちにとって、継続的な眼差しを自分に向け続けてくれる相手は必要だし、それがあるだけで、子どもの中に大きな変化があるのではないかと思います。そして、その大人とは、肉親に限った話ではない。日常的にカメラという眼差しを向けられることでの子どもたちの反応を見ていた時に、そんなことを、ふと感じました。

「家族」という言葉に執着する必要はない
――施設で共に暮らす子どもたちや職員のことを「家族」と表現する子もいれば、「家族ではない」という子もいました。おふたりは、「家族」とはどんな存在だとお考えですか? また、本作の制作を通じて、家族観に変化はありましたか?
斎藤 人間は“個”では無い、ということを認める象徴の言葉なような気がします。切り離せないとわかっているからこそ、関わる角度や相互関係、お互いにほど良い距離感を取りたい存在なのではないでしょうか。
『大きな家』に関わって、さまざまな家族の形に触れて、僕はこれまで、向こう(家族)からのアングルや矢印に合わせようとし過ぎていた気がしました。互いの理想に縛られていたんじゃないかと。同時に、他人だからこそ、“本家”を超えた家族のような存在にもなれるのかなと、思うようになりました。

パリコレ等のモデル活動を経て、2001年俳優デビュー。『昼顔』、『シン・ウルトラマン』など数々のドラマや映画で主演を務め、現在配信中のNetflix『極悪女王』やTBS日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』など話題作に出演中。俳優業と並行して映像制作にも積極的に携わり、初⻑編監督作『blank13』で国内外の映画祭で8冠を獲得。劇場体験が難しい被災地や途上国の子供たちに映画を届ける移動映画館「cinéma bird」の主宰や全国のミニシアターを俳優主導で支援するプラットフォーム「Mini Theater Park」を立ち上げるなど、幅広く活動している。
竹林 めちゃくちゃ個人的な意見ですが、家族という言葉に執着せず、少しゆるく構えるくらいがちょうど良いのではと思っています。その人との関係を括る言葉を探さずに、大切と思う気持ちを大事にすることで生きやすくなるなら、そっちの方が良いなと。
元々はそんなに意識せずに無頓着に生きてきたところはあったのですが、改めて家族の定義について葛藤する子ども達と会話を続けながら、こちらも色々と考えさせてもらいました。
僕には子どもがふたりいるんですが、これまで、親としてどういう役割を果たせばいいのか、悩みながら過ごしてきたところがあったんですね。社会の目を意識し、親としてのプレッシャーを感じていたというか。進路に関しても、「お前、この先どうするんだ。どの学校を受験するんだ」なんて、子どもに詰め寄ったりして。

コマーシャル、YouTubeコンテンツ、リモート演劇、映画等、さまざまな映像作品を監督。2021年公開の青春リアリティ映画『14歳の栞』は単館からのスタートだったが、SNSで話題となり45都市にまで拡大。監督・共同脚本を務めた長編映画『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』にて、第32回日本映画批評家大賞 新人監督賞・編集賞を受賞。
でも、この施設を通じて、子どもたちの今の姿を認め、肯定するまなざしを送り続けることで、子どもたちはいろいろなチャレンジができるし、安心して前に進めるんだということを感じました。
おかげで、しつけや進路など、親としてストレスに感じてきた問題が少し小さく思えるようになりました。今は、少し肩の荷を下ろして、子どもに期待し過ぎず、否定もせず、今の姿を肯定するまなざしを送り続けるという、シンプルなことを一番大事にしようとしています。……いつもそうであることは、ちょっと勇気と努力も必要なのですが(笑)。
さまざまなことを気づかせてくれる『大きな家』。この作品は、被写体となった子どもたちだけでなく、観る人にとってもまた、“人生のお守り”になることだろう。
衣装クレジット(齊藤氏):セットアップ・スニーカー(ワイズフォーメン/ワイズ プレスルーム TEL:03-5463-1540)、シャツ(ヨウジヤマモト/ヨウジヤマモト プレスルーム TEL:03-5463-1500)