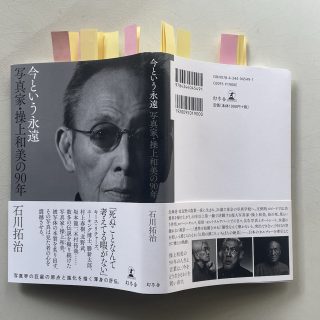2009年から’15年の約6年半、のべ500日以上をかけて、47都道府県、2000近くの場所を訪れた中田英寿。世界に誇る日本の伝統・文化・農業・ものづくりに触れ、さまざまなものを学んだ中田が、再び旅に出た。

窯焼きは炎の動きで思いがけない作品ができる
旅をしていると、「気のいい場所」だと感じることがある。佐賀県唐津市の山あいにある唐津焼の窯元「隆太窯」は、まさにそんな場所だった。隆起に富んた敷地内には小川が流れ、古民家を改築したという作業場やギャラリーが並ぶ。観光用の庭園のように手入れが行き届いているわけではない。目に入るのは、自然のままの雑木や雑草。それでもその場にいて、吹き抜ける風を感じると、それだけで心が安らぐように感じる。
この隆太窯は、唐津焼の人間国宝にもなった12代太郎右衛門氏の5男である中里隆さんが開いた。中田英寿が訪問した日、隆さんは不在だったが、息子の太亀さんと孫の健太さんが作業場でロクロを回していた。

「すごく気持ちのいい場所ですね」(中田)
いまの季節はいいですけど、夏は暑いし、冬は極寒ですよ(笑)。雪が降り込んでくるなかでロクロを回していることもありますよ」(中里太亀さん)
ロクロを回す二人を静かに見ている中田。沈黙もまた心地よいのもこの場ならではの感覚かもしれない。
「登り窯がいくつかありましたが、焼きの作業は窯で行うんですか?」(中田)
「ほとんどはガス釜を使っていて、窯焼きをするのは年に5〜6回です。窯焼きは炎の動きで思いがけない作品ができるという楽しさがありますが、どうしても“歩どまり”が悪いんです」(中里太亀さん)
聞けば、2日後に窯焼きを行うという。中田は予定があり、その日の朝には東京に戻らなければならなかったが、われわれスタッフは“居残り”可能だった。太亀さんにお願いして、2日がかりで行われるという窯焼きの火入れを見学させてもらうことにした。
火入れが行われるのは夕方。しかし準備は午前中から始まる。成形された器を敷地内の登り窯の中に隙間なく詰め込んでいく。置く場所によって炎の動きや温度の上昇速度が異なることを計算に入れながらの作業だ。ぎっしりと詰め込むと、入り口を封じ、あとは火入れを待つのみ。

火入れの時間がやってきた。まずは窯のスタッフと見学のわれわれにも酒器が回され、窯焼きの成功を祈って乾杯。「焼き物の神様」にも献杯が行われる。もっと緊張した雰囲気かと思っていたら、みんなどこか楽しそうだ。まるで小学校のキャンプファイヤーの前のようなワクワク感がある。
「ここから二晩かけて焼きます。1200度まで上がったら、あとはそれが下がらないように薪を焚べ続けるだけです」(中里健太さん)
夜中も誰かが窯のそばにいて、小山のように積み重なった薪がすべて灰になるまで焼き続ける。
「窯の中は、どんなに計算してもしきれない。だから面白いし、やめられないんです」(中里太亀さん)
しばらく見学していたが、東京に帰る飛行機の時間が迫ってきた。できれば焼き上がりまで見ていたかったし、この場の空気をもう少し吸っていたかった。しばらくクルマで走って振り返ると、隆太窯の方向からゆったりと煙が上がっているのが見えた。窯に詰め込まれた器たちがどう変わっていくのか。その完成形をまた見に来たくなった。

「に・ほ・ん・も・の」とは
2009年に沖縄をスタートし、2016年に北海道でゴールするまで6年半、延べ500日以上、走行距離は20万km近くに及んだ日本文化再発見プロジェクト。"にほん"の"ほんもの"を多くの人に知ってもらうきっかけをつくり、新たな価値を見出すことにより、文化の継承・発展を促すことを目的とする。中田英寿が出会った日本の文化・伝統・農業・ものづくりはウェブサイトに記録。現在は英語化され、世界にも発信されている。2018年には書籍化。この本も英語、中国語、タイ語などに翻訳される予定だ。
https://nihonmono.jp/