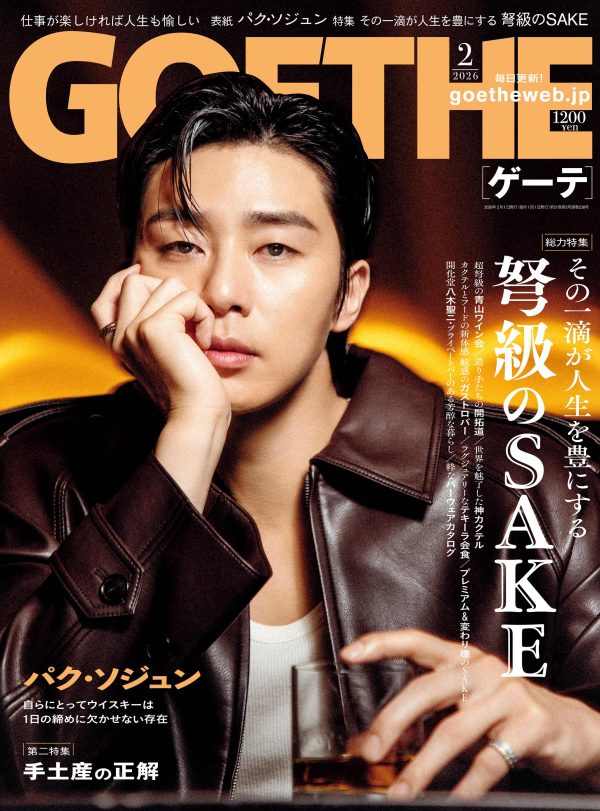ABEMAの番組『愛のハイエナ』の超人気企画「山本裕典、ホストになる。」。そのなかで俳優・山本裕典にホストとしての心意気とテクニックを熱血指導するのがホストクラブブランド、エルコレのプロデューサー“軍神”こと心湊一希だ。強い組織をつくる指導力と相手の心を摑むコミュニケーション術、そしてホストへの転身後に圧倒的な成功を収めた激動の半生を探る。インタビュー第4回は、結果が出る新人教育の極意について。【他の記事はこちら】

ホストを辞めた後の人生まで見据えた教育をする
歌舞伎町のホストクラブ「Lillion(リリオン)」「LiTA(リタ)」には、毎夜新規の客が続々と訪れる。それまでホストクラブになど行ったことのない人たちが訪れ、「ここで働きたい」と熱望する男性たちも多い。
もちろんABEMAの人気番組『愛のハイエナ』などメディアの影響は大きい。しかし同時に、心湊一希(みなといつき)のプロデュースするホストクラブが従来の暗く怪しいイメージとは異なるスタイルを打ちだしていることも、新しいファンを獲得する要因となっている。
「ホストクラブってたいてい照明が暗いんですが、それは完全に店側の都合。暗ければホストの顔がよく見えないし、粗が隠せるから(笑)。でも、マーケティングの観点から見ればお店は明るくて煌びやかな方が売り上げは上がるし、お客様のテンションもアップしますよね。できる限り楽しい時間を提供することを目指しています」
また、従業員の教育にも力を入れている心湊は、国語ドリルを解かせたり、新聞記事を要約させたりしてホストの言語能力・読解力を高める試みも行っている。
「お客様の言葉を理解するための読解力、そして自分の考えを伝えるための言語化力は、ホストにとって非常に重要。国語ドリルは小学3年生レベルからスタートするのですが、できない子も結構多いですよ。
僕が部下の教育においてもっとも大事にしているのは、ホストを卒業した後の人生を見据えた教育をすること。今いる組織に利益をもたらす人間を生産するために教育するんじゃない。その子がどうなったら幸せか、ホストを卒業したら何がしたいのかまで考えて指導する。ホストがひとりの人間として成長し毎日を幸せに過ごせるようになれば、自然とお客様を楽しませられるようになるはず。小手先の技術よりも、とにかく『周りの人に笑顔になってもらいたい』という利他の精神を身につけてもらうことが何よりも大事なんです」

1982年千葉県生まれ。デイトレーダー、営業マンを経て起業を経験した後、34歳でホストに転身。1年目から年間売り上げ1億円を達成し、その後も3年連続で1億円を超える成績を残す。月間最高売り上げは5500万円に達し、圧倒的な成績を収めた後にプレイヤーを引退。現在はホストクラブのブランド、エルコレのプロデューサーとして、新宿・歌舞伎町で「Lillion」と「LiTA」、「MIST」、大阪・ミナミで「GO」を手がけている。ABEMA『愛のハイエナ』の人気企画『山本裕典、ホストになる。』にて、山本裕典を指導する様子が大きな話題に。また、リアルホストドキュメンタリー『エルコレ〜歌舞伎超TV〜』では演者として出演している。
夜の世界だからこそコンプライアンスは徹底的に守る
新人を注意する際は「〇〇はよかった。でも惜しいところがある」と、まず最初に褒めてから課題を指摘、できるだけ厳しい言葉は使わない。「優しくするけど、甘やかしはしませんから」と心湊は笑う。
「これまでのホスト業界には、一緒に働くホストから過剰に搾取するような、偏った構造が一部に存在していました。そうした体質を変えていき、より多くの人が夢を持てる業界にしていかなければならないと考えています」
さらに夜の世界だからこそ、一般企業よりもいっそうコンプライアンスに厳しくあらねばならないとも感じている。
「僕は新人ホストに対して怒鳴ったりはしません。もちろん指導する立場なので時には厳しいことを言いますけど、しっかり愛情を持って接しているつもりです。男の子たちにとっても働きやすい、やりがいのある場所にしたいので」
また、心湊の提案で「Lillion」ではホスト志望者を面接する際にIQテストを受けさせているという。それはなぜか?
「人間って、自分と同じくらいのIQの人との会話が一番弾むらしいんです。日本人の平均IQが100前後と言われているので、ちょうどそのあたりのIQの子を採用するようにしています。決してIQが高いからいい、というわけではないんです。
ただ、IQよりも大事なのは国語力ですね。IQテストと一緒に国語テストも受けてもらっていますが、IQが高くても国語の点数が低いケースって意外と多いんですよ」
国語力、言語力を磨くために、心湊が自分自身にも課していることがあるという。
「僕は約8年間、映画を毎日見るように心がけているのですが、その映画のあらすじや面白さ、魅力、人に薦めるポイントなどを言語化して人に伝えるようにしています。一緒に働くホストの子たちに『この映画を見て、内容を俺に面白く説明して』と課題を与えることも(笑)。そうすると漫然とではなく集中して考えながら映画を見るようになるので、物事の構造を捉える訓練にもなるんです」
第5回に続く。