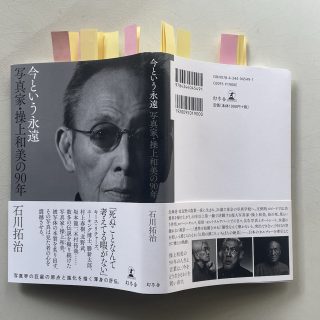第172回芥川賞を受賞した作家・鈴木結生さん。受賞作『ゲーテはすべてを言った』は文豪ゲーテのものとされる名言が「本当にゲーテの言葉であるか」を探し求める物語。主人公・博把統一(ひろばとういち)は真実を追う中で、言葉と文学、愛、家族についての思索を深めていく。一冊を通して、鈴木さんの文学、哲学、芸術に関する博学ぶりに驚かされるが、それ以上に難解ともいえる題材を流れるようにリズミカルに、わかりやすく読ませるアウトプットのセンスに感嘆させられる。インタビュー第2回は鈴木さんの「インプット・アウトプット術」を探る。#1

2001年福島県生まれ。2024年『人にはどれほどの本がいるか』で林芙美子文学賞佳作を受賞しデビュー。2025年『ゲーテはすべてを言った』で第172回芥川賞を受賞。現在は福岡の西南学院大大学院に在籍し英文学を専攻している。
23歳・鈴木結生が“博覧強記”と言われる理由
ゲーテ研究の第一人者・博把統一は家族で出かけたレストランで、紅茶のティーバッグに書かれたゲーテの名言「Love does not confuse everything, but mixes.」に出合う。いかにもゲーテが使いそうな言葉であるが、統一は「本当にゲーテ自身が発したものなのだろうか」と疑問を抱く。その謎解きを軸に小説『ゲーテはすべてを言った』のストーリーは進んでいく。
「ティーバッグのエピソードは実際にあった出来事。父が手にしたゲーテの名言を僕に見せて、“この言葉はどの本に書いてあるの?”と聞いてきた。わかりませんでした。この謎を解決したいとずっと思っていましたが、なかなか手をつけられなかった。謎を解決するには、ゲーテの全集を読破しなければならないですから。そろそろ取りかかってみようと思ったのが、『ゲーテはすべてを言った』を書くきっかけです」
そこから『ゲーテはすべてを言った』を書くためのインプット作業が始まった。図書館に通い、目の前にゲーテの著作や論文、関連書籍、派生文学作品などを積み上げる。本を読みつつ、気になったフレーズをノートにメモ。その姿は「およそ読書とはいえない、美しくないものだった」と鈴木さんは言う。
「1作書くにあたり、関係する本を数百冊は読みます。『ゲーテはすべてを言った』執筆のために読んだ本は500冊。昨年はこの小説を含め2作書いたから、1年間で1000冊ほど読みましたね。僕は“せっかくの時間を損したくない”という思いが強い。読書と創作の両方を同時にできれば、時間が節約できて一挙両得。仕事と趣味を両立できる利点はそこにあると思います」
机に積み上げられた莫大な量の本を読む順序にもこだわりがある。
「小説を書くスタイルは作家それぞれだと思いますが、僕の場合はまず作品の大枠を作ります。そのために最初はゲーテの著作ではなく、ほかの人が書いたゲーテに関する論文を読む。そうして自分の中にゲーテの体系を築いていくんですね。その後にゲーテ自身の著作を読み、小説に使えるデータを抽出。そのデータをゲーテの体系に当てはめていくというスタイルです」
『ニュー・シネマ・パラダイス』の最後のキスシーンのような小説を書きたい

小説『ゲーテはすべてを言った』には文学に関することだけでなく、さまざまな分野の情報が出てくる。食、花、音楽、映画から、漫画『マカロニほうれん荘』(1977年〜1979年に『週刊少年チャンピオン』で連載)まで。鈴木さんが「博覧強記」といわれる所以だが、どのようにインプットの幅を広げているのだろう。
「古いものに触れることが好きなんです。ゲーテ以外のデータに関しては、これまでの人生で経験し、蓄積してきたものが多い。漫画『マカロニほうれん荘』は実際に読んだことがあるし、チャン・イーモウ監督の『初恋のきた道』は何度も観ています。ちなみに『ゲーテはすべてを言った』の中でジュゼッペ・トルナトーレ監督の映画『ニュー・シネマ・パラダイス』についても記述していますが、執筆中にちょうどリバイバル上映をやっていて、最初から終わりまでずっと泣きながら観た。何度も鑑賞しているのに、観るたびに泣いてしまう。あのラストのキスシーンは映画史に残る名場面。映画への愛にあふれた、監督人生で一生に一本しか撮れない映画だと思います。ああいうキスシーンを、僕は小説の中でやってみたい。そのための方法論を模索し続けているんです」
そうした古い物事を、具体名を出して入れ込むことで小説にリアリティが出る。だがリアルタイムで経験していない鈴木さんにとって、時代的な齟齬を防ぐための検証は欠かすことができない作業だ。
「登場人物ごとに年表を作りました。この人物は何歳という設定だから『マカロニほうれん荘』を知っているはず、という具合に。世代感を重視し、登場人物を肉付けしていくことでリアリティが生まれるんです。僕は小学6年で初めて小説を書き始めましたが、どんどん難解になっていき、人が読めるようなものではなくなってしまった。まるで怪文書のよう。自分としては面白かったが、それではダメだと。大人になるにつれて、読んでもらえないことへの恐怖を感じるようになったんです。今は難しい概念的なことを述べるときこそ、リアリティある物語を重視しています」
概念を伝えるために、例話や寓話を用いるのはキリスト教の伝統でもある。「価値がわからないものに、価値のあるものを与えても無駄である」という概念を伝えるために、イエスは「豚に真珠」の寓話を用いた。だが、鈴木さんはそうした寓話の必要性が現代社会において失われつつあると感じることが増えたという。
「同年代の人と話をしていると、現代人は寓話やたとえ話が好きじゃないと感じます。“愛は大切だ”ということを示すために、小説家はたくさんの例話を書いてきました。でも、そんなことはいいから、“愛は大切だと言ってくれ”というのが現代人。概念は概念として直接伝えてほしいんです。でも、それでは簡単な概念しか伝えられないし、聞く方もわかりやすいことしか理解できない。ウィトゲンシュタインが論理学用語を用いて短く端的に言っていることは、僕には理解できません。それを説明するような物語がほしいと思います。難しいことを、誰にでもわかるように伝える。それが小説の機能であり、小説家の役割だと考えています」