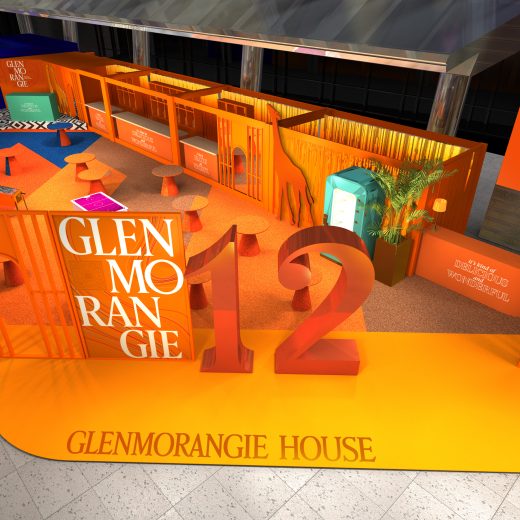デビュー3作目にして本年度の三島由紀夫賞の候補作となった『息』が、2023年5月31日に単行本として発売される小池水音氏。本格的に作家の道を歩み始めた小池氏の書くことに対する矜持、そして、「仕事」に対する想いを語ってもらった。 #1#2#3

小池水音/Mizune Koike
1991年東京都生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業後、出版社に入社し、ライフスタイル誌の編集者として働く。2020年第52回新潮新人賞を受賞、小説家としてデビュー。
筆が進まない時は絶望感すら感じる
この連載1回目で、デビュー作となった『わからないままで』を書き上げるのに約1年かかったと明かしてくれた小池氏。2作目はデビュー翌年の2021年に、3作目は2022年にと、新作を発表するのは、今のところ1年に1作のペースとなっている。それは小池氏が、平日はライフスタイル誌の編集者として働いており、執筆に充てられる時間に制限があるためだ。
雑誌の編集と小説を書くこと。どちらも言葉を使って表現するという共通点はあるものの、小池氏にとっては大きく異なるようだ。
「写真を撮る人、かっこいい服を集める人、ヘアメイクをする人など、雑誌はたくさんの人が関わって成り立つもの。締め切りという期限がはっきりしているので、それに向けて、やるべきことをチームで行い、完成させるものだと思っています。対して小説は、自分で自分を積み重ねていく作業。自分が手を動かさなければ、何も進まないし、ゴールにはたどり着けない。似ているようで、まったく違うという気がしています。
どちらが楽しいか、ですか? うーん、どちらも楽しいです。ただ、小説に関しては、筆がまったく進まないと、ほぼ絶望感しかないですが(笑)」
編集も小説を書くことも「仕事」ではなく「労働」
雑誌の編集者と作家。ふたつの仕事を持つ小池氏だが、「あなたにとって仕事とは?」と尋ねると、意外な答えが返ってきた。
「雑誌をつくることも小説を書くことも、“表現”ではありますし、ある種きらびやかで、有閑的なものに見えるかもしれません。でも、自分としては、自己実現の意味を含む『仕事』というより、日常を支えている『労働』という気持ちが強いですね。その意識をないがしろにしてしまうと、雑誌も小説も不要なものとして消えて行ってしまうのではないかと」
誰かが口にするために野菜を育てる、誰かが暮らすために家を建てる、誰かが通るために道を造る。自分の知恵と時間とエネルギーを使って、人々の生活を成り立たせるのに必要なものを生み出し、提供することで対価を得る。それが、労働だ。だとしたら、小池氏が指摘する通り、雑誌づくりも、人の暮らしを彩るために行う労働に他ならない。小説もまた然りだ。
「僕が書いている家族との相克(そうこく)などが、あまり切実なものと受け取れない、ノイズのようにしか感じない方もいるかもしれません。でも、そうしたノイズは誰の身にも、思いもよらないかたちで訪れうるものです。自分の書いたものがすぐさま多くの人に届いたり、大きな驚きとともに読まれることはなくとも、ある時、ふとしたきっかけで誰かの心の深い部分に通じるかもしれない。小説を書くということは、決して浮世離れした行為ではないと思っていますし、そうであってほしいという気持ちもあります」
遠くで鳴る木々の折れる音を聞き分けるのが小説家

恩人から「水音」というペンネームをつけてもらう際、哲学の認識論を引き合いに、「深い森の中で木が折れて音がしても、それを認識する人間がいなかったとしたら、その音は鳴っていることになるのだろうか」という話をされたそうだ。そして、松尾芭蕉の名句「古池や蛙飛び込む水の音」も、そうしたテーマのもとに詠まれたのではないかと。
「小説家とは、遠く離れた森の木の折れる音や、池に蛙が飛び込んだ時の水の音を聞き分ける存在なのではないかという話をしてくださいました。それで『水音』と名づけてくださったんです」
デビュー作は、姉の死から10年たったからこそ書けたもの。そんな風に「他人が読みうるだけのものを書くには、時間が必要なのだと思う」と、小池氏。
「もちろん、インプットしたものをそのまま表現できる職業ではありませんし、無意識のうちに自分の体験が文章に出てしまうこともあるでしょう。でも、これからどんな体験を重ねるかで、書けるものはきっと違ってくるはず。自分にできることがひとつでも多くなっているよう、これから5年、10年と、より真剣に、誠実に取り組んでいきたいと思っています」
初の単行本『息』が2023年5月31日に発売!

『息』
¥2,090/新潮社
喘息の一息一息の、生と死のあわいのような苦しさ。その時間をともに生きた幼い日の姉と弟。弟が若くして死を選んだあと、姉は、父と母は、どう生きたか。喪失を抱えた家族の再生を、息を繋ぐようにして描きだす長篇小説。新潮新人賞受賞作「わからないままで」を併録。