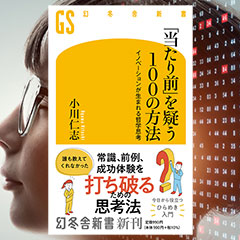AND MORE
2024.06.16
不確実性をそのまま受け止めると、悩む必要はなくなるーーネガティブ・ケイパビリティを身につけろ!
新しい発想で世界経済をけん引する企業が次々と登場する欧米に比べ、なぜ日本ではイノベーションが生まれないのか。それは、欧米では子どもの頃から「当たり前を疑うことが大事だ」と徹底的に教え込まれ、物事を批判的に思考するクセができているから。その教育の根底にあるのが「哲学」だ。好評発売中の『「当たり前」を疑う100の方法』(幻冬舎新書)では、人気哲学者の小川仁志さんが古今東西の哲学から、マンネリを抜け出し、ものの見方が変わる100のノウハウを伝授。本書より、試し読みをお届けします。第4回。➡︎ 第1回から読む

答えを出さない方がいいと考えてみる―キーツのネガティブ・ケイパビリティ
私たちはどうしても答えを出そうとします。そうでないとすっきりしないからです。でも、この不確実な時代、なんでも答えが出るわけではありません。だからモヤモヤするのです。
だとしたら、そもそも答えを出さなくても済むような発想をしたらどうでしょうか。そこで参考になるのが、19世紀初頭のイギリスロマン主義の詩人ジョン・キーツ(1795―1821)が唱えた「ネガティブ・ケイパビリティ」です。あえて訳すなら、消極的受容力とでもいえるでしょうか。
もともとキーツは、詩人や作家の取るべき望ましい態度としてこのネガティブ・ケイパビリティについて論じていました。不確実なものや未解決のものをそのまま受け止める能力のことです。
これによって人は、早急に答えを出してしまうのではなく、本当の正解を導くためにより多くの可能性を残した状態でいられるというわけです。詩などの文学的表現には、まさにそうした可能性、つまり余韻を残した状態が求められるといっていいでしょう。
それは文学だけでなく、あらゆる分野に当てはまります。実際、ネガティブ・ケイパビリティは、後に精神医学などに応用されています。不確実なのに無理に答えを出しても、それが正しいとは限りません。
だとするならば、いっそ不確実性をそのまま受け止めた方が、悩む必要はなくなります。さらにこの場合、事態がはっきりした時には、様々な可能性の中から本当に正しい選択をする余地が残るという利点もあります。
〈こんな感じで使ってみよう〉
Q、ネガティブ・ケイパビリティで判断を留保した方がいい事例を考えてみてください。
A、たとえば、うまくいっていない時に、人生をどうするかは早まって決めない方がいいと思います。そんな時はネガティブ・ケイパビリティで、あえて選択せずに日常を過ごすのです。そうすれば、いずれ自ずと決めたくなる瞬間がやってくるはずです。あるいは、世の中が混沌としている時もそうです。時代が変わろうとしている時に、従来の価値観で物事を判断すると誤りを犯す可能性があります。そんな時こそネガティブ・ケイパビリティで見極める方が賢明です。
PICK UP
-

LIFESTYLE
PR2026.1.9
絶景と美食を満喫できる、“海最前列”の1日2組限定オーベルジュ「UMITO KAMAKURA KOSHIGOE」【ラウンジ会員限定プレゼント】 -

LIFESTYLE
PR2026.1.16
松田翔太「発進から力強くてレスもいい」。軽量&高性能PHEV「マクラーレン アルトゥーラ」に惹かれる理由 -

LIFESTYLE
PR2026.1.19
北海道・ニセコのバックカントリー拠点「ARC’TERYX NISEKO HUT」を体験。そこで触れた真の豊かさとは -

WATCH
PR2026.1.23
TASAKI、ジャパンメイドの高技術ドレスウォッチ -

WATCH
PR2026.1.23
日本が誇る、G-SHOCKの最高峰「MRG-B2100D」 -

LIFESTYLE
PR2026.1.23
鈴⽊啓太、肌ケア“10秒投資”。大人の美容液「SHISEIDO MEN アルティミューン」 -

GOURMET
PR2026.1.23
世界に2つだけ。グッチ大阪の秘密のミクソロジーバーに潜入 -

PERSON
PR2026.1.23
【アイヴァン】市村正親「演技とは、役を生きること」 -

LIFESTYLE
PR2026.1.30
メジャーリーガー・吉田正尚と「レンジローバー スポーツ」。進化を体現する者の邂逅 -

LIFESTYLE
PR2026.2.5
“不可能を可能にする”──ディフェンダーラリーチームがダカールで見せた証明。その挑戦の軌跡
MAGAZINE 最新号
2026年3月号
今、世界が認めるジャパンクオリティ「日本のハイブランド」
仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ3月号』が2026年1月23日に発売となる。特集は、今、世界が認めるジャパンクオリティ「日本のハイブランド」。表紙は中島健人!
最新号を購入する
電子版も発売中!
GOETHE LOUNGE ゲーテラウンジ
忙しい日々の中で、心を満たす特別な体験を。GOETHE LOUNGEは、上質な時間を求めるあなたのための登録無料の会員制サービス。限定イベント、優待特典、そして選りすぐりの情報を通じて、GOETHEだからこそできる特別なひとときをお届けします。