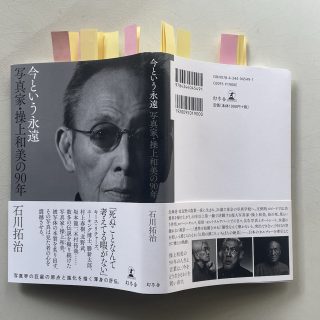世界的文豪、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ。作家のドリアン助川さんは言う。ゲーテの言葉は「太陽のように道を照らし、月のように名無者を慰める」と。雑誌『ゲーテ』2009年4月号に掲載した、今こそ読みたいゲーテの名言を再録する。

この地方を説明せよと言うのか。先ず自分で屋根に上りなさい
――『ゲーテ格言集』より
他人の言葉を聞いて知ったつもりになるな。自ら足を運び、自らの目で見、自らの耳で聞き、その体験をおのれのものとせよ。ゲーテはそんなふうに言いたかったのだろう。わかりやすいメッセージだ。だが、この警句は、大人ならばさらに一歩踏み込んで捉えた方が良さそうだ。
実は、自らの目で、自らの耳で、という部分がくせものなのだ。他者からの説明、現代はそれがマスメディアやネットでの言説になるのだが、もちろんそれをうのみにしてしまう人に比べれば、自らものを見ようとする人の方がはるかに主体的であることは理解できる。
しかし、自らの目は本当に信用できるのだろうか? 誰もが自らの目で見さえすれば、それぞれの真実に近付けるのだろうか?
これに関して、私などはあまり肯定的ではない。経てきた歳月の分だけ、どんな人にでも過信があり、愚鈍があるものだと思っている。新たな体験が体験に成り得ず、逆に視界が曇りがちになっているのが私たち大人なのではないか。「最近の若い連中は」「世の中意味不明だよね」などと言い始めたら要注意。培ってきたはずの感性も、放っておけば瓦礫となる。それが障害物となり、大人を屋根に上らせなくなるのだ。
では、もう一度屋根から世界を見てみたいと願うピーターパンやウェンディはどうすればいいのか。単純なことで、世界を見たがった幼き日々にもう一度戻ればいい。母親に手を引かれ、「お母さん、あそこの奥にはなにがあるの?」と駅の改札口を指さしたその時代の目を取り戻すことだ。
これは私が実際に体験したことだ。知人を千駄ヶ谷の駅前で待っている間、自分の感覚を三歳ぐらいまでに戻してみた。すると帰宅ラッシュのなか、銀色の自動改札と、そこに小走りに吸い込まれていく人たちが、なにかとても不思議な存在に見え始めた。あの人たちはなぜあんなに急いでいるのだろう? あの銀色の扉の奥になにか楽しいことが待っているの? それとも、大人は自分を粉々にしたくなるような気持ちになることがあって、二度と戻れないあの門のなかに自ら吸い込まれていくの?
こうした感慨を得てからまわりに目をやってみると、見慣れたはずの東京が、未踏のバビロンの街のように妖しく迫ってきた。世界は再構築され、私は一篇の詩を書いた。屋根の上から新しい街が見えたからだ。
――雑誌『ゲーテ』2009年4月号より
Durian Sukegawa
1962年東京都生まれ。作家、道化師。大学卒業後、放送作家などを経て'94年、バンド「叫ぶ詩人の会」でデビュー。'99年、バンド解散後に渡米し2002年に帰国後、詩や小説を執筆。2015年、著書『あん』が河瀬直美監督によって映画化され大ヒット。『メキシコ人はなぜハゲないし、死なないのか』『ピンザの島』『新宿の猫』『水辺のブッダ』など著書多数。昨年より明治学院大学国際学部教授に就任。